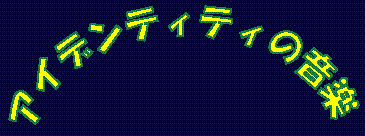BOOTLEG !
投稿日 2000年8月23日(水)18時04分 投稿者 中川大一
[cs25229.ppp.infoweb.ne.jp] 削除
田中さん はじめまして
中川大一@世界思想社編集部です。
最近の若い人は、CDをレンタルしてきてCDにコピーするって聞きましたけど、ホントですか? どうやったらそんなことができるのかしら。パソコンで? 音質は落ちないのかな。
学術書は、漫画みたいに海外で海賊版が出回ることはありませんが、コピーの問題はやっぱり頭痛の種。苦労を重ねてレイアウトしたり間違いを正して完成させても、アッという間に複写できちゃう。250ページの本が、見開きでコピーするから1枚10円でも1250円。もっと安いとこもあるだろうし、これじゃ勝ち目はないよ。本は材質じゃなくって内容に価値があるわけだから、コピーは窃盗と同じだ、というのが出版社の立場。しかし、中味は著者が考えたものだから著者のもの(著作権)。あんまりつきつめると出版社の取り分ってレイアウトくらいしか残らない
(版面権)からそーっとしておこう、という雰囲気もあります。
渡辺ゼミの学生さんは、本ができたらコピーなんてしないで買ってくださいねヽ(^0^)ノ また、反論をお待ちしています。
戦う前に負けています
投稿日 2000年8月23日(水)22時35分 投稿者 今井壮之助 [n2mng054.avis.ne.jp] 削除
田中勇輔さん、あなたの海賊盤に対する意見は、むしろ85%で擁護してしまっていて、15%で音楽業界の損失、つまりレコード店の不利益を訴えていますね。ベースにあるのは法的な善悪で、だから海賊盤のサイトは正しいという結論。海賊盤サイトの連中に自信と勇気を与えてしまっています。
私はサーチエンジン数社に抗議したんですが、無視されました。それは次のような内容です。
# 貴社が「CDのデーターベース・サイト」として紹介している数サイトはす
# べてブートレグのデーターベースであって、オフィシャルのデーターベース
# ではありません。ご存じのようにブートレグはモグリの稼業であって、オ
# フィシャルの作品を調べたいビジターの希望を満たすものではありません。
# ブートレグ専門サイトを貴社が認めるのは自由ですが、「ブートレグ専門の
# データーベース・サイト」と紹介するのが妥当ではありませんか。
とある町を訪れたら駅前商店街がすべてポルノショップだったようなものです。海賊盤を擁護するような発言はつけあがるだけ、慎むべきだと考えます。私は海外のメーリングリストに参加しているんですが、日本が話題に上るのは海賊盤についてのものばかり。私はそれを忍者〜ゴキブリ気質と呼んで恥じます。
オフィシャルのデーターベースや音楽の意味を語り合う文化、そうしたものの片隅でひっそりと、ビルの地下でエログッズを売っているような存在であるべきです。
ロバート・フリップは言いました、ブートレグはレイプされたような不快感だと。田中さんの意見にミュージシャンへの配慮が0%だったのが悲しかったし、私はミュージシャンへの尊厳を第一に考慮する主義です。この尊厳とは金銭的利益ではなく、創造的作品への敬意です。
こういう抗議をサーチエンジン社にレコード販売業界として行うことを提案したのです。繰り返しますが、法的に切り出すと、戦う前に負けます。ミュージシャンへの尊厳を重んじれば正義の女神は販売業界の側にあります。この私の提言を活用されることはいといません。
Re: 1%の重み
投稿日 2000年8月23日(水)22時32分 投稿者 今井壮之助 [n2mng054.avis.ne.jp] 削除
私の著作は寄贈されたロック・メディア全誌が書評を拒否したといういわく付きの書ですから、渡辺さんが躊躇ったというのもわかります(笑)。
ただ私は、書評を望んだというよりも、貴サイトの膨大なロック文献リストに加えていただきたかっただけです。というのは、ポピュラー音楽をテーマに卒論を書く大学生が貴サイトにアクセスするようですので。文献リストには確かにピンク・フロイド関連書がありましたが、あれは芸能雑誌のノリの翻訳本です。それよりも、ピンク・フロイドの音楽の神秘性にテーマを絞った弊著の方が卒論にインスピレーションを与えるのではないかと考えたまでです。
ネット検索でピンク・フロイドを調べても、海賊盤マニアのコレクションを見せつけられるばかりで、肝心の音楽の意味について本格的な評論を提供しているのは弊サイトぐらいなものです。日本の場合ですが。そうですね、大学生のロックの卒論を書く参考として、「プログレッシブロックを日本語で歌う会」(http://www.threeweb.ad.jp/~tanei/progre/) などが最適でしょう。英語の歌詞を独自の解釈で翻訳して批評し合うもので、ロック+英語の勉強にもなります。
MDだのDVDだのと音楽環境が今、大きく変化しつつありますが、夢も現実も目を閉じれば同じ(*)……、目を閉じればLPもCDもMDも同じではないですか。それらの出所は一律、ミュージシャンの魂です。
普遍的なロックの意味から目を逸らすことなく、若い世代にも伝えていく責任があります。「中高年ロックファンのライフスタイル」みたいな話題が多いようですが、ロックのメッセージに自分のライフスタイルを見い出すのをベースとすべきで、ノスタルジーをベースにしてしまうと世代に溝が生じてしまうでしょう。私は50代ですが。
(*)=何かの歌詞の引用と思ったら著作権に触れるけど、思わなければそうではない(笑)。
http://www.avis.ne.jp/~fancysc/
参考文献に載せました
投稿日 2000年8月24日(木)02時21分 投稿者 juwat [x-wing033.fu.comlink.ne.jp] 削除
今井さん
再度の書き込みありがとうございます。ご指摘を受けましたので、さっそく『アイデンティティの音楽』の参考文献に載せました。しかしもともとのロック音楽文献については、他のジャンルも含めて、ここ数年ほとんど更新していません。整理する時間がないのが主な理由です。断ってありますように、このリストは阪神大震災で研究室の書架が倒れたときに、データベース化したものです。大学を代わったのを機会に追加を考えたのですが、時間がとれませんでした。
田中君の返答にはなかなか厳しい意見がきたなと思いました。彼は仕事を始めて半年の見習いです。彼の店にやってくる横柄なお客には優しい視線を向けていらっしゃるのですから、彼にも暖かいまなざしを向けてほしいと思います。
彼もそうだと思いますが、ぼくは海賊版についての日本のサイトをほとんど知りません。ちょっと調べてみたいと思いますので、ぜひ情報をお寄せ下さい。
>ロックのメッセージに自分のライフスタイルを見い出すのをベースとすべき
全くその通りです。しかし、今の自分を考えることには当然、過去を振り返る作業が必要になります。と言うよりは、原点にもどって現在までの道筋をたどることが必要になります。その時に50年代や60年代の音楽に懐かしさを感じるのは至極当たり前の心情のように思います。ノスタルジーはそれ自体は悪いものだと思いません。それだけだと、うんざりしてしまいますが………。
ぼくは今井さんとは違って、一途に一人のミュージシャンや一つのバンドを追いかけることはしていません。一時期ディランにのめり込んでいた時期はありますが、今は誰に対しても、距離感をもって接しているような気がします。同世代の人たちには特にそうです。半世紀も生きてくれば、誰でも、社会的な立場や、それなりの経済的な資産、あるいは政治的な発言が与える影響などを無視して発言や行動や表現がしにくい状況におかれるようになります。もちろんミュージシャンとて例外ではありません。そこまで含めて、ロックにつきあっていく。「ロックのメッセージに自分のライフスタイルを見いだす」というのは、ぼくにとってはそういうこととして意味を持っています。
ピンク・フロイドについて書かれた本は確かに「芸能雑誌のノリの翻訳本」かもしれません。しかし、ぼくにとっては事実を知る上で結構役に立ちました。ミュージシャンをテーマにした本はたいがいその手のものですが、誰がどんな理由や関心で読むか、どのように役に立つか、どんな影響を与えるか、といったことは、また多様なもので、一概にだめと烙印を押すことはできないように思います。これもまた田中君の店にやってくるしょうもない客が持っているかもしれない可能性を優しく見つめる視線につながるのかもしれません。
中川さん
本のコピーは、実はぼくもよくやっています。しかし、品切れで、学生に買わせようと思っても本がないことが多いのです。また、Amazon Comで便利になったとは言え、英書の場合には時間がかかりますから、ついついテキストをコピーでと言うことになってしまいます。もちろん、出版状況の厳しさは承知していますから、気持ちはいつでもアンビバレンツな状態です。今度の本がでたらもちろん、学生には勧めますが、しかし、学生は本当に本を買いません。電話代できゅうきゅうとしているのです。音楽の海賊サイトがはやるのも、やっぱり同じ理由によるのかもしれません。コンピュータも含めてソフトが知的資産であることは、もっと議論されていい問題だと思います。
初校ゲラが上がってきました。
投稿日 2000年8月24日(木)14時00分 投稿者 大隅直人 [cs25215.ppp.infoweb.ne.jp] 削除
渡辺先生
本日、予定通り初校のゲラが上がってまいりましたので、控えのゲラ(ちゃんと文字が印刷されています――念のため【笑】)を、クロネコヤマトでお送りします。校正者によるチェックの入ったゲラは、9月9日にお届けする予定ですので、それまでは、この控えゲラでご校閲の作業を進めておいて下さい。
さて、文字校正以外に、とりあえず以下の3点についてご検討いただければ幸いです。
1.本文中の図表でキャプションのないものがありましたが、暫定的に××××××という風にしてスペースをとってあります。ですので、そこを埋めるなり、形式を変更するなり処理をお願いします。
2.以前にも申し上げましたが、本文なり扉なりに写真などを図版を入れるご希望があればお申し付け下さい。
3.目次の扉に、
アイデンティティの音楽
――――――――――――――――――――
メディア・若者・ポピュラー文化
◆
目 次
という個所があります。この◆の場所に、何か本文のテーマに関係するイラストやマークを6ミリ四方ぐらいに縮小したものをあしらうと面白いかなと思っています。何もないようでしたら、印刷所の持っている約物や記号を入れますが、ご検討下さいませ。
以上、業務連絡でした。
図版について
投稿日 2000年8月24日(木)23時41分 投稿者 juwat [x-wing041.fu.comlink.ne.jp] 削除
大隅さん
了解しました。
9日までに一応チェックを完了させておきます。その際、年表と参考文献の追加もしておきます。それから、索引の話をされていましたが、どうしましょうか。もし必要なら、索引マークをつけるようにします。連絡してください。図表のキャプションも了解しました。本文中の図版はどうしますか、コピーがいいのか、スキャナでとったものをフロッピーで送った方がいいのか、印刷の段階になったら、原板がいりますね。その点もお知らせ下さい。目次の扉のマークですが、ピース・マークではどうですか。手に入りそうでなかったら、こちらで探してみますが、これもどういう形で送ったらいいのか連絡をお願いします。
以上、業務連絡への返事でした。
それでは。
ゲラが届きました
投稿日 2000年8月26日(土)00時04分 投稿者 juwat [x-wing012.fu.comlink.ne.jp] 削除
大隅さん
本日ゲラを受けとりました。なかなかいいレイアウトだと思いました。索引もちゃんと目次に入ってますね。マークをつけておきます。いろいろ用事があって読むのは来週中頃まで無理なのですが、気になって、ついついぺらぺらと見てしまいました。
明日は早起きして東京に行かなければならないのです。
それでは。
はじめまして
投稿日 2000年8月26日(土)11時42分 投稿者 いのうえさち [pfa40ba.tck4.ap.so-net.ne.jp] 削除
はじめまして、井上幸といいます。
先生のホームページをみて、連絡をとらせていただくようになりました。私は60年代とその時代のロックに関心を持っています。大学では「1960年代、アメリカのサイケデリック文化にみる陶酔と覚醒」というテーマで卒業論文を書き、現在は研究生として1年間、 アドルノの文化産業論とロックについての考察をしています。秋には東京経済大学の大学院を受験しようと考えています。後期の授業が始まったら一度先生の研究室をおたずねすることになると思います。色々な情報や助言をいただけたら幸いです。
願書と過去問題を大学へもらいに行きました。 今、研究計画書に悩んでいます。 私はロックについて考えたいことがたくさんあってなかなか考えがまとまりません。考えがまとまらなくてモヤモヤしてしまう私をレコードが救ってくれています。この頃はストーンズばかり聴いています。ブライアン・ジョーンズがまだ輝いていた頃の初期のストーンズが私には良い特効薬になっています。
いつでもどうぞ
投稿日 2000年8月27日(日)00時23分 投稿者 juwat [x-wing045.fu.comlink.ne.jp] 削除
井上さん
研究室にはいつでもお訪ねください。ただしにぎやかな院生がいますから、圧倒されないように。サイケデリックの次がアドルノでは、さぞや落差が激しかったことと思います。しかし、ある意味でいえば、ポピュラー音楽について両極を見たと言えるのかもしれません。で、今ブライアン・ジョーンズだというのは、あなたの関心や心理状態がどうなっているのか、逆に知りたい気もします。
いずれにしても大学院を受けられるようでしたら、とにかくまず、試験に通るよう、準備をしておいてください。
それでは。
準備、頑張ります。
投稿日 2000年8月27日(日)18時46分 投稿者 いのうえさち [p84a7b7.tck4.ap.so-net.ne.jp] 削除
渡辺先生
先生のおっしゃるように私はポピュラー音楽の両極をみているように思います。 卒業論文でポピュラー音楽の良い面ばかりを論じ、アドルノのいうような批判には全く触れることがなかったことに気づき「今年はアドルノを」と考えました。すると、今まで自分が考えていたポピュラー音楽(ロック)による若者たちの 一体感はアドルノのいうような文化産業による画一化、全体化になってしまうのか。いや、若者と音楽の関係はアドルノが言う程簡単なものではない、というように私の考えが混乱してしまっているのです。
ブライアンはポピュラー音楽への関心の始まりなのです。15歳の時にジャケットのブライアンと目が合って、ストーンズを聴き始めました。私は原点に戻りたがっているのかもしれません。
|