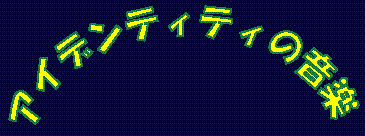再び振られました
投稿日 2000年8月17日(木)18時23分 投稿者 太洋社 滝口 [ns.p-taiyosha.co.jp] 削除
中川さんに再び振られて,再度おじゃまします印刷会社の滝口です。隅と隈を間違えたのはどうも私のようで,11日の中川さん指摘のワープロの変換ミスの代表のようなことをしてしまいました。大隅さん,大変失礼しました。でもどっちも“おおすみ”で出るんですよね。
確かにデータ入稿が増えて直接入力は減りました。現在入力しているのは,数式関係くらいでしょう。Texなんかは電算化しないで直接PS書き出しをしてフィルム出力します。また,一時ほどコンバート出来ないソフトも減りました。そうですね,Macの世界ではクラリスワークスがコンバート出来ませんでしたね。ソフトがなくなる直前に解決されましたが。印刷業界もいろいろ変革が激しく,多くのソフトに対応しなければならないんで,結構大変なんですよ。版元さんによっては,全くデータを確認せずに出稿されるところもありますし,世界思想社さんくらいのレベルにみなさんなっていただければ,我々は大変楽になるんですけど。
中川さんに一言。データ入稿になって(多少変換ミスはあるにしろ)誤植は減りました。でも校正の赤字はあまり減りませんね。これが出版社と印刷会社の永遠のテーマ?
ロックを聴きつづけること
投稿日 2000年8月17日(木)16時18分 投稿者 大隅直人 [cs25238.ppp.infoweb.ne.jp] 削除
2週間前に購入したルー・リードの「エクスタシー」のパッケージを、数日前、ようやく開封しました。先月、渡辺先生のお宅にお邪魔した際に、生活の身近なものとしてロックがごく自然にかかっていることに刺激を受けたせいか、家にいる時にステレオを鳴らすことが多くなりました。
また、最近、中古のMDプレーヤーを買いました。それで、さっそくダビングして持ち歩いています。ちなみに、通勤の途上や移動中の電車で聴くのは非常に心地よいものの、会社の昼休みにはルー・リードは似合いませんね(笑)。そういえば、中高生の頃もいつもウォークマンを携帯していましたが、シンセを多用したニューウェーブやテクノのサウンドは、東京の風景に非常に良くマッチしていました。ボブ・ディランなどのシンプルなロックをじっくり聴くようになったのは、大学に入って京都へ来てからのことです。
ところで、『アイデンティティの音楽』の冒頭近くに、「ぼくはその後現在に至るまで、演歌や歌謡曲に転向することもなく、ロック音楽を聴きつづけている。」という一節がありました。この中の「転向」という言葉に少しひっかかっています。なぜ年をとるとロックを聴かなくなるのか。これは結構重要な問題です。
しかし、それを「転向」と呼んでよいものか。サラリーマンなどをやっていると、そもそもゆっくり音楽を聴く時間というのが絶対的に持てなくなります。一方で、つき合いなどでカラオケを歌う機会というのが出てきます。それで、私なども「ウケ狙い」で演歌や流行の曲が歌えるようにと、ひそかに研究したりすることがあります(笑)。
年相応に聴ける音楽が少ないというのもあるでしょう。私はボブ・ディランの年のとり方が好きです。最近の、非常にナチュラルな、志村けんのような雰囲気にも一種のあこがれを感じます(笑)。しかし、日本人で、そういう意味で共感出来るような歌い手というのはなかなか見つかりません。忌野清志郎も、友部正人も何か違うし、シオンもいまひとつです。小沢健二も面白かったけど、最近は何をやっているのかよく知りません。
なんだかとりとめもなくダラダラと書いてしまいました。ロックを聴きつづけたいという意志だけははっきりしているのですが・・・。
みなさん、何かご意見やアドバイスをお願いします。
「転向」について
投稿日 2000年8月18日(金)10時30分 投稿者 juwat [k1514.k1.tku.ac.jp] 削除
大隅さん
「転向」と使ったのは、それが音楽に限らない問題だからです。「転向」は生活スタイルに関わるもので、音楽はその表層にあるものです。ロックを聴かなくなるのは、それを必要としない生活スタイルに変わったからだと思います。もちろん、それは音楽に限りません。文学でも映画でも、あるいはそのほかのものでも、自分なりの関心を、どこかで捨ててしまってきたのです。
中年以降のそれも男たちを見てください。企業戦士の果てに、リストラ、離婚、さらには子供たちの反乱と大変な状況ですが、彼らには有効な対処法がないのです。
この前中川さんにいわれましたが、中年の生活スタイルは考えなければいけない大事なテーマだと思います。
滝口さん
中川さんのいちびりにもめげずに再度の登場ありがとうございます。誤植は減ったのに赤字はなくならないという指摘は、耳が痛いです。先日、今作成中の本に大いに関係のある本を見つけてしまいました。読んだら、校正で書き加えたくなります。そうすると大隅さんや滝口さんにはいやな顔をされるかもしれません。で、読もうかやめようか迷っているところです。
それでは。
中高年のライフスタイル
投稿日 2000年8月19日(土)06時05分 投稿者 八子 [zaqd2bd3c26.zaq.ne.jp] 削除
お久しぶりです。
最近、NAP STERから音源をダウンロードするのに凝っていて、昼夜逆転の生活を送っています。ちょうど、音楽を聴き始めた頃、私が中高生の頃にに聴いていた音楽を、集中的にダウンロードしています。
あの頃は、学校から帰るとラジオにかじりついて、必死で聴いていました。音楽を一番集中して聴いていた頃ではないかと思います。フォー・シーズンス、ラスカルズ、ソニー&シェール、ビーチボーイズ等々。とにかく、アメリカのヒットチャートにはまっていました。あの頃の曲は、ほとんどが2〜3分という小粒の世界ですが、分かりやすくシンプルでキャッチーなメロディと、完成度は驚くほど高かったように思います。今聴いても、というより今だからこそでしょう、ほんとに胸にシミます。
中高年のライフスタイルについてですが、確かに、今一番中、途半端な位置に佇んでいるのが中高年男性であるような気がします。老け込む年でも立場ではないが、かといって時代の潮流からはちょいずれてて。べたなギャグではありませんが、「ちゅうとはんぱやなあ!」みたいな。
今月号の文芸春秋に村上龍とソニーの久多良木健氏による「ITに怯えるおじさんたちへ」という笑えるタイトルの対談が載っていました。要するに、ITなんぞに惑わされず、自分のやりたいことを見つけて、それをやり続けなさいという話で、ちょっと複雑な気持ちになりました。「それは、若いもんにいうセリフやろ!」という感じ。まあ今の時代、「おじさん」に対するアドバイスなんてこんなもんなんでしょうね。情けない。
と思いつつ、深いところでは納得もしてるのが、おじさんの中途半端なところ。
おじさんたちはどこへ行く?
投稿日 2000年8月21日(月)00時38分 投稿者 juwat [x-wing010.fu.comlink.ne.jp] 削除
八子さん
書き込み、感謝します。
50年代から60年代前半にかけてのアメリカの音楽は、ぼくにとっても出発点で、時々かけては懐かしがってます。小遣いをためてはドーナツ版を買ってた時代で、60年代の後半からはLPしか買わなくなりました
去年、大学でポピュラー音楽についての特別講義をやって、毎回ゲストを招いたのですが、50年代から四谷でジャズ喫茶をやっていた人は、その存在価値を、レコードを買うお金がなくて、聞きたいものを聞く場所だったのだと話されました。60年代後半のロック喫茶も同じでしたが、そういえば、レコードの値段は高かったと思います。今は、安く手に入りますね。NAP STERだとお金はかかりません。これは音楽にとっていいことなのでしょうか、それとも悪いことなのでしょうか。
おじさんたちはどこへ行ったらいいのか、本当に切実な問題だと思います。だからこそ、ロックやフォーク世代のミュージシャンには、今の同世代の状況を歌ってほしいと思うのですが、泉谷はテレビでぼやくばかりですし、南こうせつは懐メロ専門で、吉田拓郎はガキに迎合してばかりです。なぜ日本にはヴァン・モリソンやルー・リードやニール・ヤングのような人がいないのでしょうか?
今日Wowowでサザンのライブを見ましたが、ばからしくなって途中でやめました。年齢を感じさせながら、なおかつ格好いいという変化ができていないと思いました。
音楽との出合い、音楽の意味
投稿日 2000年8月21日(月)13時30分 投稿者 今井壮之助 [n2mng039.avis.ne.jp] 削除
「Mailから」でレコード店に勤務される田中勇輔さんの意見を拝見しました。はじめて聴くレコードに「意味」を求めて購入するのは極まれなケースでしょう。「○○のCDどこにあんのぉ?」という田中さんにとって煩わしい客というのは、ちょっと興味を抱いたから売場に来たのであって、ヒット中だということもジャンルも知らないから、どこに陳列しているかも知らないのです。
皆さんの最も大切なバンドのレコードを初めて探したときのことを思い出してみてください。レコード店を訪れてその場所へまっすぐに進めましたか? 店員に「自分で探す努力も必要」という視線を感じるのは辛いものです、ビギナーにとっては。
そして、やがてそのビギナーがそこで購入したレコードが最も大切なバンドに昇格しているかも知れません……。音楽の深い意味を考察する思索派オーディエンスとて、所有レコードの90%には何も意味を見い出せなくて聞き流していると思いますよ。したがって、レコード店の方はそういう90%を相手にしているわけです。
変えるぐらいの重みのあるレコードがあるのです。そう、それは一日100人の客がいればたった1人ということになります。
田中さんはそういう音楽ワールドの入口の番人で、客は入口ではまだ何も語れません。「意味」を考察するのはいわば音楽ワールドを出たあとの「能動的な行為」です。それが渡辺さんのフィールドという意味で、田中さんがそこまで足を延ばしている(そういうサイトに加わる)というのは有意義なことですね。
ところで、ネットの検索であるバンドのサイトを探すと、データベースの提供といううたい文句の実態はすべて海賊盤の紹介(実は目的はそのトレード)であるという現状をどう思われますか? つまりサーチエンジンであたかも推薦されているのをレコード販売業界で阻止できないのでしょうか(サイトの閉鎖ではなく、海賊行為はコソコソやるべきで、サーチエンジンからはずすべきという意味です)。
渡辺潤さんの「音楽が意味のあるものとして聴かれていない」件について。ポップスや抽象音楽とは異なり、ロックは「意味」が進化した音楽のはずです。やはり英語の歌詞が軽視されるという致命傷の深さは、英語風に歌えばサマになるという勘違いの根強さから測ることができるでしょう。
文学作品または映画に「意味」があるのはだれでも承知しているんですが、音楽には詞という言葉を超えたところにも意味がある。ゆえに困難であり、しかるに人間そのものを探究するメディアになり得ると思います。
「なぜ音楽の意味を考えるのか?」「そこに意味があるからよ」という私の考察を別のBBSにポストしたばかりなので、参考になれば……。
↓
http://bbs.cafe.ne.jp/usr2/1127/a/index.cgi
1%の重み
投稿日 2000年8月22日(火)00時01分 投稿者 juwat [x-wing026.fu.comlink.ne.jp] 削除
今井さん
お久しぶりです。
あなたの書かれた『ピンク・フロイド 幻燈の中の迷宮』(八幡書店)を紹介されて、すぐに読みました。その独特の世界を書評したいと思いましたが、なかなかうまい切り口が見つからず、そのままになってしまいました。ごめんなさい。
あなたが言うように、深い意味を見いだせるのは1%程度なのかもしれません。しかし、50年代以降に出されたレコードやCDは膨大ですから、その1%でもかなりの数になるはずです。ポピュラー音楽は文化産業の中の一番手軽な商品ですから、ジャンクが目立ちますが、探せば、いいものも多いのです。そのようなものを並べていけば、音楽が文学や映画に劣るものでないことは分かるはずです。
学生のころにディランの海賊版をなけなしのお金をはたいて何枚も買いました。有名なライブ、あるいは売り込みようのデモ・テープなどで、音は最悪でしたが、オフィシャルのものとは違う興奮を感じました。
net検索での海賊版紹介はそれとはずいぶん違いますね。お金を払わずに、聴きたい曲が手にはいるという、それこそ現金な都合を感じます。とは言え、ポピュラー音楽の著作権って何なのか、という疑問も昔から感じています。ある種の伝承性、悪く言えば「パクリ」が当たり前の世界です。それが市場の巨大化で、莫大なお金が動く産業になっている。
だから、ただで手にはいるのなら、それもいいじゃないかという気にもなります。
ラップのようにサンプリングによって成立したジャンルもありますし、なかなか難しい問題だと思います。
ところで田中君。今井さんにぜひ返答してあげてください。
はじめまして。
投稿日 2000年8月23日(水)03時14分 投稿者 田中勇輔 [fkcy0103.ppp.infoweb.ne.jp] 削除
下で今井さんにメールを読んでいただいた田中勇輔です。去年まで渡辺先生のゼミでお世話になっていました。
今井さんの御意見は大変参考になりました、明日からの仕事に生かしたい思っています。
>店員に「自分で探す努力も必要」という視線を感じるのは辛いものです、ビギナーにとっては
この御意見には耳が痛かったです、少し仕事に慣れると仕事が雑になりますから、初心を忘れてはいけませんね。しかしお客様には色々な方がいらっしゃいます、CDを買いに来店されたのか、店員に喧嘩を売りに来られたのか分からないような方とかいらっしゃるのですが、こういったお客様に気持ちよく帰っていただけるようになれば一人前なんでしょうね、まだまだ接客の修行が足りません。
まだまだ半人前ですが1人でも多くのお客様に音楽を聴いて頂きたいという思いは強いです。「世の中には色々な音楽がありますよ」ということをアナウンス(お節介とも言いますね)できて、そのアナウンス(お節介)に耳を傾けてくださるお客様が増えてくだされば嬉しいですね。接客同様こちらも修行が必要ですが。
>ところで、ネットの検索であるバンドのサイトを探すと、データベースの提供といううたい文句の実態はすべて海賊盤の紹介(実は目的はそのトレード)であるという現状をどう思われますか?
業界全体にとって由々しき問題です。しかし規制するのは非常に困難だと思います。相手は「自由」が売りのりのインターネットですから法律による規制も難しいですし、渡辺先生も書き込みをされていましたが、音楽を作る現場ではサンプリングという手法が日常茶飯事であり、また現在の著作権の在り方自体に批判があったりするので一筋縄では括れない問題です。ただ一つ言えることはこの現状を放置しておけば音楽業界は大きな損失を被ることは確実です。
|