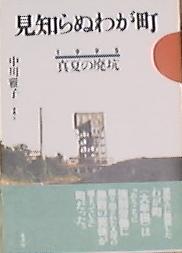『見知らぬわが町』
−真夏の廃坑−
中川雅子(葦書房、1995)
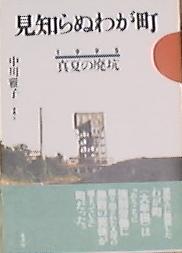
この本は、自分探しの迷路のなかにいる一人の高校生の少女が、自転車であてどもなくさまようなかで、住み慣れた大牟田の町の風景を読み替えていく、その過程を綴った本である。いつもの当たり前の世界にいるかぎり、町の風景はいつもと同じで、何も新しいものは見えてこない。しかし、ふとした拍子で、安定していたはずの世界に、大きな裂け目があることを感じることがある。それは、人とわかりあえないという悩みからはじまるかもしれないし、自分が一人ぼっちであることを痛切に思い知るところからはじまるかもしれない。自分が構築しつつある世界と、常識的な世界の亀裂は、大人の物語をこわし、自分の物語をつくり始める、思春期に、最も深くなることが予測される。この亀裂は、若者のなかに、世界に対するはちきれんばかりの欲動を生み出す。この欲動は、学びへの抑えがたい欲求にもなるし、暴力や犯罪へのエネルギーにもなり得る。
この本の著者中川さんもまた、自分と世界との大きな亀裂を感じていたに違いない。なぜならば、寂れゆく平凡な地方都市の地底(じぞこ)に横たわっている魔界を見据える力は、自分のなかに自己と他者との亀裂感を抱えた者ではなくてはもち得ないものだからである。
おそらく日本の高校生は、各世代のなかで一番難しい文章を読み、一番勉強をしている層だろう。しかし、その勉強の多くは、あらかじめ大人によって構築された世界像をアメーバーのようにひたすら吸収するものではないだろうか。自己と他者の亀裂に悩み、その悩みをナイフとして、常識的な世界を切りひらいていく、そのような学びに至る者は、稀有なのではないだろうか。
中川さんのすごさは、自らの内なる亀裂を通して、一見平和に見える地方都市の地底(じぞこ)に眠る囚人労働者たちの声、朝鮮人労働者たちの声を聴き分けようとしたところにある。実は、彼女が探し出し、炭鉱の囚人労働者の墓地ではないかと推測している無縁墓地は、わたしの実家のすぐ近くにある。高校の頃、わたしは毎日のようにその無縁墓地の脇を犬を連れて散歩したものだった。夜暗くなると、何か出そうだと早足で駆け抜けた無縁墓地。あそこに世界の裂け目がぽっかり穴をあけていたとは。まさに、見えども見えず、聞けども聞けずのわたしだった。
歴史を通して、自分を発見していく中川さんのこの学びのスタイルこそ、これからわたしのゼミナールで追求していきたい姿だと思わされた。