丂丂2002/12/29(Sun)丂亙擭偺悾亜
丂崱擭傕傑偨侾擭偑廔傢傠偆偲偟偰偄傞丅悢帤偑偡傋偰曄傢傞1999擭丄怴偟偄悽婭偵曄傢傞2000擭丄儚乕儖僪僇僢僾偺擭偵曄傢傞2001擭偲偙偙悢擭偺擭偺悾偼丄擌傗偐偩偭偨丅偟偐偟丄2002擭偺擭偺悾偼扺乆偲曢傟傛偆偲偟偰偄傞丅偙傟偐傜偼傎傫偲偆偵廔傢傝側偒擔忢偺偼偠傑傝側偺偩傠偆丅悽婭枛丄怴悽婭偺偍嵳傝偺偁偲偱丄擔忢傪偳偺偔傜偄惗偒惗偒偲惗偒傞偙偲偑偱偒傞偐丄崱丄侾擔侾擔偺墿崹傪惿偟傒側偑傜丄傏傫傗傝偲峫偊偰偄傞丅
丂偦偟偰丄崱擔偼丄崱擭偺係寧偵憙棫偭偰偄偭偨懖嬈惗偨偪偲怴廻偱堸傫偱丄偨偔偝傫榖傪偟傑偟偨丅傒傫側偦傟偧傟偺悽奅偱傕傑傟偰丄傂偲傑傢傝傕傆偨傑傢傝傕戝偒偔側偭偰偄傞傛偆偱丄偨偺傕偟偔姶偠傑偟偨丅巹偵偲偭偰傕丄斵傜偲榖傪偡傞偙偲偱帺暘偺崱傪妋偐傔傞偙偲偑偱偒丄侾擭偺偟傔偔偔傝偲偟偰傛偄堦擔偵側傝傑偟偨丅
丂偍偦傜偔崱擔偱儂乕儉儁乕僕傕崱擭偺巇帠擺傔丅侾擭娫丄偁傝偑偲偆偛偞偄傑偟偨丅姦偝偑偙偨偊傞擭枛偱偡丅偳偆偐偍恎懱偵偍婥傪偮偗偰偍夁偛偟壓偝偄丅偟偭偲傝偟偨擭枛丄擭巒傪両
丂丂2002/12/25(Wed)丂亙椃偺偙偲亜
丂椃偵弌傞偨傃偵丄乽側偤巹偼椃偵弌偰偄傞偺偩傠偆偐丠乿偲巚偆丅椃偵弌傞偨傃偵丄偄偮傕乽椃側傫偰偟側偗傝傖傛偐偭偨乿偲巚偆丅傂偲傝傏偭偪偺屒撈丅嶻傑傟偨偽偐傝偺愒傫朧偺傛偆偵怺偄庘偟偝偵曪傑傟傞丅偦傟偱傕丄偦偺怺偄埮傪撍偒敳偗傞偲丄堦嬝偺岝偑幩偟崬傫偱偔傞丅崱夞偼丄旘峴婡偐傜傒偨撿偺嬻偵婸偔惎乆丅壏偐偄傕偺偑帺暘偺側偐偵惗傑傟偰偔傞丅偦偟偰丄怴偟偄帺暘偲弌夛偄丄偦傟偐傜傛偆傗偔丄巹偺椃偑偼偠傑傞丅
丂丂2002/12/23(Mon)丂亙婣娨亜
丂偟傇偲偔柍帠惗娨偄偨偟傑偟偨丅嵞傃儀僩僫儉傊偺椃偱偟偨丅儀僩僫儉偺怘偼敳孮偵偍偄偟偔丄惗偒傞偙偲傪姮擻偟偰偒傑偟偨丅儀僩僫儉偵惗偒傞恖乆偺僄僱儖僊乕偼傎傫偲偆偵枺椡揑偱偡丅僶僀僋偑寖偟偔墲棃偡傞奨偱丄堦弖堦弖傪巚偄偭偒傝惗偒偨偁偲丄婣傝偺旘峴婡偺拞偱偼嫊扙姶偲偝傃偟偝偱偄偭傁偄偱偟偨丅壗偐崱偺擔杮偱偼丄惗偒傞偙偲偑傗傗偙偟偔偹偠嬋偑偭偰偄傞傛偆側婥偑偟傑偡丅惗偒傞偙偲偼偄偮偺帪戙傕妋偐偵嬯偟偄偙偲偩偗偳丄偦傟偼杮棃揑偵偼寛偟偰傗傗偙偟偄偙偲偱偼側偄偲巚偆偺偱偡丅岺嬈攑悈偲惗妶攔悈偱僐乕僸乕怓偵墭傟偨僒僀僑儞愳偵棁偱旘傃崬傒丄塲偖巕偳傕偨偪偺巔偵丄恖娫偲偟偰偺偨偔傑偟偝傪姶偠傑偟偨丅偦偟偰丄偙傟偐傜擔杮偱峫偊偰偄偔偨傔偺嵽椏傪偨偔偝傫偄偨偩偒傑偟偨丅
丂悽奅偼崱丄戝偒側塓偺拞偵偁傝傑偡丅僌儘乕僶儕僛乕僔儑儞偺恑峴偼丄儀僩僫儉偵偄偰傕捝愗偵姶偠傜傟傑偡丅巹偼僌儘乕僶儕僛乕僔儑儞偲偼丄惗偒傞偙偲偺宱尡偺婓敄側杒乮愭恑崙乯偺恖乆偑丄擹枾側惗傪惗偒偰偄傞撿乮搑忋崙乯偺恖乆偺惗妶偵堦曽捠峴揑偵戝偒側塭嬁傪梌偊偰偄傞忬懺傪巜偡傕偺偲峫偊傑偡丅偙偙偵懳榖傪偮偔傞偙偲偑偱偒側偔偰偼丄巹偨偪偺枹棃偼傕偼傗側偄偺偐傕偟傟傑偣傫丅杒偲撿偺娭學偼丄傑偝偵妛峑丄嫵幒偺嫵巘偲惗搆偲偺娭學丄幮夛偵偍偗傞戝恖偲巕偳傕偲偺娭學偲僷儔儗儖側傕偺偱偟傚偆丅杒偼撿傪巜摫偡傞偺偱偼側偔丄懳榖偺応偲偟偰帺傜傪奐偄偰偄偐側偔偰偼側傜側偄偺偱偡丅
丂偙偙悢擭丄擔杮偱偼僫僔儑僫儕僘儉偑惙傫偵慀傜傟偰偄偰丄悽憡偺晄埨偑僫僔儑僫儕僘儉偵椡傪梌偊偰偄傑偡偑丄僫僔儑僫儕僘儉偼栤戣偺夝寛偵偮側偑傝傑偣傫丅傕偼傗悽奅偼偁傑傝偵傕暘偐偪偑偨偔憡屳偵埶懚偟崌偭偰偄傞偐傜偱偡丅摨帪偵丄杒偲撿丄傑偨偝傑偞傑側抧堟丄崙乆偺嵎堎傪峫椂偟側偄僀儞僞乕僫僔儑僫儖偺巚憐傕傑偨尰幚棧傟偱偁傝丄栤戣偺夝寛偵偼偮側偑傝傑偣傫丅杒偑杒偲偄偆棫応偐傜尒偊偰偒偨傕偺乮嬤戙偲偄偆憇戝側幚尡偺峴偒媗傑傝乯偐傜栚傪偦傜偡偙偲側偔丄撿偲偺懳榖偺応傪憂傝弌偡偙偲丄偙偺摴偵偟偐婓朷偼側偄傛偆偵巚偄傑偡丅
丂恖惗偺壽戣傪梌偊偰偔傟傞乬椃乭偲乬弌夛偄乭偵偄偮傕姶幱偟傑偡丅偙偺栭丄僄僕僾僩丒儖僋僜乕儖乮偐偮偰偺屆戙僄僕僾僩偺搒丒僥乕儀乯偺僥儘帠審偱垽偡傞恖偨偪傪幐偭偨壠懓偨偪偺僪僉儏儊儞僞儕乕傪娤傑偟偨丅乬椃乭傪偙傛側偔垽偡傞巹偼丄乬椃乭乮偦傟傕怴崶椃峴偱偟偨乯偺搑忋偱柦傪幐偭偨恖乆偲撍慠偺憆幐偵嬯偟傒偺恖惗傪憲傞恖乆偺巔偵偨偩椳偡傞偟偐偁傝傑偣傫偱偟偨丅嬯偟偝偺拞偵偁傝側偑傜丄奜崙偺堚懓偨偪偲庤傪偨偢偝偊側偑傜丄擇搙偲嶴帠傪孞傝曉偝側偄偨傔偵丄恖乆偺婰壇傪崗傓堅楈旇偺寶棫偵岦偗偰恠椡偡傞堚懓偺恖乆偺巔偼丄怱傪懪偮傕偺偑偁傝傑偟偨丅僥儘偲偺偨偨偐偄偼尩偟偄偨偨偐偄偱偡丅寛偟偰揋傪摿掕偟偰敋寕偡傟偽帠懌傝傞偲偄偆傛偆側埨堈側傕偺偱偼偁傝傑偣傫丅帺傜偺宱尡偺婓敄偝偵婥偯偐偢丄抦傜偢抦傜偢偺偆偪偵恖乆偺惗傪埑敆偟偰偄傞帺傜傪尒偮傔傞丄撪側傞帺暘偲偺偨偨偐偄偱傕偁傝傑偡丅捈愙偵偼壗偺嵾傕側偄偺偵斶偟傒偺偳傫掙偵撍偒棊偲偝傟偨堚懓偺恖乆偑丄偦偙傑偱偨偨偐偭偰偄傞偺偱偡丅偣傔偰堚懓偺恖乆偺婩傝偵怱傪崌傢偣偨偄偲巚偄傑偡丅恖乆偵偐偗偑偊偺側偄宱尡偲怱偺岎棳傪梌偊傞乬椃乭偑埨怱偟偰庣傜傟傞丄偦偆偄偆悽奅傪堢傫偱偄偔丄偦偺堦揰傪傔偑偗偰妛傫偱偄偒偨偄偲巚偭偰偄傑偡丅
丂丂2002/12/17(Tue)丂亙弌峲亜
丂嶐擔偱擭撪偺島媊丄僛儈僫乕儖偑廔椆丅栭偼僛儈偺懪偪忋偘偱惙傝忋偑傝傑偟偨丅偦傟偱傕椺擭傛傝偼儃儖僥乕僕偑掅偐偭偨偐傕偟傟傑偣傫丅偁傞妛惗偐傜乽愭惗偼丄巹偺偍晝偝傫偵帡偰偄傞乿偲尵傢傟丄彮乆僔儑僢僋偱偟偨偑丄傕偆庒偔偼側偄偭偰偙偲偱偟傚偆丅偝偰丄僔乕僘儞偑堦抜棊偮偄偨偲偙傠偱丄崱擭傕傑偨偪傚偭偲弌偐偗偰傑偄傝傑偡丅傛偔弌偐偗傞傗偭偪傖側偲巚傢傟偦偆偱偡偑丄偳偆傕巹偼椃傪偟側偄偲惗偒偰偄偗側偄恖娫偺傛偆側偺偱偡丅偍偦傜偔擔崰偼堦斣偁偲傑傢偟偵偟偰偄傞帺暘帺恎傊偺働傾偲懳榖偺偨傔偵弌偐偗偰偄傞偺偩偲巚偄傑偡丅崱夞傕傑偨惗娨傪傔偞偟偰偑傫偽傝傑偡丅偦傟偱偼傑偨棃廡偍夛偄偄偨偟傑偟傚偆丅
丂丂2002/12/13(Sat)丂亙挬從偗亜
丂梉從偗傪傒傞偙偲偼偲偒偳偒偁傞偗傟偳傕丄挬從偗傪傒傞偙偲偼偦偆懡偔偼側偄丅偟偐偟丄崱擔偼傔偢傜偟偔憗婲偒傪偟偰丄壠偺慜偺嶨栘椦偺岦偙偆偵峀偑傞挬從偗傪傒偨丅搤偺挬丄怱懪偨傟傞挬從偗偩偭偨丅枍憪巕偺乽弔偼弻乿偵乽搤偼偮偲傔偰乿偲偄偆偔偩傝偑偁傞偑丄傑偝偵搤偺挬偼偡偽傜偟偄丅搤偺挬偺偡偽傜偟偝偵弌夛偆偲丄憗怮憗婲偒偺惗妶偵偁偙偑傟傞偺偩偑丄枅擔偺拞偵偼崱擔偺傛偆側尒帠側挬從偗偺擔傕偁傟偽丄偳傫傛傝偟偨撥傝偺擔傕偁傞偟丄塉偺挬傕偁傞丅偳傫側挬偱傕丄怴偟偄堦擔偺偼偠傑傝偲偟偰婌傇偙偲偑偱偒傞帺暘偱偁傝偨偄丄偲巚偄偮偮丄傗偭傁傝偳傫傛傝偟偨擔偵偼偆偭偲偆偟偔側傞帺暘帺恎傪庴偗擖傟傛偆偐側偲傕巚偆丅偳偆偐傛偄廡枛傪両
丂丂2002/12/12(Thu)丂亙敿寧亜
丂搶偺嬻偵偼敿寧偑傂偭偦傝偲婸偄偰偄傞丅傆偲拫娫偱傕戝嬻偺岦偙偆偵偼柍悢偺惎偑徠傝婸偄偰偄傞偺偩側偁偲巚偆丅栚偵尒偊傞傕偺偟偐婥偯偐側偄偗傟偳傕丄栚偵尒偊側偄傕偺偑戝愗側壗偐傪巟偊偰偄傞丅
丂偝偰丄拞搰傒備偒偺乽抋惗乿偼傗偼傝椡偑偁傝傑偟偨丅妛惗偨偪偲偲傕偵偟傒偠傒偲挳偒擖傝傑偟偨丅拞搰傒備偒偺壧傪挳偒側偑傜丄乽庛偝乿偺乽嫮偝乿偺傛偆側傕偺傪姶偠傑偟偨丅偦偟偰丄乽庛偝乿偺乽嫮偝乿偙偦偑恖娫偺傎傫偲偆偺椡偱偼側偄偐偲巚偆偺偱偡丅乽嫮偝乿偺乽嫮偝乿傪捛偄媮傔傞偲丄恖娫偼僟儊偵側傞傛偆偵巚偆偺偱偡丅傾儊儕僇偲偄偆崙偑枺椡揑側崙偱偁傝摼偨偺偼丄偦偺楌巎揑側乽庛偝乿偺備偊偵丄柉庡庡媊傪妋棫偟丄懡條側恖乆偺嫟懚傪媮傔偰偒偨偐傜偱偼側偄偐偲巚偄傑偡丅揱摑偲偄偆乽嫮偝乿傪傕偨側偐偭偨偐傜偙偦丄傾儊儕僇偼乽帺桼乿乽暯摍乿偲偄偆壙抣傪媮傔丄悽奅拞偵嫟懚偺堦偮偺僨僓僀儞傪敪怣偟偰偒偨偺偩偲丄巹偼峫偊傑偡丅僀儔僋峌寕傪峴偆偐偄側偐偼丄傾儊儕僇偑丄偦偟偰悽奅偑丄乽嫮偝乿偺乽嫮偝乿傪媮傔傞偺偐丄乽庛偝乿偺乽嫮偝乿傪慖戰偡傞偺偐丄偦偺暘偐傟摴偩偲丄巹偼巚偄傑偡丅
丂栰嶁徍擛偑昤偄偨乽寀偺曟乿偺悽奅丅偁偺愴憟偵摜傒偵偠傜傟傞拞偱偺恖娫偲偄偆懚嵼偺埑搢揑側乽庛偝乿傪尒偮傔傞偙偲偑丄巹偨偪傪媬偆偺偱偼側偄偐偲傆偲巚偭偰偄傑偡丅傾儊儕僇偵廧傓恖乆偑栭偺惎偱偁傞側傜偽丄僀儔僋偵廧傓恖乆偼拫偺惎側偺偐傕偟傟傑偣傫丅巹偨偪偵偲偭偰栚偵偼尒偊側偄偗傟偳傕丄偦偙偵偼摨偠傛偆偵廳偄丄擔乆偺惗妶丄壠懓傊偺垽偑偁傞偵偪偑偄側偄偺偱偡丅
丂丂2002/12/11(Wed)丂亙抋惗亜
丂乽嬻偺捁乿偲棃傟偽師偼乽栰偺壴乿偲峴偒偨偄偲偙傠偩偑丄乽栰偺壴乿偵娭楢偡傞榖偑巚偄晜偐偽側偄偺偱丄暿偺榖戣偱丅擭枛偺俶俫俲峠敀壧崌愴偵拞搰傒備偒偑弌応偡傞偲偄偆偺偑榖戣偵側偭偰偄傞丅拞搰傒備偒偲偄偊偽丄僥儗價弌墘傪偐偨偔側偵嫅傒懕偗偰偄傞壧昉偲偟偰桳柤偩偑丄偄傛偄傛搊応偡傞傜偟偄丅巹偼偙偙悢擭丄峠敀壧崌愴偵朞偒偰偄偨偲偙傠偩偭偨偑丄拞搰傒備偒偑弌傞偲側傞偲丄怱傕梙傟摦偔丅拞妛埲棃偺拞搰傒備偒偺僼傽儞偱丄斵彈偺壧偵偼偟傫偳偄偲偒偵壗搙傕壗搙傕媬傢傟偰偒偨偐傜偱偁傞丅
丂偝偰丄偙傟偐傜峴偆乽惗搆巜摫榑乿偺庼嬈偱丄拞搰傒備偒偺乽抋惗乿傪挳偙偆偲巚偭偰偄傞丅偙偙悢擭傗偭偰偄傞庢傝慻傒偱偁傝丄柦偺廳偝丄弌惗偺婌傃丄乽惈乿偲乽惗乿偺怺偝丄恖娫偺崻尮揑側庴摦惈側偳傪妛傇偨傔偵丄偙偺壧偼奿岲偺嫵嵽側偺偩丅戝妛偺庼嬈偲偟偰丄巹偑堦斣怱偵巆偭偰偄傞偺偼丄搶嫗宱嵪戝妛乽尰戙幮夛偲恖娫乿偱楌巎妛偺杚尨寷晇愭惗偑峴傢傟偨乽弌惗慜恌抐偲恖娫偺惗偺庴梕乿乮偙偺僞僀僩儖偼巹偑彑庤偵偮偗偨傕偺乯偺庼嬈偱偁傞丅偙偺庼嬈偱丄巹偼乽抋惗乿傪挳偒丄椳偑儃儘儃儘偲棳傟偨丅抦偲忣偑傒偛偲偵摑崌偝傟丄妛惗偨偪傪戝偒偔梙偝傇偭偨偁偺偲偒偺庼嬈偼丄巹偺庼嬈偺執戝側傞儌僨儖偲側偭偰偄傞丅
丂拞搰傒備偒偼埫偄偲偄偆恖偑偄傞丅偦偆尵偆恖偼丄偳傫掙偐傜尒忋偘偨惎嬻偺旤偟偝傪抦傜側偄偺偩偲巚偆丅巹偼崅戜傛傝傕孍抧偑岲偒偱偁傝丄孍抧偐傜尒偨悽奅偵偟偽偟偽姶摦偡傞丅偦偟偰丄惗偒偰偄傞婌傃傪姶偠傞丅拞搰傒備偒傕傑偨偄偮傕恖惗偺孍抧偵棫偭偰丄恖娫傊偺墳墖壧傪敪偟懕偗偰偒偨丅偙偺拞搰傒備偒偑丄俿倁偲偄偆崅戜偵偺傏傞偙偲偱壗偑曄傢傞偺偐丅偪傚偭偲晄埨偱傕偁傞丅偱傕丄偒偭偲堦帪偺嵳傝偺偁偲丄斵彈偼傑偨孍抧偵栠傝丄墳墖壧傪壧偄懕偗傞偙偲偩傠偆丅
丂丂2002/12/10(Tue)丂亙嬻偺捁亜
丂嶐擔偼姦偔偰堦擔搥偊偰偄偨偺偩偑丄崱挬偼惵嬻偑嬻偄偭傁偄偵峀偑傝丄偙偙傠側偟偐怱傕怢傃傗偐偵側偭偨傛偆側婥偑偡傞丅偦偆偄偊偽丄崱擔偼捁偺巔傪偄偮傕傛傝偟偽偟偽尒偐偗傞偟丄捁偺偝偊偢傝偑偦偙傜拞偵嬁偒搉偭偰偄傞丅偁傑傝偵傕憗偔朘傟偨愥偺擔偺偁偲丄堦惗寽柦丄塧傪扵偟偵弌偰偒偰偄傞偺偩傠偆偐丅偲偙傠偱丄愥偺娫丄捁偼偳偙偵恎傪愽傔偰偄偨偺偩傠偆偐丅
丂丂2002/12/9(Mon)丂亙愥傗丄偙傫偙亜
丂挬婲偒偰丄壠偺慜偺嶨栘椦傪尒傞偲丄偙偙偼杒奀摴偐偲尒傑偛偆偽偐傝偺嬧悽奅偑傂傠偑偭偰偄偨丅偪傚偆偳僗僞僢僪儗僗偺僞僀儎傪僲乕儅儖偺僞僀儎偵攦偄懼偊偨偲偙傠偩偭偨偺偱丄幵偼抐擮偟偰丄僶僗偲揹幵偱偺捠嬑偵側偭偨丅搶嫗偱偼捒偟偔丄挬偵側傝丄擔拞偵側偭偰傕愥偑崀傝懕偄偰偄傞傕偺偩偐傜丄揹幵偺僟僀儎偼棎傟丄戝妛傑偱棃傞偺偑堦嬯楯偩偭偨丅
丂愥偲姦偝偵恎懱傪恔傢偣側偑傜傕丄僟僀儎偺棎傟偵儂僢偲棊偪拝偔帺暘偑偄傞偙偲偵婥偯偄偨丅媫偄偱偄傞偺偩偗傟偳傕丄晄巚媍偲偁偣傝偼姶偠傜傟側偄丅偦傫側偵悽偺拞丄巚偆捠傝偵偼側傜側偄傫偩傛丅愥側偺偩偐傜巇曽偑側偄丅偦偆偄偆惡偑帹尦偱偝偝傗偄偰偔傞丅
丂側偤偐丄撿偺崙偺恖乆偑丄偳傫側偵尩偟偄惗妶偺拞偱傕丄昁偢拫怮傪偟丄偳傫側偵昻偟偄惗妶偺拞偱傕丄寢崶幃傪惙戝偵廽偭偰偄偨偙偲傪巚偄弌偟偨丅巹偨偪偼丄斵丒斵彈傜傪懹偗幰偲尵偆丅偦偟偰丄懹偗偰偄傞偐傜偄偮傑偱宱偭偰傕昻偟偄偺偩偲尵偆丅偟偐偟丄斵傜偼弸偄抧堟偱惗偒傞帺暘偨偪偺恎懱偺偙偲傪弉抦偟偰偄傞丅偦偟偰丄惗偒傞栚揑偼壗偐偲偄偆偙偲傪揑妋偵捦傫偱偄傞偺偱偁傞丅
丂愥偵偼彑偰側偄丅崕暈偡傞偺傕棫攈偱偁傞丅偟偐偟丄傕偆廫暘崕暈偟懕偗偰偒偨偱偼側偄偐丅偲偒偵偼丄庴偗擖傟偰傒傞偺傕偄偄偺偱偼側偄偐丅愥偵傕丄戜晽偵傕彑偰側偄惗偒暔偱偁傞帺暘偨偪偺偙偲偵婥偯偄偰丄庛偭偪偄偙偲傪慜採偲偟偰悽奅傪僨僓僀儞偡傞側傜偽丄傕偭偲惗偒傞偙偲傪妝偟傔傞偲巚偆偺偩丅
丂巹偑偔偩傜側偄偙偲傪彂偄偰偄傞娫傕丄峑柋怑堳偺曽偼恾彂娰慜偺愥傪僗僐僢僾偱憕偒弌偟懕偗傜傟偰偄傑偡乮尋媶幒偺憢傛傝乯丅偨偩偨偩摢偑壓偑傝傑偡丅偙偆偟偨恖偺楯嬯偺忋偵巹偨偪偺曕傒偑偁傞偺偱偡偹丅愥偑崀傞偨傃偵丄偼偟傖偄偱偺傫偒側暥復傪彂偄偰偄傞帺暘偲偼戝堘偄偱偡丅傑偨丄彍愥傗僟僀儎挷惍偵娋傪棳偝傟偰偄傞岎捠娭學偺恖偨偪偵傕摢偑壓偑傝傑偡丅偛偔傠偆偝傑偱偡丅
丂丂2002/12/6(Fri)丂亙屒撈亜
丂嶐擔偺枅擔怴暦梉姧偵丄崱暿傟偨偽偐傝偺僇僢僾儖偑実懷揹榖偱乽尦婥丠乿偲榖偟偰偄傞偙偲偵偮偄偰偺僐儔儉偑宖嵹偝傟偰偄偨丅偙偺僐儔儉傪彂偄偨婰幰偼丄忢擔崰偐傜婰帠偐傜偆偐偑偊傞懠幰傊偺憐憸椡偺朙偐偝偵宧暈偟偰偄傞婰幰偱偁傞丅僐儔儉傪撉傫偱嬃偄偨偺偼丄斵偑実懷揹榖傪傕偭偰偄側偄偲偄偆偙偲偱偁偭偨丅巹偺傛偆側怑庬側傜偲傕偐偔丄怴暦婰幰偱偁偭偰実懷揹榖傪傕偨側偄偲偄偆偺偼丄僗僑僀偲偟偐尵偄傛偆偑側偄偲巚偆丅斵偼偄偮傕偼岞廜揹榖偱楢棈傪偟丄岞廜揹榖偑側偄偲偒偵偼実懷揹榖傪傕偭偰偄傞恖偵庁傝傞偦偆偱偁傞丅
丂斵偼僐儔儉偵師偺傛偆偵婰偟偰偄偨丅恖偼屒撈偵傛偭偰抌偊傜傟丄帺屓傪宍惉偡傞丅楒垽偼偦偺偨傔偺戝帠側婡夛偱偁傞丅側偺偵丄偺傫傋傫偩傜傝偲偮側偑偭偰偄偰偼丄偳偆偟偰恖偵側傝摼傛偆偐丅変枬偙偦偑恖傪堢偰傞偺偩丅偲
丂抁偄僐儔儉偩偭偨偑丄怺偄姶柫傪庴偗偨丅偦偟偰丄斵偺婰帠偺偡偽傜偟偝偑丄尩偟偄帺屓偲偺懳榖偺拞偱惗傑傟偰偄傞偺偩偲偄偆偙偲傪抦偭偨丅偝傜偵丄変偑恎傪怳傝曉傝丄巹偵乽変枬乿偡傞偙偲傪嫵偊偰偔傟偨妛惗偨偪偺偙偲傪巚偭偨丅
丂堦曽偱丄懠幰偵垽偝傟偨埨怱姶偑慜採偲偟偰懚嵼偟側偗傟偽乽屒撈乿偵側傞偙偲傕擄偟偄偺偩偲偄偆偙偲傕巚偭偨丅偁傞偄偼僐儔儉偵彂偐傟偨僇僢僾儖偼丄崱丄彨棃偺乽屒撈乿偵旛偊偰丄梒巕乮偍偝側偛乯偺傛偆偵偮傞傒偁偭偰偄傞偺偐傕偟傟側偄丅懠幰傊偺憐憸椡偑朿傜傓偙偲偼丄帺暘傪暯埨偵偡傞偙偲偩偲傕巚偭偨丅
丂丂2002/12/4(Wed)丂亙僀償傽儞丒僀儕僢僠亜
丂僩儖僗僩僀偺嶌昳偵亀僀償傽儞丒僀儕僢僠偺巰亁偲偄偆彫愢偑偁偭偨丅戝妛帪戙丄嫵堢妛偺庼嬈偱撉傫偩杮偩偭偨丅偦偟偰丄偟偽傜偔偟偰摨柤偺僀償傽儞丒僀儕僢僠偲偄偆挊柤側嫵堢巚憐壠偑偄傞偙偲傪抦偭偨丅僇僜儕僢僋偺巌嵳偱傕偁偭偨僀償傽儞丒僀儕僢僠偼丄亀扙妛峑偺幮夛亁亀扙昦堾壔幮夛亁側偳偺挊嶌傪捠偟偰丄尰戙暥柧偵懳偟偰塻偄斸敾傪撍偒偮偗偰偄偨丅乽妛峑偑偁傞偐傜恖乆偼杮棃揑側妛傃偐傜墦偞偐傞乿偲偄偆僀儕僢僠偺斸敾偼丄嫵堢妛偵傕懡戝側塭嬁傪梌偊偨丅偦偟偰丄巹偺巚憐宍惉偵偍偄偰傕僀儕僢僠偺塭嬁偼戝偒偐偭偨丅亀扙妛峑偺幮夛亁偺偁偲丄僀儕僢僠偺巚憐偼丄妛峑傪斲掕偡傞峫偊曽偐傜妛峑傪恖乆偺妛傃偺偮側偓栚偲偟偰慻傒懼偊傞峫偊曽偵揮夞偟偰偄偒丄巹傕慡偔摨偠婳愓傪曕傫偩丅
丂僀儕僢僠偺挊嶌偺拞偱偼丄嫵堢偵偮偄偰偺挊嶌埲忋偵丄巹偨偪偺曢傜偟傪尒偮傔捈偟偨亀惗偒傞巚憐亁乮摗尨彂揦乯偵巹偼嵟傕庝偒偮偗傜傟偨丅僀儕僢僠偼丄恖乆偑廧傑偆壠偑婯奿昳乮僈儗乕僕乯偲側傞偙偲偑丄杮摉偵恑曕偲尵偊傞偺偐偲栤偆偨丅傑偨丄恖乆偑廤偄丄梀傃丄惗妶偺応偲偟偨楬抧偑丄偨偩岠棪揑側堏摦偺偨傔偺摴楬偲側傞偙偲偑丄偼偨偟偰恖娫偺朙偐偝傪惗傒弌偡偺偐偲丄撉幰偵栤偄傪撍偒偮偗偨丅亀惗偒傞巚憐亁偼偲偰傕傢偐傝傗偡偄杮偱丄崱偺曢傜偟傪尒偮傔捈偡偄偔偮傕偺庤偑偐傝傪梌偊偰偔傟偨丅
丂偦偺僀償傽儞丒僀儕僢僠偑12寧3擔76嵨偱朣偔側偭偨丅1980擭戙偵偼壂撽傗悈枔傪朘栤偟偨偙偲傕偁傝丄擔杮偲傕怺偄偐偐傢傝偑偁偭偨丅怺偄恖椶垽偲柧濔側榑棟傪寭偹旛偊偨偨偖偄傑傟側巚憐壠偩偭偨丅
丂丂2002/12/3(Tue)丂亙姶摦偲嫵梴亜
丂偟偽傜偔慜偺嫵庼夛偱丄宧垽偡傞摨椈偺彊嫗怉偝傫偑嫵梴嫵堢偵偮偄偰榖偝傟偨丅巹側傝偵棟夝偟偨偙偲傪婰偡偲師偺傛偆側榖偱偁偭偨丅
丂乽嫵梴嫵堢夵妚偑嫨偽傟偰偄傞偑丄嫵梴偼壗偐偲峫偊傞偲偙傟偼巹偨偪偵偲偭偰傕擄偟偄栤戣偱偁傞丅偨偩丄妛惗偨偪偵嫵梴傪偮偗傞傛偆偵偲偄偔傜尵偭偰傕丄嫵梴傪偮偗傜傟傞傕偺偱偼側偄丅嫵梴傪媮傔傞偵偼丄傑偢姶摦偑昁梫偱偁傞丅嫵梴偺岤傒偲怺傒偐傜偵偠傒偱傞恖娫棟夝丄悽奅棟夝偺朙偐偝偵懪偪恔偊傞傛偆側姶摦傪宱尡偟偰偼偠傔偰丄恖偼嫵梴傪昁梫偲巚偄丄嫵梴傪媮傔傞偺偱偁傞丅傑偢巹偨偪嫵堳偑姶摦偟偰偄傞偐丄偦偟偰嫵梴傪愗偵媮傔偰偄傞偐丄偦偙偐傜怳傝曉偭偰尒偮傔偰傒偨偄丅乿
丂傕偪傠傫丄巹偼彊偝傫偺榖傪挳偄偰姶摦偟丄偙偺傛偆側偙偲偽傪帺暘偺拞偐傜帺慠偵敪偡傞偙偲偺偱偒傞嫵梴傪媮傔偨偄偲愗偵巚偭偨偺偱偁偭偨丅
丂偦偟偰丄嶐擔偺僛儈僫乕儖傪寎偊偨丅偦偙偱丄敪昞偝傟偨嶌昳傕屄惈朙偐偱尒帠側傜偽丄偦傟偵懳偡傞妛惗偨偪偺僐儊儞僩傕僀儞僞價儏乕偺岅傝庤偲嶌昳偺嶌傝庤偺巚偄傪媯傒偲偭偨戩敳側傕偺偱偁傝丄巹偼偨偩偨偩姶摦偟丄栙傞偟偐側偄偲偄偆宱尡傪偟偨丅傕偪傠傫丄偙偺傛偆側応偼侾擭偵偦偆壗夞傕偁傞傢偗偱偼側偄丅偟偐偟丄偙偺宱尡偼丄偙偙偵偼偨偟偐偵嫵梴偵偮側偑傞姶摦偑惗傑傟傞搚忞偑偁傞偲妋怣偝偣傞偵廫暘側傕偺偩偭偨丅
丂巹偼帺暘偺巇帠偺堄枴傪傑偩傑偩傢偐偭偰偄側偄丅偟偐偟丄帺暘偺栚偺慜偱婲偙傞弌棃帠傪尒偰偄傞偲丄偦偙偵偼巹偲偄偆偪偭傐偗側恖娫偺堄恾傗巚偄傪偼傞偐偵挻偊偨戝奀尨偑峀偑偭偰偄傞傛偆偵巚偊傞丅戝奀尨傪偳偙傑偱峴偗傞偐丄偦傟偼傢偐傜側偄丅偟偐偟丄偙偺姶摦偼丄彫偝側廙偱戝奀尨偵憜偓弌偡桬婥傪梌偊偰偔傟偨偺偩偭偨丅
丂丂2002/12/2(Mon)丂亙JUST SYSTEM亜
丂姦偐偭偨11寧偑嫀傝丄憗偔傕12寧偑朘傟偨丅2002擭偲偄偆擭傕偁偲侾儢寧傪巆偡偺傒偲側偭偨丅尋媶幒偺憢偐傜尒偊傞峠梩傕傎傏嶶偭偰偟傑偄丄恾彂娰慜偺暚悈偑偔偭偒傝偲尒搉偣傞傛偆偵側偭偨丅暚悈偺傑傢傝偺儀儞僠偵廤偆妛惗偨偪傕壗偐棊偪拝偄偨姶偠偑偡傞丅偟偭偲傝偲偟偨搤偺偼偠傑傝偱偁傞丅
丂偝偰丄偲偁傞帠忣偐傜怴偟偄僷僜僐儞傪攦偭偰丄僩儔僽儖偵憳嬾偟偨巹偱偁偭偨偑丄堦偮偄偄偙偲偵弌夛偭偰丄姶寖偟偨丅偲偄偆偺偼丄愄偐傜垽梡偟偰偄偨僕儍僗僩僔僗僥儉偺儚乕僾儘僜僼僩堦懢榊偺ver.9偑怴偟偄俷俽偱偁傞Windows XP忋偱傕巊偊傞偲偄偆偙偲偑傢偐偭偨偐傜偱偁傞丅
丂偛懚抦偺傛偆偵丄僷僜僐儞嬈奅丄僜僼僩僂僄傾乕嬈奅偱偼丄俷俽偑戙懼傢傝偡傞搙偵丄慜偺償傽乕僕儑儞偺惢昳偼巊偊側偔側傞偲偄偆偙偲偑偟偽偟偽偁傞丅偙偺偙偲偵傛偭偰丄徚旓幰偼斲墳側偔怴偟偄徚旓傪梋媀側偔偝傟丄嬈奅偼弫偆偙偲偵側偭偰偄傞丅偮傑傝丄偄偮傑偱傕巊偄懕偗傜傟傞惢昳傪採嫙偟丄怴偟偄俷俽偵傕懳墳偱偒傞僒億乕僩傪偡傞偙偲偼丄夛幮偺棙塿偲偄偆娤揰偐傜傒傞偲丄儅僀僫僗偺偙偲偵側傞丅
丂僕儍僗僩僔僗僥儉偺堦懢榊偼丄儅僀僋儘僜僼僩偺儚乕僪偵傎傏巗応傪惾姫偝傟丄尩偟偄忬嫷偵抲偐傟偰偄傞丅偙傟偼儚乕僪偑巊偄傗偡偄偲偄偆偙偲傛傝傕丄扤傕偑儚乕僪傪傕偭偰偄傞偐傜儚乕僪偠傖側偄偲晄曋偩偲偄偆偲偙傠偐傜偒偰偄傞丅
丂偝偰丄堦懢榊偼偙偺師偺償傽乕僕儑儞乮棃擭俀寧敪攧梊掕乯偱ver.13偵側傞丅偮傑傝丄巹偑巊梡偟偰偄傞ver.9偲偄偆偺偼4悽戙丄偄傗傑偩13偼弌偰偄側偄偐傜3.5悽戙慜偺惢昳偲偄偆偙偲偵側傞丅偩偐傜丄怴偟偄惢昳傪攧傞偨傔偵偼丄ver.9傪夁嫀偺傕偺偲偡傞偨傔偵丄Windows XP偵偼懳墳偟偰偄傑偣傫丄偲偡傟偽偄偄偺偱偁傞丅
丂偲偙傠偑丄僕儍僗僩僔僗僥儉偺儂乕儉儁乕僕偵偼丄ver.9傪Windows XP偱栤戣側偔巊偊傞傛偆偵偡傞偨傔偺儌僕儏乕儖乮廋惓偺僜僼僩偺傛偆側傕偺乯偑柍椏偱採嫙偝傟偰偄傞丅偩偐傜丄儐乕僓乕偼挿偄婜娫偵傢偨偭偰丄垽梡偟偨償傽乕僕儑儞傪巊偄懕偗傞偙偲偑偱偒傞丅
丂偙偆偟偨婇嬈偺庢傝慻傒偵弌夛偆偲丄巹偺傛偆側僴乕僩偱姶偠傞儐乕僓乕偼丄師傕僕儍僗僩僔僗僥儉偺惢昳傪峸擖偟傛偆偲峫偊傞丅嫄恖儅僀僋儘僜僼僩偲偺嫞憟偼尩偟偄偐傕偟傟側偄丅偟偐偟丄抧摴側庢傝慻傒傪尒偰偄傞恖乆偼偄傞丅戝偒偄偙偲丄椡偺嫮偄偙偲偵傕偺傪偄傢偣偰丄傗傝偨偄曻戣傗偭偰偄傞偲丄偦傟傕偪傖傫偲恖乆偼尒偰偄傞丅嫄戝偵尒偊偰傕丄怣傪幐偊偽丄姠夝偡傞偺偼偁偭偲偄偆娫偐傕偟傟側偄丅楌巎偼丄椻揙偵丄偦偟偰昁慠揑偵峴偒拝偔応強偵巹偨偪傪偄偞側偭偰偄偔丅
丂丂2002/11/29(Fri)丂亙書暊愨搢亜
丂倃俹僷僜僐儞偼俷俽傪嵞僀儞僗僩乕儖偟偰丄摨偠僜僼僩傪埲慜偲偼堘偆弴斣偱擖傟偰傒偨偲偙傠丄栤戣側偔摦偄偰偄傞丅弴斣傪曄偊偨偩偗偱偆傑偔偄偔側傫偰丄僴僀僥僋偺偼偢側偺偵壗偲傕儘乕僥僋側夝寛朄偱偁傞丅庼嬈傪峴偆忋偱傕丄帒椏傪攝晍偡傞弴斣偑寛掕揑偩偭偨傝偡傞偑丄偄偢偙偺悽奅傕弴斣偲偼戝愗側傕偺偐傕偟傟側偄丅偟偐偟丄偄偮傕偙傫側晽偵揔摉偵偛傑偐偟偰丄怺偔孈傝壓偘傛偆偲偟側偄偲偙傠偑巹偺偄偄壛尭偝偱偁傞丅
丂偝偰丄崱擔偺杮戣偵擖偭偰丄僛儈偵偮偄偰丅棃廡偺僛儈惗偺敪昞乽壎巘傊偺僀儞僞價儏乕乿傪撉傫偱偄偰丄徫偄偑偲傑傜側偄丅僀儞僞價儏傾乕偺妛惗偲愭惗偑儃働偲偮偭偙傒偲偄偆姶偠偱夛榖偑傔偪傖偔偪傖偍傕偟傠偄偺偱偁傞丅徫偄偼怱傪桙偟偰偔傟傞傕偺偱丄壗偲傕妝偟偄僀儞僞價儏乕傪偁傝偑偲偆両偲偄偆婥暘偱偁傞丅恖偵徫偄傪梌偊偰偔傟傞偺偼偲偰傕戝偒側嵥擻偱偁傝丄帓暔偱偁傞丅偄偮傕偼偳傫側巜摫傪偟側偗傟偽偄偗側偄偐偲恎峔偊側偑傜丄恎傪屌偔偟偰丄妛惗偺敪昞尨峞傪撉傫偱偄傞巹偺恎懱偼丄偙偺僛儈惗偺僀儞僞價儏乕偱堦婥偵傎偖偝傟偰偟傑偭偨丅傗偼傝妝偟傓偙偲偑壗帠偵偮偗偰傕尨揰偱偡偹丅傎傫偲偆偵偐側傢側偄丅
丂丂2002/11/28(Thu)丂亙倃俹亜
丂嶐擔偺僎僗僩島墘偼偲偰傕偄偄傕偺偵側傝傑偟偨丅妛惗偨偪偵丄偦偟偰巹偵丄帺暘傜偟偔惗偒傞偙偲偺戝愗偝傪嫵偊偰偄偨偩偒丄姶幱偺婥帩偪偱偄偭傁偄偱偡丅
丂偝偰丄恖偑惗偒傞偲偄偆偙偲傪椼傑偡儊僢僙乕僕傪傕傜偭偰儖儞儖儞偲婣偭偰丄傢偗偁偭偰怴挷偟偨巇帠梡僷僜僐儞偵僜僼僩傪僀儞僗僩乕儖偟偰偄偨偲偙傠丄撍慠丄乽梊婜偟側偄栤戣偑婲偙傝傑偟偨丅傆偵傖傜傜乿偲偄偆儊僢僙乕僕偑弌尰偟偨丅巹偼丄壗堦偮乽梊婜偟側偄乿傛偆側憖嶌偼偟偰偍傜偢丄偩偨摦嶌偑妋擣偝傟偰偄傞僜僼僩傪擖傟偨偩偗偱偁偭偨丅側偺偵丄傂偳偄偙偲偵偳偺僜僼僩傪棫偪忋偘偰傕乽梊婜偟側偄栤戣偑婲偙傝傑偟偨丅傆偵傖傜傜乿偲偄偆儊僢僙乕僕偑弌偰丄僷僜僐儞偑搥傝偮偄偰偟傑偆丅壗搙儕僙僢僩傪偐偗偰傕摨偠偱偁傞丅慡偔乽梊婜偟側偄乿帠懺偱偁傞丅
丂怴偟偄僷僜僐儞偵偼丄Microsoft Windows XP Professional偲偄偆俷俽偑搵嵹偝傟偰偄傞丅儅僀僋儘僜僼僩幮偑丄埨掕惈偺偁傞俷俽偲偟偰偟偒傝偵愰揱偟偰偄傞傕偺偱偁傞丅偟偐偟丄巹偵偲偭偰偼丄偙傟傑偱偺Windows95傗98偱偡傜宱尡偟偨偙偲偺側偄丄傂偳偄帠懺偩偭偨丅儅僀僋儘僜僼僩偵嬯忣傪偄偆偺傕柺搢偔偝偄偺偱丄嵞僼僅乕儅僢僩丄俷俽偺嵞僀儞僗僩乕儖傪偟偰偼偠傔偐傜傗傝捈偡偙偲偵偟偨丅儅僀僋儘僜僼僩傕偁傟偩偗悽偺晉傪堦恖愯傔偟偰偄傞偺偩偐傜丄傕偆偪偭偲傑偟側傕偺傪弌偟偰傎偟偄傕偺偩丅傕偟偐偟偨傜峀崘旓偵偟偐偍嬥傪巊偭偰偄側偄偺偱偼側偄偐偲媈擮偑傛偓傞丅偳偺僷僜僐儞嶨帍傪撉傫偱傕倃俹偼徧巀偝傟偰偄傑偡傕偺偹丅
丂嶐斢偐傜崱挬偵偐偗偰丄偨偭傉傝偲儅僀僋儘僜僼僩偵帪娫傪扗傢傟偨丅偦偟偰丄崱丄俇擭慜偺屆偄僷僜僐儞乮Windows95搵嵹/Pentium 133MHz乯偱暥復傪彂偄偰偄傞丅偙傟偱壗堦偮晄帺桼偼側偄丅怴偟偄傕偺偑偡偖傟偰偄傞偲偼尷傜側偄丅偟偐偟丄悽偺棳傟偵偼媡傜偊側偄丅怴偟偄僜僼僩傗僴乕僪偑怴偟偄俷俽偵偟偐懳墳偟側偔側傞偲屆偄俷俽偼捖晠側傕偺偲側偭偰偟傑偆丅偙偆偟偰偳傫偳傫屆偄傕偺偼偁偲偵抲偄偰偄偐傟傞丅偲偄偆傛傝傢偞傢偞怴偟偄傕偺傪屆偔偟偰偄偔偙偲偑崱偺幮夛偺帺屓塣摦偺傛偆偱傕偁傞丅
丂怴偟偄僽僢僔儏偑屆偄僽僢僔儏傛傝偄偄偺偐傢傞偄偺偐傢偐傜側偄丅怴偟偄儈僒僀儖偑屆偄儈僒僀儖傛傝偄偄偺偐傢傞偄偺偐傢偐傜側偄丅怴偟偄僷僜僐儞偵岦偐偆崱偺妛幰偨偪偑屆偄尨峞梡巻偵岦偐偭偨妛幰偨偪傛傝偄偄巇帠傪偟偰偄傞偺偐偳偆偐傢偐傜側偄丅偲丄僽僣僽僣尵偭偰偄傞壣偑偁傟偽丄屆偄妛幰偨偪偺傛偆偵巇帠偵岦偐偊偽偄偄偺偵丄偲傕偆堦偮偺帺暘偑偮傇傗偄偰偄傞丅
丂丂2002/11/27(Wed)丂亙埆柌嶰杮亜
丂壗偲偄偆偙偲偐丄埆柌傪嶰杮棫偰偱尒偰偟傑偭偨丅埆柌偼堦杮偱傕廫暘側偺偵丄傛傝偵傕傛偭偰暿偺僥乕儅偺埆柌傪嶰杮棫偰偱尒傞偲偼丒丒丒
丂偍偐偘偱挬婲偒偨傜丄偐偊偭偰旀傟偰偄偨丅偄傗丄彂偄偰偄傞偆偪偵巚偄弌偟偨丅嶰杮棫偰偱偼側偔丄巐杮棫偰偩偭偨偙偲傪丅僩儂儂儂儂丅栚偑妎傔偰偄傞偲偒偼堦杮棫偰偺庼嬈偡傜巐嬯敧嬯偟偰偄傞偲偄偆偺偵丄栭偵側傞偲壗偲僀儅僕僱乕僔儑儞朙偐側摢側偺偱偟傚偆丅
丂偙傟偐傜庼嬈丄僎僗僩偺曽偺偍榖偑暦偗傞偺偱丄偲偰傕妝偟傒偱偡丅偱偼丅
丂丂2002/11/26(Tue)丂亙崙夛尒妛亜
丂崱擔偼挬偐傜崙夛偲傗傜傪尒妛偟偰偒傑偟偨丅抧壓揝偺塱揷挰墂偐傜抧忋偵弌傞偲丄偦偙偼暿悽奅偱偡丅埲慜偵惵嶳捠傝偱恖庬偑堘偭偰偄偨偍榖傪偟傑偟偨偑丄塱揷挰傕恖庬偑堘偄傑偡丅惗廘偄擋偄偺偡傞乮僗儈儅僙儞乯攚峀巔偺抝惈偑憗懌偵曕偄偰偄傑偡丅崙夛媍帠摪偲媍堳夛娰偑暲傃棫偮娫偺摴傪丄僲乕僱僋僞僀偺巹偼丄偡偛偡偛偲曕偄偰偍傝傑偟偨丅
丂戞擇媍堳夛娰偲傗傜偵擖傝傑偡偲乮仏丂媍堳夛娰偲偼丄崙夛媍堳偺巇帠応強丄戝妛偺尋媶幒搹偺傛偆側傕偺偱偡丅媍堳偵側傞偲堦恖堦幒偑梌偊傜傟傑偡丅奺搣偺夛媍幒偺傛偆側晹壆傕偁傝傑偡丅撪晹偵偼丄攧揦丄媔拑揦丄怘摪丄偦偟偰壗偲俰俿俛傕偁偭偰丄偪傚偭偲偟偨抧壓奨偺傛偆偵側偭偰偄傑偡丅抧壓奨偲偄偆傛傝傕昦堾偺傛偆側姶偠偱傕偁傝傑偡偑丅乯懸崌幒偵偼僞僶僐偺墝偑傕偆傕偆偲偟偰偄傑偡丅帺摦斕攧婡偺娛僕儏乕僗偼側偤偐侾侽擭慜偺偍抣抜偺侾侽侽墌偱偟偨丅偪側傒偵丄媍堳夛娰偼嶰偮偁傝傑偟偰丄戞堦偲戞擇偑廜媍堾媍堳偺偨傔偺夛娰丄偦偟偰傕偆堦偮嶲媍堾媍堳夛娰偲偄偆傕偺偑偁傝傑偡丅戞擇媍堳夛娰偼嶰偮偺夛娰偺恀傫拞偵寶偭偰偄傑偡丅
丂崱夞偺崙夛尒妛偼丄傂傚傫側偙偲偐傜媍堳偝傫偺偮偰偱偺尒妛偱偟偨偺偱丄傎偲傫偳嬛嬫偼側偔丄偔傑側偔媍堳夛娰偲崙夛傪尒偰傑傢傞偙偲偑偱偒傑偟偨丅媍堳夛娰偺抧壓俀奒偐傜抧壓摴傪捠偟偰崙夛偵撍擖偟傑偟偨丅懡偔偺媍堳偑偙偺抧壓摴傪捠偭偰搊堾偟偰偄傞偦偆偱偡丅搊堾偲偄偆偐傜偵偼丄崟揾傝偺幵偱昞尯娭偵忔傝偮偗側偄偲奿岲偑偮偐側偄傕偺偱偡偐傜丄俿倁偺塮憸偱偼偦偆偄偆僀儊乕僕偑棳傟傑偡偑丄偙傟偼彮悢攈偩偦偆偱偡丅抧壓摴偺嬤摴傪捠偭偰棤岥偐傜峴偭偨傝棃偨傝偟偰偄傞偐傜惌帯壠偼棤偱僐僜僐僜傗傞偺偑忋庤偩偲偄偆埬撪偺旈彂偝傫偺榖偱偟偨丅
丂偝偰丄抧壓摴傪捠偭偰偄偒傑偡偲丄僶僢僕傪偮偗偨媍堳偝傫偨偪偲偡傟堘偄傑偡丅偦偆偱偡丅崱偼崙夛夛婜拞丅侾帪偐傜杮夛媍偱嵦寛偑峴傢傟傑偡偺偱丄傎偲傫偳偺媍堳偝傫偑偙偙偵廤傑偭偰偄傞偺偱偡丅傗偭傁傝惗偺媍堳偝傫偨偪偼敆椡偑偁傝傑偟偨丅側傫偲偄偭偰傕壗枩丄壗廫枩偺恖偨偪偵帺暘偺柤慜傪彂偄偰傕傜偭偰偄傞恖偨偪偱偡偐傜丄偦偆偦偆廮側恖偼偄傑偣傫丅恎嬤偵尒傑偡偲丄廋梾応傪偔偖偭偰偒偨偲偄偆晽奿偑昚偄傑偡丅偳傫側廋梾応偱偁傞偺偐偼掕偐偵偼抦傝傑偣傫偑丅旈彂偝傫偐傜偼丄媍堳傪尒偮偗偰丄巜偝偟偰屇傃幪偰偵偟偰憶偄偩傝偟側偄傛偆偵偲偄偆拲堄傪庴偗傑偟偨偑丄偦傫側恖偑偄傞偺偱偡偹丅幐楃側偙偲偱偡丅
丂崙夛偺撪晹偵擖傝傑偡偲丄媍堳愱梡偺僄儗儀乕僞乕偑偁傝傑偡丅偙偙偵偼堦斒恖偼忔傟傑偣傫丅偟偐偟丄椬偵摨偠巇條偺僄儗儀乕僞乕偑偁傝丄偦傟偵忔偭偰俀奒偵忋偑傝傑偡丅崙夛媍帠摪偼偛懚偠偺傛偆偵恀傫拞偵嶰妏壆崻偑偁偭偰嵍塃懳徧偺偮偔傝偵側偭偰偄傑偡丅恀傫拞偺壆崻偑嫽枴怺偄偲偙傠偱偡偑丄偙偙偼傎偲傫偳巊傢傟偰偍傜偢丄岦偐偭偰嵍偑廜媍堾丄塃偑嶲媍堾偲側偭偰偄傑偡丅廜媍堾偲嶲媍堾偼慡偔暿乆偺慻怐傜偟偔丄偙偙偱摥偔恖偨偪傕崙夛偵嬑傔偰偄傞傢偗偱偼側偔丄廜媍堾偵嬑傔偰偄傞偐丄嶲媍堾偵嬑傔偰偄傞偐丄偩偦偆偱偡丅尒妛傕崙夛尒妛偱偼側偔丄廜媍堾尒妛偐丄嶲媍堾尒妛偱偁偭偰丄巹偨偪偼廜媍堾媍堳偺徯夘偱偟偨偐傜廜媍堾尒妛偲偄偆偙偲偱偟偨丅偮傑傝恀傫拞偐傜塃懁偵偼懌傪摜傒擖傟傞偙偲偼偱偒側偄傢偗偱偡丅
丂嬃偔傋偒偙偲偵丄巹偨偪偼廜媍堾媍挿偺墳愙幒丄偦傟偐傜戞堦埾堳夛幒偵擖傞偙偲偑偱偒傑偟偨丅墳愙幒偱偼傢偢偐廫悢暘慜傑偱丄媍挿偲傾僼僈僯僗僞儞偐傜偺棃媞偺柺択偑峴傢傟偰偄偨偦偆偱偡丅媍挿惾偵嵗傞偙偲傕壜擻偱偟偨丅偮偄朰傟偰偄傑偟偨偗偳丄巹偨偪偺崙偼崙柉庡尃丄偮傑傝柉偺崙側偺偱偡偹丅偩偐傜丄崙夛媍帠摪傕恖乆偵傂傜偐傟偰偄傞傢偗偱偡丅傑偨戞堦埾堳夛幒偲偼丄偳側偨傕偛懚偠偺偼偢偺梊嶼埾堳夛側偳偺幙媈偑峴傢傟傞夛媍幒偱偡丅偙偙偱傕偳偺惾偵嵗傞偙偲傕偱偒傑偟偨丅巚偄偺傎偐丄嫹偄嬻娫偩偭偨偺偱嬃偒傑偟偨丅俿倁偼偝傑偞傑側傕偺傪恎嬤偵姶偠偝偣傞偲偲傕偵丄庤偺撏偐側偄傕偺丄墦偔棧傟偨傕偺偵姶偠偝偣傞岠壥傪傕偭偰偄傑偡偑丄幚嵺偵尒偰傒傑偡偲丄崙夛偱榑愴偟偰偄傞偲偙傠偭偰偙傫側偲偙傠偐丄傆乕傫偲姶偠偝偣偰偔傟丄偖偭偲惌帯偲帺暘偲偺嫍棧偑嬤偔側傞偐傜晄巚媍偱偡丅
丂偝偰丄堦偮擖傞偙偲偑偱偒側偐偭偨偺偼丄崙夛偺杮夛媍応偱偡乮偙偺傎偐偵傕揤峜偺媥懅幒側偳傕偁傞乯丅偙偙偵擖傞偨傔偵偼丄廜媍堾偺怑堳偵側傞偐丄撪憰丒揹婥偺岺帠壆偝傫偵側傞偐丄偦傟偲傕慖嫇偱摉慖偡傞偐丄偄偢傟偐偺曽朄偑昁梫偲偺偙偲偱偟偨丅尩廳側尞偑偐偐偭偰偄傑偡丅偟偐偟丄偲偒偳偒恖偑弌擖傝偡傞偲偒偵僠儔僠儔偲拞偑尒偊傑偟偰丄幚偼嫹偄偲偄偆偙偲偑傢偐傝傑偟偨丅俆侽侽恖傎偳偺恖傪廂梕偡傞偵偼偪傚偭偲嫹偔丄挿偄夛媍偼偍婥偺撆偲偄偆姶偠偱偡丅
丂偖傞偭偲夢偭偰丄偍怘帠偺帪娫偑傗偭偰偒傑偟偨偺偱丄崙夛怘摪偱枊偺撪曎摉傪怘傋傑偟偨丅儊僯儏乕偵偼偝傑偞傑側掕怘丄庻巌側偳傕偁傝丄偍枴傕傑偢傑偢寢峔側傕偺偱偟偨丅媍堳偝傫偵榖傪偆偐偑偆偲丄崙夛媍帠摪晅嬤偼僐儞價僯傕側偔丄巇帠偑栭愴偵擖傞偲戝曄偩偦偆偱偡丅堦斣嬤偄僐儞價僯偱墲暅俁侽暘偐偐傞偲偐丅婯惂娚榓丄撪廀奼戝偱崙夛媍帠摪慜偵僐儞價僯傪怴愝偟偰傕傜偄偨偄傕偺偱偡丅偒偭偲斏惙娫堘偄側偟偩偲巚偄傑偡丅偁偲梋択偱偡偑丄戝妛偱嫵庼夛偑墑傃偨偲偒偵偼丄偨偙從偒偺弌揦偑偁傟偽側偁偲巚偄傑偡丅傑偁丄偨偙從偒壆傗偍偱傫壆傑偱偁偭偨傜丄偄偮夛媍偑廔傢傞偐傢偐傝傑偣傫偺偱丄側偄傎偆偑柍擄側偺偐傕偟傟傑偣傫偑丅
丂偍暊偄偭傁偄偵側偭偨偲偙傠偱丄杮夛媍侾侽暘慜偺儀儖偑側傝傑偟偨丅偄傛偄傛杮夛媍偺朤挳偱偡丅僇儊儔丄強帩昳傪儘僢僇乕偵梐偗偰丄僄儗儀乕僞乕偱係奒偵忋偑傝傑偡丅朤挳寯偺拲堄帠崁偵偄偒側傝乽堎條側暈憰傪偟側偄偙偲乿偲偁傝傑偡丅乽堎條側暈憰乿偲偼側傫偧傗偲巚偄偮偮丄乽晄懱嵸側峴堊傪偟側偄偙偲乿偲偄偆偙偲偽偑懕偄偰栚偵擖傝傑偡丅崙夛偵傕堄枴晄柧側峑懃偑偁傝丄擔杮偺峑懃偲偼側偐側偐崻怺偄傕偺偱偁傞偙偲傪抦傝傑偟偨丅娗棟嫵堢壓偺拞妛峑擖妛幃偺傛偆側嬞挘姶傪傕偭偰丄朤挳惾偵擖傝傑偟偨丅
丂偪傚偆偳杮夛媍奐巒偺帪崗丄媍堳偝傫偨偪偼傎偲傫偳廤崌偟偰偄傑偡丅忋偐傜尒偰偄傑偡偑丄偍偍丄搚堜偨偐巕偝傫丄奀晹弐庽偝傫丄奀峕揷枩棦偝傫丄柸娧媍挿丄抦偭偨婄偑暲傫偱偄傑偡丅偪傚偭偲儈乕僴乕偵側偭偨婥暘偱偡丅媍堳偺惾弴偼姷廗偲偟偰丄堦斣慜偵侾擭惗媍堳丄偦偟偰摉慖夞悢丒擭楊偑庒偄弴偵嵗傝丄屻傠偵枩擭媍堳偲側偭偰偄傑偡丅傑傞偱拞妛峑偐丄崅峑偺惾弴偺傛偆偱偡丅
丂媍挿偺奐夛愰尵偺偁偲丄崅墌媨巰嫀偺栙摌偑偁傝丄懕偄偰儚儞僊儕朄埬偺嵦寛偑峴傢傟傑偟偨丅堦恖偺媍堳偝傫偑儚儞僊儕朄埬偺庯巪愢柧傪偟偰偄傞娫丄夛媍応偼巹岅偺恀偭惙傝偱偡丅傕偪傠傫丄懡偔偺媍堳偝傫偨偪偼媍寛傪偡傞偨傔偱偼側偔丄忣曬岎姺偺偨傔偵弌惾偟偰偄傞傢偗偱偡偐傜丄偙傟偼摉慠偺偙偲偐傕偟傟傑偣傫丅乮戝妛偺島媊偱傕丄妛惗偼忣曬岎姺偺偨傔偵弌惾偟偰偄傞偺偱丄巹岅傪偡傞偺偼偟偛偔摉慠偺偙偲偩丅偦偺斵丒斵彈傜偵偳偆榖傪暦偄偰傕傜偆偐偑戝妛嫵堳偺榬偺尒偣偳偙傠偩偲偄偆尒幆偁傞榖傪偟偰偔傟偨摨椈偑偄傑偟偨丅乯偮傑傝丄傎偐偺媍堳偝傫偵挳偐偣傞傛偆側墘愢偑偱偒傞媍堳偝傫偼戩敳偟偨椡検傪傕偭偰偄傞偲峫偊偰偄偄偱偟傚偆丅媍堳偝傫偨偪偵懳偟偰偼丄偁傑傝柍棟側偙偲傪偙偪傜傕梫媮偟傑偣傫偺偱丄偤傂帺暘偨偪偺巔傪屭傒側偑傜丄嫵堢偵偮偄偰偺朄埬傪怰媍偟偰偄偨偩偒偨偄偲愗偵婅偆偽偐傝偱偡丅
丂偝偰丄儚儞僊儕朄埬偺庯巪愢柧偑廔傢傞偲丄媍挿偑乽嵦寛傪峴偄傑偡丅堎媍偁傝傑偣傫偐丠乿偲敪尵丄乽堎媍側偟乿偲慡堳堦抳偱弖偔娫偵壜寛偝傟傑偟偨丅崱擔偺怰媍偼偙傟偩偗偲偄偆偙偲偱丄崙夛偼廔傢傝丅傢偢偐俆暘傎偳偺惌帯僔儑乕偱偟偨丅偱偒傟偽丄傕偆彮偟尒偰偄偨偐偭偨偺偱偡偑丅抦偭偰偄傞媍堳偝傫偨偪傪扵偡壣偡傜偁傝傑偣傫偱偟偨丅巆擮丅
丂嵞傃媍堳夛娰偵栠偭偰丄媍堳偝傫偺巇帠晹壆傪尒偣偰偄偨偩偄偰丄婣楬偵偮偒傑偟偨丅婣傝偵偼丄媍堳夛娰偺懸崌幒偼恖偱偁傆傟偐偊偭偰偄傑偡丅偳偆傕抧曽偐傜偺捖忣抍偺傛偆偱偡丅奜偵弌傞偲丄嬻婥偼偍偄偟偔丄崙夛媍帠摪偲嬧埱偺栘偑惵嬻偵塮偊偰偄傑偟偨丅偁傫側偙傕偭偨嬻婥偺拞偱巇帠傪偝傟偰偄傞媍堳偝傫偨偪傪彮偟尒捈偟傑偟偨丅偦偟偰丄捖忣丄捖忣偱棙塿桿摫偺惌帯壆傪堢偰傞偺傕丄崙柉偺暯榓偲埨慡傪庣傝丄岞惓側幮夛傪抸偔惌帯壠傪堢偰傞偺傕丄巹偨偪崙柉偺偁傝傛偆偩偲偄偆偙偲傪巚偄傑偟偨丅岾偄偵偟偰丄崱偺擔杮崙偼丄擔杮崙寷朄偵庣傜傟丄崙柉庡尃偑曐徹偝傟偰偄傑偡丅悽奅偵偼丄崙夛偑偁偭偰傕偦偙偵崙柉偑傾僋僙僗偱偒側偄崙偑偨偔偝傫偁傞偵偪偑偄偁傝傑偣傫丅崙夛偼丄巹偨偪偺傕偺丄偦偟偰岞嫟偺傕偺偩偲偄偆堄幆傪幚姶偱偒偨偙偲丄偙傟偑崱夞偺崙夛尒妛偺戝偒側廂妌偵側傝傑偟偨丅挿偄儗億乕僩傪廔傢傝傑偡丅
丂丂2002/11/25(Mon)丂亙柌尒怱抧亜
丂挬偐傜堦擔僶僞僶僞偟偰偄偰丄崱傛偆傗偔堦懅偮偗偨丅扅崱丄屵屻俈帪係俇暘丅廡枛偼丄嬤偔偺僗乕僷乕偵攦偄暔偵弌偐偗偰丄傆傜傆傜偲嬶崌偑埆偔側傝丄偦傟偐傜抐懕揑偵怮偰偄偨丅偆傑偄偲偙傠偵嬑楯姶幱偺擔偑偁偭偰丄偁偺廽擔偑側偗傟偽丄崱崰丄晽幾偱怮崬傫偱偄偨偵偪偑偄側偄丅崱擭偼晽幾偺朘傟傕憗偄傛偆偱偁傞丅
丂22擔偺柌偐傜惲傔偰傕傑偩柌尒怱抧偺巹偩偑丄奆偝傫傕晽幾側偳彚偝傟側偄傛偆偵丄偟偭偐傝偲塰梴偲媥梴傪偲傜傟傑偡傛偆偵丅偲偄偆傢偗偱丄崱擔偼偙偺曈偱丄傑偨柧擔両
丂丂2002/11/22(Fri)丂亙柌亜
丂偍偐偘偝傑偱丄崱擭傕柍帠偵嵨傪堦偮廳偹傞偙偲偑偱偒傑偟偨丅傑偨棃擭堦偮嵨傪廳偹傞偙偲傪栚昗偵惗偒偰偄偒偨偄偲巚偄傑偡丅
丂偝偰丄崱擔偺丄偪傚偆偳巹偑惗傑傟偨柧偗曽崰丄堦偮偺柌傪尒傑偟偨丅偦傟偼丄巹偑僀僗儔僄儖偺僥儖傾價僽戝妛傪朘傟偰偄傞柌偱偟偨丅傕偪傠傫丄巹偼偐偮偰僥儖傾價僽戝妛偵峴偭偨偙偲偼偁傝傑偣傫丅偦偟偰丄僥儖傾價僽戝妛偲偄偆戝妛偑幚嵼偡傞偐偳偆偐丄偦傟傕抦傝傑偣傫丅偟偐偟丄偦傟偼偨偟偐偵僥儖傾價僽戝妛偱偟偨丅
丂巹偼僣傾乕偵嶲壛偟偰偍傝丄偦偺僣傾乕偱偼尩廳側拲堄偑偁傝傑偟偨丅偦傟偼寛偟偰廤抍偐傜棧傟偰偼側傜側偄偲偄偆傕偺偱偟偨丅廤抍偐傜棧傟偰丄堦恖傏偭偪偵側偭偨搑抂偵丄僥儘儕僗僩偵慱傢傟丄嶦偝傟傞丅傑偝偵偦偙偼偦偆偄偆応強偱偟偨丅戝妛偺僉儍儞僷僗偼丄僐儞僋儕乕僩懪偪偭曻偟偺僌儗乕偵暍傢傟丄嶦敯偲偟偰偄傑偟偨丅偦偟偰丄帄傞偲偙傠偵墷暷宯偺恖乆偺忋敿恎偑偍偐傟偰偄傑偡丅僥儘儕僗僩偵嶦偝傟丄摲懱傪傑偭傉偨偮偵愗傜傟偰丄偦偙偵偝傜偟傕偺偵偝傟偰偄傞偺偱偡丅抝惈傕偄傟偽丄彈惈傕偄傑偡丅僝僢偲偡傞傛偆側岝宨偱偟偨丅
丂晐偄傕偺尒偨偝偱僣傾乕偵嶲壛偟偨巹偱偟偨偑丄偙傟偼偲傫偱傕側偄偲偙傠偵棃偨偲屻夨偟傑偟偨丅偙傟傑偱偺椃偱宱尡偟偨晐偝偲傑偭偨偔幙偺堘偆晐偝偑偦偙偵偼偁偭偨偺偱偡丅僥儘偵嫰偊側偑傜曢傜偡偲偄偆偙偲偼偙傫側偙偲偐偲湵慠偲偟傑偟偨丅偦偟偰丄埨慡抧懷偺墦偔偐傜僥儘偲愴憟偵偮偄偰岅傞帺暘偺擣幆偼丄摉帠幰偺怱偺嫰偊傪偡偔偄偲傞偙偲偑傑偭偨偔偱偒偰偄側偐偭偨偲巚偄傑偟偨丅
丂偁偪傜偙偪傜偵昚偆寣偲巰偺廘偄偵偙偺悽偺抧崠傪姶偠丄棫偪恠偔偟偰偄偨巹偼丄壗偲偄偆偙偲偐丄廤抍偐傜偼偖傟偰偟傑偄傑偟偨丅摲懱傪傑偭傉偨偮偵抐偪愗傜傟偨恖娫偨偪偺塣柦偑師偼巹偺塣柦偲側傞偺偱偡丅尵偄傛偆偺側偄晐傟偑巹偺側偐偐傜暒偒忋偑偭偰偒傑偟偨丅
丂傑偢偼寶暔偺拞偵擖傠偆偲丄奃怓偵偔偡傫偩寶暔偺拞偵恎傪塀偟傑偟偨丅偳偙偐傜揋偑廝偭偰偔傞偐傢偐傜側偄忬嫷偼丄昞尰偟傛偆傕側偔偒偮偄傕偺偱偟偨丅堦偮偺晹壆偺拞偵丄恖偑堦恖擖傞偙偲偑偱偒傞偖傜偄偺娵偄寠傪敪尒偟傑偟偨丅偙偙傪扵偝傟傟偽嶦偝傟傞偙偲偼傢偐偭偰偄傑偟偨偑丄傎偐偵塀傟傞偲偙傠傕側偐偭偨偺偱丄巹偼偦偺寠偺拞偵怺偔愽傒傑偟偨丅偦偟偰丄偟偽傜偔偡傞偲丄柧傞偄捠傝偵弌偰偄傑偟偨丅彆偐偭偨偺偱偡丅
丂偙傟偼巹偺柌偱偡丅柌暘愅傪庴偗傟偽巹偺怱偺栤戣偲偟偰偙偺柌偼埖傢傟傞偐傕偟傟傑偣傫丅偟偐偟丄挬婲偒偰丄怴暦偵栚傪捠偟偨偲偙傠丄僄儖僒儗儉偱帺敋僥儘偑婲偙偭偰偄傞偱偼偁傝傑偣傫偐丅彮彈傜傕傆偔傔偰侾侽柤偺巰幰偑弌偰偄傞偲偁傝傑偡丅偦偟偰丄僔儍儘儞庱憡偼丄曬暅偩偲嫨傫偱偄傑偡丅傕偪傠傫丄帺敋僥儘帺懱傕僀僗儔僄儖孯偺怤峌偵懳偡傞曬暅偲偟偰峴傢傟偰偄傑偡丅峳傟栰傪僀儊乕僕偡傞巹偨偪偺報徾偲偼堘偭偰丄僈僓抧嬫偲偄偭偨庡偵僷儗僗僠僫恖偑廧傫偱偄傞抧堟偼丄恖岥偺枾廤抧堟偱偡丅偝傜偵怽偟傑偡偲丄儐僟儎嫵乮僉儕僗僩嫵乯懳僀僗儔儉嫵丄儐僟儎恖偲傾儔僽恖偲偄偭偨懳棫恾幃偼壗偲傕搈愶乮偢偝傫乯側傕偺偱偡丅僀僗儔僄儖偵廧傫偩宱尡偺偁傞曽偵偍恞偹偟偨偲偙傠丄僀僗儔僄儖偺嫵夛偵偼傾儔僽恖偺僋儕僗僠儍儞偑偨偔偝傫偄傞偦偆偱偡丅峳偭傐偄懳棫恾幃偺拞偱丄偦偺傛偆側恖偨偪偼偳傫側偵偐怱傪捝傔側偑傜丄傑偨尰幚偵傕婔廳傕偺嵎暿偲攔彍偺拞偱曢傜偟偰偍傜傟傞偙偲偱偟傚偆丅
丂巹偼嫢抏偵搢傟偨僀僗儔僄儖偺儔價儞庱憡傪垽偟傑偡丅儔價儞偼孯恖偱偁傝側偑傜丄朶椡偱栤戣傪夝寛偟傛偆偲偡傞偙偲偺嬸偐偝偲埆弞娐偵婥偯偒丄擲傝嫮偄懳榖傪傕偭偰僷儗僗僠僫偵暯榓傪抸偙偆偲恠椡偟傑偡丅偦偺寣偺燌傓傛偆側搘椡偼丄僀僗儔僄儖偺僫僔儑僫儕僗僩偵傛偭偰抐偪愗傜傟傑偟偨偑丄偦偺巚偄偼偨偟偐側悈柆傪曐偭偰偄傑偡丅悽奅偼丄僥儘儕僗僩偲曬暅幰偱峔惉偝傟偰偄傞傢偗偱偼側偄丅偦傫側扨弮側傕偺偱偼側偄丅帺敋僥儘偵嵟垽偺巕偳傕傪扗傢傟側偑傜傕僔儍儘儞偺曬暅偵斀懳偟偰偄傞僀僗儔僄儖偺恖乆丄偦偆偟偨恖偨偪偺巚偄偵摢傪悅傟側偑傜丄怱傪婑偣偨偄偲巚偭偰偄傑偡丅
丂丂2002/11/21(Thu)丂亙愻擼亜
丂媣偟傇傝偵帪帠栤戣偵偮偄偰丅杒挬慛偺漟抳栤戣偱乽愻擼乿偲偄偆偙偲偽偑巊傢傟偰偄傞丅漟抳偝傟偨恖乆偑丄杒挬慛偲偄偆崙壠偺嫵媊丒壙抣娤傪嶞傝崬傑傟偨偲偄偆偙偲傪巜偡偺偱偁傠偆丅偨偟偐偵堦偮偺壙抣娤丄偟偐傕偦傟偑撈慞揑偱偁傝丄懠幰偺懚嵼傪屭傒側偄傕偺偱偁傟偽丄偦偙偐傜夝偒曻偨傟傞偙偲偼戝愗側偙偲偱偁傞偲巚偆丅偟偐偟側偑傜丄乽愻擼乿偲偄偆偙偲偽偑岅傜傟傞偲偒偺暥柆偱婥偵側傞偙偲偑偁傞丅偲偄偆偺偼丄乽愻擼乿偲偄偆偙偲偽偑巊傢傟傞偲偒偺慜採偵偁傞偺偼丄帺暘偼惓偟偔偰丄憡庤偑岆偭偰偄傞偲偄偆悽奅擣幆偺傛偆偵巚傢傟傞偐傜偱偁傞丅
丂巹偨偪偺幮夛傕偄偔偮傕偺栤戣傪書偊偰偄傞丅椺偊偽丄撿杒栤戣丄娐嫬栤戣丄愴憟偲偄偆栤戣丅崱丄巹偨偪偑埨壙側巻傪戝検偵巊梡偡傞偙偲偑奜崙偺怷椦傪攋夡偟偰偄傞偙偲偵偮側偑偭偨傝丄僼傽儈儗僗偱埨壙偱偍偄偟偄僄價傪怘傋傞偙偲偑奜崙偺恖乆偺惗妶婎斦傪怚傫偱偄偨傝丄偝傑偞傑側栤戣偑偦偙偵偼偁傞丅偨偟偐偵堦偮偺壙抣娤偩偗偵暍傢傟傞偺偱偼側偔丄堎側傞峫偊傪昞柧偡傞帺桼偑朄偵傛偭偰庣傜傟偰偄傞揰偵偍偄偰丄巹偨偪偺幮夛偼昡壙偝傟傞丅偟偐偟丄巹偨偪偑擔乆愙偟偰偄傞忣曬偼丄堎側傞峫偊傪堢傓揰偵偍偄偰傎傫偲偆偵曃傝偑側偄偲尵偊傞偩傠偆偐丅
丂懠幰傪旕擄偡傞偲偒偵丄偪傚偭偲偽偐傝偱傕帺暘偵傕偦傫側偲偙傠偑側偄偺偐偳偆偐晄埨偵側傞丄偦偆偄偆怲傑偟偝偑寢峔戝愗側偺偱偼側偄偐偲巚偆偺偱偁傞丅
丂丂2002/11/20(Wed)丂亙50000姶幱亜
丂50000僇僂儞僩丒僎僢僩偺儊乕儖偑僛儈惗偐傜傗偭偰偒傑偟偨丅垽梡偺昳傪乽慹昳乿偲偟偰僾儗僛儞僩偡傞偙偲偵偟傑偟偨丅惿偟偔傕偼偢傟偨曽丄怽偟栿偁傝傑偣傫丅偝偰丄峠梩偑慛傗偐側崱挬偱偟偨丅崱廐偼媫寖偵婥壏偑壓偑偭偨偨傔丄嶳娫晹偺傛偆側傒偛偲側峠梩偑晲憼栰偱傕傒傜傟傑偡丅搶嫗宱嵪戝妛偺撿幬柺丒搶幬柺偺栘乆偼偲偰傕傒偛偲偱偡丅椢偵曪傑傟偨僉儍儞僷僗偼丄婥偯偐傟偵偔偄偗傟偳傕丄妛傃傪堢傓戝偒側嵿嶻偩偲巚偄傑偡丅偱偼
丂丂2002/11/20(Wed)丂亙娫傕側偔50000両亜
丂1997擭偐傜5擭偁傑傝懕偗偰偒偨乬Internet 偨傑偺偝傫傐傒偪乭偩偑丄娫傕側偔50000僇僂儞僩傪寎偊傛偆偲偟偰偄傞丅抶乆偲偟偨曕傒偩偭偨偑丄巹偺愘偄暥復傪撉傫偱偄偨偩偒丄偲偒偵偼壏偐偔丄偲偒偵偼尩偟偔椼傑偟偺偙偲偽傪偐偗偰壓偝偭偨撉幰偺曽乆偵偼丄姶幱偺巚偄偱偄偭傁偄偱偁傞丅偙傟傑偱乬Internet 偨傑偺偝傫傐傒偪乭偱捲偭偰偒偨偺偼丄幐傢傟偨擇廫戙傪庢傝栠偡偨傔偺嶰廫戙慜敿偺巹偺埆偁偑偒偱偁偭偨偑丄偙傟偐傜偼嶰廫戙慜敿偺埆偁偑偒傪傑偲傑偭偨偐偨偪偵憂傝忋偘偰偄偔偙偲偑巹偺巇帠偵側傞偲巚偆丅50000僇僂儞僩傪摜傫偩曽偵偼丄婰擮偺慹昳傪恑掓偟偨偄偺偱丄偤傂偲傕偛楢棈壓偝偄丅帺暘偱抧棆傪摜傑側偄傛偆偵丄偟偽傜偔偼傾僋僙僗傪峊偊偰偍偒傑偡丅嶰廫戙慜敿傕偁偲擇擔丅偱偼丅
丂丂2002/11/19(Tue)丂亙嬧埱偺婸偒亜
丂搶嫗宱嵪戝妛偵偼丄嬧埱偺栘偑偁傞丅偙偺婫愡丄嬧埱偼僉儔僉儔偲墿嬥怓偵婸偒丄偁傑傝偵傕尒帠偱偁傞丅廐偺梲偺岝偵偼偠偗丄晽偵備傟傞嬧埱偺巔偼丄侾擭娫偺僋儔僀儅僢僋僗偱傕偁傞丅偟偐偟丄偙偺嬧埱傕搤偺娫偼僴僎僴僎偱丄壞傕傂偨偡傜栁偭偰偄傞偩偗丅僷僢偲偟側偄挿偄帪娫傪偨傔偰丄偙偺婫愡偵偙傟偱傕偐偲偽偐傝偵婸偔偺偱偁傞丅
丂怱偵撍偒巋偝傞傛偆側嬧埱偺婸偒傪巚偄婲偙偟側偑傜丄扺乆偲偟偨擔忢偺執戝偝偵夵傔偰婥偯偐偝傟偰偄傞丅挿偄恖椶偺楌巎傪捠偟偰丄恖偺恖惗傕傑偨戝偄側傞擔忢偵曪傑傟偨傕偺偱偁偭偨偩傠偆丅杴乆偲偟偨擔忢偑側偗傟偽丄傎傫傕偺偺婸偒偼惗傑傟摼側偄傕偺偱偁傞丅
丂丂2002/11/15(Fri)丂亙戝恖偺攚拞亜
丂巕偳傕偼戝恖偺攚拞傪尒偰堢偮偲偼丄傛偔尵偄摉偰偨偙偲偽偱偁傞丅僥儗價偱儚僀僪僔儑乕偵揃晅偗偵側偭偰偄傞戝恖偑丄巕偳傕偵乽曌嫮偟側偝偄乿偲偄偭偰傕側偐側偐岠偒栚偼側偄偩傠偆丅尵偭偰偄傞偙偲傛傝傗偭偰偄傞偙偲傪尒敳偔丄偙傟偑巕偳傕偱偁傞丅
丂偝偰丄帪帠捠怣偺僯儏乕僗偵傛傞偲丄巹岅傪拲堄偝傟偨崙夛媍堳偑媡僊儗偟丄拲堄偟偨媍堳偵墸傝偐偐傠偆偲偟偨偲偄偆丅埲壓偵偙偺僯儏乕僗傪堷梡偟傛偆丅
丂乽廜堾崙搚岎捠丒朄柋埾楢崌怰嵏夛偱侾俆擔丄巹岅傪拲堄偝傟偨帺柉搣媍堳偑媡忋丄拲堄偟偨柉庡搣媍堳偵媗傔婑傝丄棎摤悺慜傑偱偄偔憶偓偑偁偭偨丅暿偺帺柉搣媍堳偑巭傔偵擖傝帠側偒傪摼偨傕偺偺丄柉庡搣偺嵅摗宧晇崙懳埾堳挿偼摨擔丄拞愳廏捈帺柉搣崙懳埾堳挿偵懳偟丄岥摢偱峈媍偟偨丅
丂娭學幰偵傛傞偲丄幙栤拞偺壛摗岞堦巵乮柉庡乯偑丄巹岅傪偟偰偄偨媖峃懢榊巵乮帺柉乯偵拲堄丅偙傟偵暊傪棫偰偨媖巵偑丄幙栤廔椆屻丄暿幒偵堏偭偨壛摗巵偵乽榖偟偰偄偨偺偼偍傟偩偗偠傖側偄乿偲媗傔婑偭偨丅
丂峈媍傪庴偗偨帺柉搣懁偼丄廡柧偗偵拞愳巵偑媖巵偐傜帠忣傪挳偄偨忋偱懳墳傪専摙偡傞曽恓丅媖巵偼婰幰抍偺幙栤偵乽壗傕側偄乿偲傇偤傫偲偟偨昞忣偱摎偊偨偑丄乬媡僊儗乭偝傟偨壛摗巵偼乽暊偺拵偑帯傑傜側偄乿偲丄媖巵偺幱嵾傪媮傔偰偄傞丅乿
丂崙柉偺戙昞偱偁傞崙夛媍堳偱偁傞丅偨偩偨偩忣偗側偄偲偄偆偟偐側偄丅偦偟偰丄嵟崅偵忣偗側偄偺偼乽榖偟偰偄偨偺偼偍傟偩偗偠傖側偄乿偲偄偆僙儕僼偱偁傞丅乽丒丒丒僆儗偩偗偠傖側偄乿乽丒丒丒側傫偱僆儗偩偗乿丅偙傟偼懡偔偺嫵巘偨偪偑巕偳傕偨偪偐傜敪偣傜傟傞偙偲偽偺拞偱嵟傕偑偭偐傝偡傞僙儕僼偺堦偮偱偁傞丅庡懱偲偟偰愑擟傪堷偒庴偗傞偙偲偑偱偒側偄恖娫偺暔尵偄偩偐傜偱偁傞丅
丂巹偼嫵堢偺壽戣偼丄悽奅偵岦偒崌偄丄懠幰偵岦偒崌偄丄帺暘偵岦偒崌偄丄庡懱偲偟偰愑擟傪堷偒庴偗傞恖娫偵堢偮偙偲偱偼側偄偐偲峫偊偰偄傞丅乽偍傟偩偗偠傖側偄乿偲偄偆惌帯壠偨偪偑丄恖椶偺抦揑嵿嶻偺忋偵惉棫偟偰偄傞乽嫵堢婎杮朄乿傪夵惓偡傞偵抣偡傞偺偐偳偆偐丄婄傪愻偭偰丄嬀傪尒偰丄峫偊捈偟偰傎偟偄丅
丂偟偽傜偔慜丄島媊拞偵擇搙傕巹岅傪拲堄偡傞婡夛偑偁偭偨丅拲堄偝傟偨妛惗偼乽崱搙偐傜懺搙傪夵傔傑偡丅曄傢偭偨帺暘傪尒偰偄偰壓偝偄丅乿偲儗億乕僩偵彂偄偰偒偨丅偦偟偰丄偦傟偐傜堦搙傕巹岅傪偟偰偄側偄丅戝恖偺攚拞傪尒側偑傜惗偒偰偄傞庒幰偨偪偩偑丄斵傜偺傎偆偑偢偭偲戝恖偺傛偆偩丅
丂偪側傒偵丄巹岅傪拲堄偟偨壛摗岞堦偝傫偼巹偺慖嫇嬫偺侾擭惗崙夛媍堳偱丄棫攈側曽偱偁傞丅枅廡枅挬丄墂慜偵棫偪丄恖乆偵帺暘偺偙偲偽偱岅傝偐偗丄埑搢揑偵慻怐椡偱傑偝傞懳棫岓曗傪偺傝偙偊偰丄摉慖偟偨丅傑偝偐慻怐傪傕偨側偄壛摗偝傫偑摉慖偡傞偲偼巚偭偰偄側偐偭偨偺偱丄傗偭傁傝恖乆偼尒偰偄側偄傛偆偱尒偰偄傞傕偺偩偲姶怱偟偨傕偺偩偭偨丅乬巹岅乭傪拲堄偟偨壛摗偝傫傕傑偨堦恖偺戝恖偱偁傞丅
丂丂2002/11/14(Thu)丂亙宱尡亜
丂嶐擔丄惗搆巜摫榑偺島媊偱偼丄僎僗僩島巘偲偟偰怴嵗杒崅峑偺嬥巕彠愭惗偵棃偰偄偨偩偄偨丅嫵幒偼偄偮傕偼婄傪尒偣側偄妛惗偨偪傕傗偭偰偒偰丄偁傆傟傫偽偐傝偱偁傝丄姦偔側傝偮偮偁傞偙偺婫愡偵傕偐偐傢傜偢抔朳偑偄傜側偄傎偳擬婥偑偨偩傛偭偰偄偨丅偦偟偰丄嬥巕愭惗偺掕帪惂崅峑偐傜尰嵼偺晪擟峑偵帄傞侾俉擭娫偺嫵怑惗妶偺曕傒偵挳偒擖偭偰偄偨丅
丂妛惗偨偪偺儗億乕僩傪撉傓偲丄斵丒斵彈傜偑丄傢偢偐侾夞俋侽暘偺弌夛偄偺拞偱丄堦惗寽柦偵嬥巕愭惗偲偄偆懚嵼傪撉傒偲偭偰偄傞偙偲偑揱傢偭偰偔傞丅偦偟偰丄堎岥摨壒偵婰偟偰偄傞偺偑丄乽宱尡乿偲偄偆傕偺偺廳傒偵偮偄偰偱偁傞丅嬥巕愭惗偼丄侾俉擭娫丄惗搆偨偪偲恀偭惓柺偐傜岦偒崌偄丄惗搆偺堦偮傂偲偮偺偙偲偽丄媈栤傪庴偗偲傔丄偦傟偵墳摎偡傋偔慡椡傪恠偔偟偰偒偨愭惗偱偁傞丅忢幆偵傛傝偐偐傞偙偲傪嬌椡旔偗丄惗搆偨偪偲偺娫偱擔乆惗傑傟傞乽弌棃帠乿偦偟偰乽宱尡乿偐傜帺暘偺乽偙偲偽乿傪棫偪忋偘偰偙傜傟偰偄傞丅偟偨偑偭偰丄偦偺乽宱尡乿偵偼偨偟偐側廳傒偑偁傞丅妛惗偨偪偼偙偺廳傒傪偟偭偐傝偲庴偗偲傔偰偄傞傛偆偱偁偭偨丅
丂庒幰偨偪偑戝恖偺榖傪暦偐側偔側偭偨偲尵傢傟偰媣偟偄偑丄堦曽偱斵丒斵彈傜偼栆楏偵戝恖偺榖傪媮傔偰偄傞偲丄巹偼姶偠偰偄傞丅斵丒斵彈傜偑墋偆偺偼丄戝恖偺乽愢嫵乿乽柦椷乿偺尵岅偱偁傝丄戝恖偺乽宱尡乿偺尵岅偵偼妷朷偟偰偄傞偺偱偁傞丅乽宱尡乿偺尵岅偑岅傜傟偰偄傞偲偒丄偦偙偵偨偳偨偳偟偝偑偁偭偰傕丄斵丒斵彈傜偼師偺偙偲偽傪懸偭偰偄傞丅側偤側傜偽丄尵梩偲尵梩偺娫乮傑乯偵傕丄乽宱尡乿偑燌傒弌偟偰偄傞偐傜偱偁傞丅娫偑傕偨側偄偲偄偆姶妎偺枲墑偼丄僾儘僌儔儉偝傟偨尵岅偵擔乆怤偝傟偰偄傞備偊偺帠懺偱偁傝丄乽宱尡乿偺尵岅偵偍偄偰偼乽娫乿偙偦偑嵟傕梇曎偱偁傝丄娫偑傕偨側偄偲偄偆姶妎偑惗傑傟傛偆偑側偄偺偱偁傞丅
丂擔杮幮夛偵偼恀偺堄枴偱偺乽宱尡乿偑側偄偲尵偭偨偺偼丄揘妛幰偺怷桳惓偩偭偨丅乽懱尡乿傪偳偙傑偱慿偭偰傕乽娭學乿傑偱偱廔傢偭偰偟傑偆偲丄怷桳惓偼亀惗偒傞偙偲偲峫偊傞偙偲亁偺拞偱弎傋偰偄傞丅乽懱尡乿傪怺偄帺屓撪懳榖偵傛偭偰欚殣偡傞偙偲偵傛偭偰惗傑傟傞乽宱尡乿丅乽宱尡乿偺偙偲偽傪戝恖偨偪偑傕偰傞偐偳偆偐偑丄乽嫵堢乿偲偄偆娭學惈偑惉傝棫偮偐偳偆偐偺尞偱偁傠偆丅
丂丂2002/11/13(Wed)丂亙僆僼傿僗丒傾儚乕亜
丂杮擭搙偐傜搶嫗宱嵪戝妛偱偼丄僆僼傿僗丒傾儚乕偲偄偆傕偺偑惓幃偵巒傑偭偨丅僆僼傿僗丒傾儚乕偲偼丄妛惗偨偪偺棜廋摍偺憡択偵墳偠傞偨傔偵丄廡偵堦僐儅尋媶幒偱偺屄恖柺択傪峴偆帪娫偱偁傞丅偲偙傠偑僆僼傿僗丒傾儚乕傪奐巒偟偰偐傜丄偙偺帪娫偵妛惗偨偪偑偝偭傁傝棃側偔側偭偨丅懠偺帪娫偵偼丄妛惗偑偟偽偟偽傗偭偰偔傞偺偩偑丄僆僼傿僗丒傾儚乕偵偼棃側偄偺偱偁傞丅偁傞偄偼僆僼傿僗丒傾儚乕偼丄傔偢傜偟偔嫵堳偑尋媶偟偰偄傞帪娫偱偁偭偰丄偙偺帪娫偵偼棃偰偼偄偗側偄偲姩堘偄偟偰偄傞偺偱偼側偄偐偲丄偄傇偐偟偔巚偭偨丅偦偙偱丄偙偺傢偗偼壗偩傠偆偐丠偲乽傢偐傜側偄偙偲偼妛惗偵暦偔乿偲偄偆奿尵乮丠乯捠傝偵丄懠偺帪娫偵傗偭偰偒偨堦恖偺妛惗偵乽偳偆偟偰僆僼傿僗丒傾儚乕偵棃側偄偺丠乿偲恞偹偰傒偨丅
丂偡傞偲丄斵偼乽偊偭丄僆僼傿僗丒傾儚乕偵棃偰偄偄傫偱偡偐丠乿偲嬃偔丅偙偪傜傕嬃偄偰乽棃偰偄偄偐傜丄僆僼傿僗丒傾儚乕偩傠偆乿偲摎偊傞偲丄斵偼乽僆僼傿僗丒傾儚乕偵偼恖偑偨偔偝傫棃偰偄偰丄夛偭偰傕傜偊側偄偲巚偭偰偄偨乿偲尵偆丅側傫偲偄偆棤偺棤傪撉傫偩傛偆側峴摦偺僷僞乕儞丅偨偟偐偵傗傗偙偟偄悽偺拞偩偗偳丄戝妛偖傜偄僔儞僾儖偵傗傝偨偄傕偺偩丅偨偩偄傑丄僆僼傿僗丒傾儚乕偺帪娫丅尋媶幒偵偼惷庘偑偨偩傛偭偰偄傞丅
丂丂2002/11/11(Mon)丂亙榁偄亜
丂搚梛擔丄戝妛偺夘岇摍懱尡偺帠慜巜摫偱妛惗偨偪偲偲傕偵摿暿梴岇榁恖儂乕儉偺僗僞僢僼偺曽偺榖傪挳偄偨丅尰応偺榖偼嬶懱惈偵晉傒丄偐偮廳傒偑偁偭偨丅榖偺拞偱丄尰嵼丄80戙偐傜90戙偺恖偨偪偑巕堢偰偵暠摤偟偨傝丄幮夛偱偄偨帪戙偼偳傫側帪戙偩偭偨偐憐婲偟偰傒傛偆偲偄偆傕偺偑偁偭偨丅揹幵偺僉僢僾傕憢岥偱惡傪弌偟偰峸擖偟丄傕偪傠傫僷僜僐儞傗実懷偼側偐偭偨帪戙偱偁傞丅帪戙偺寖棳偲丄偦偺拞偱榁偄傪寎偊傞偙偲偺戝曄偝偵夵傔偰婥偯偐偝傟偨丅崱偺僐儞價僯乮曋棙側乯幮夛偼丄偝傑偞傑側惗妶偺抦宐傪惗偐偡応偺彮側偄幮夛偱偁傞丅偍擭婑傝偑偦偺椡傪敪婗偡傞偙偲偑擄偟偄幮夛偱偁傞丅
丂偍榖傪偟偰偄偨偩偄偨曽偼妛惗偨偪偵乽奆偝傫偑榁擭婜傪寎偊傞60擭屻偺幮夛傪憐憸偟偰偛傜傫側偝偄丅偦偺崰偵偼恖椶偼晛捠偵寧偵峴偭偰偄傞偐傕偟傟傑偣傫丅寧偵峴偔僉僢僾傪偳偆傗偭偰攦偆偺偐丄傑偛偮偄偰偄傞偐傕乿偲偄偆榖傪偝傟偨丅巹傕傑偨60擭屻偺幮夛傪憐憸偟偨丅偟偐偟丄恖椶偑寧椃峴傪偡傞幮夛偼憐憸偱偒側偐偭偨丅峳傟壥偰偨幮夛偺拞偱帺暘偨偪偺椡偱惗偒傞尩偟偝傪崪恎偵偟傒偨庒幰偨偪偑丄惗妶偺抦宐傕傕偨偢丄偨偩搑曽偵偔傟傞榁恖偨偪偵堦曀傕偣偢偵丄栙乆偲搚偵孡傪擖傟偰偄傞丄偦偆偄偆僀儊乕僕偑晜偐傫偱偒偨丅偝偰丄60擭屻偺悽奅偼偄偐偵丅
丂丂2002/11/8(Fri)丂亙僾儗僛儞僩亜
丂抋惗擔偺僾儗僛儞僩偵壗偑傎偟偄偐偲恞偹傜傟丄峫偊偰傒傞偑丄傎偟偄傕偺偼壗堦偮摢偵晜偐傫偱偙側偄丅傎偟偄偲偄偊偽丄乽柧濔側摢擼偲孅嫮側恎懱偲姲梕側怱乿偱偁傞偑丄偄偢傟傕僾儗僛儞僩偟偰傕傜偊傞傛偆側戙暔偱偼側偄丅昁梫側傕偺偼僾儗僛儞僩傪懸偨偢偵攦偭偰偄傞偟丄傎偟偄傕偺偲尵傢傟偰傕尒偮偐傜側偄偺偱偁傞丅
丂偝偰丄乽偙偺崙偵偼壗偱傕偁傞丅乧偩偑丄婓朷偩偗偑側偄丅乿偲偄偆偙偲偽偼丄懞忋棿偺亀婓朷偺崙偺僄僋僜僟僗亁偺拞偺堦愡偱偁傞丅偍偦傜偔乽壗偱傕偁傞乿偐傜偙偦乽婓朷乿偑側偄偵偪偑偄側偄丅恖偼寚偗偰偄傞偐傜偙偦丄偦偺寚偗偨晹暘傪夞暅偡傞偙偲傪妷朷偟丄帺暘傪搎偗偰偨偨偐偆丅傕偟乽壗偱傕偁傞乿側傜偽丄帺暘傪搎偗傞偙偲偼僶僇僶僇偟偄偙偲偵側傞丅偱傕丄彮偟峫偊偰傒傛偆丅傎傫偲偆偵壗偱傕偁傞偺偐丅巕偳傕偨偪偑惗偒惗偒偲妛傋傞妛峑偼偁傞偺偐丄巕偳傕偨偪偑媠懸傪庴偗偢寬傗偐偵堢偰傞壠掚偼偁傞偺偐丄巗柉偺巚偄偑惌嶔偲偟偰幚尰偝傟傞傛偆側惌帯偼偁傞偺偐丄恀柺栚偵偑傫偽偭偰偄傞恖偑曬傢傟傞傛偆側巇慻傒偼偁傞偺偐丄偪傚偭偲巚偄偮偔偩偗偁偘偰傕丄乽寚偗偰偄傞乿偱偁傠偆傕偺偼偨偔偝傫尒弌偣傞丅偦偆峫偊偰傒傞偲丄乽壗偱傕偁傞乿偲巚偭偰偄傞恖偼丄乽抦揑憐憸椡偑側偄乿偲偄偆偙偲偵側傞丅
丂抋惗擔偺僾儗僛儞僩傪巚偄偮偐側偄偺傕丄巹偺乽抦揑憐憸椡乿偺寚擛偩傠偆丅偍偦傜偔廃傝偺恖偨偪偐傜尒傟偽丄乽愭惗側傫偩偐傜丄傕偭偲僷儕僢偲偟偨暈傪拝傟偽偄偄偺偵乿偲偐丄乽攋傟偰偄傞孋壓傒偭偲傕側偄偐傜丄偪傖傫偲偟偨孋壓攦偊偽乿偲偐丄巹偵乽寚偗偰偄傞乿偱偁傠偆傕偺偼偨偔偝傫尒弌偣傞偵偪偑偄側偄丅
丂乽寚偗偰偄傞乿傕偺偙偦丄乽婓朷乿偱偁傞偲偄偆怺墦側恀棟傪敪尒偟偨偲偙傠偱丄抋惗擔偺僾儗僛儞僩偺榖偵栠傞偙偲偵偟傛偆丅崱夞偺抋惗擔偺僾儗僛儞僩偵偼丄乽偔偮壓乿傪攦偭偰傕傜偆偙偲偵偟傛偆丅乽偔偮壓乿傪傇傜偝偘偰偍偗偽丄崱搙偼僒儞僞僋儘乕僗偑乽柧濔側摢擼偲孅嫮側恎懱偲姲梕側怱乿偺僾儗僛儞僩傪擖傟偰偔傟傞偐傕偟傟側偄偟偹丅偦傫側偙偲偼側偄偐丅
丂丂2002/11/7(Thu)丂亙怓偯偔亜
丂傎傏堦栭偵偟偰尋媶幒偺憢偐傜尒偊傞栘偑怓偯偄偰偄傞丅11寧偵擖偭偰椻偊崬傒偺尩偟偄擔偑懕偄偨偐傜偩傠偆丅妛墍嵳偑廔傢傝丄偁偲偼搤偵岦偗偰扺乆偲偟偨擔乆偑懕偔丅扺乆偲偟側偑傜恎偑堷偒掲傑偭偰偄偔斢廐偲偄偆婫愡丅傑偨堦擭丄擭椫傪廳偹傞偙偲偵側傞丅
丂偝偰丄枅擔怴暦梉姧偵楢嵹偝傟偰偄偨係僐儅枱夋乽傑偭傄傜偔傫乿偑係俈擭娫偺枊傪暵偠傞偙偲偵側偭偨丅嶌幰偺壛摗朏榊偝傫偼丄偐偮偰俶俫俲偺僋僀僘斣慻乽楢憐僎乕儉乿乮傕偆庒偄恖偨偪偼抦傜側偄偐丠乯偺敀慻儕乕僟乕傪柋傔偰偄偨恖暔偱偁傞丅摉帪丄巹偼僿儞側偍偠偝傫偲偄偆擣幆偟偐側偐偭偨偺偱偁傞偑丄乽傑偭傄傜偔傫乿幏昅偵偮偄偰偺壛摗偝傫偺夞憐傪撉傒丄怱傪懪偨傟偨丅斵偼係俈擭娫乽傑偭傄傜偔傫乿偺幏昅偺偨傔偵丄梉曽俇帪敿偐傜俋帪敿傑偱偺帪娫丄婘偺慜偵岦偐偄懕偗偨丅偦偺偨傔丄栭娫偺奜弌傕傑傑側傜側偐偭偨偲偺偙偲丅偙偺帪娫丄昤偗側偄昤偗側偄偲偄偆抧崠偺帪娫傪懴偊偨偁偲丄俉帪敿偡偓偵傾僀僨傿傾偑傂傜傔偔偺偩偲偄偆丅偦偟偰丄堦婥欒惉偵昤偒忋偘丄尨峞傪採弌丅斵偺係俈擭娫偺枅擔偼偙偺傛偆側傕偺偱偁偭偨丅
丂係俈擭娫丄偲偰偮傕側偄撉幰傪書偊傞怴暦偺係僐儅枱夋傪昤偒懕偗傞偲偄偆偺偼丄偳傫側偵偐廳埑偩偭偨偙偲偩傠偆丅偦偟偰丄擔乆丄尩偟偄帺暘偲偺偨偨偐偄偑孞傝峀偘傜傟偰偄偨偵偪偑偄側偄丅偙偺偨偨偐偄偺惉壥偑丄巇帠偵旀傟偨恖乆傪榓傑偣丄旝徫傑偣傞枅擔偺嶌昳偵偮側偑偭偰偄偨偺偱偁傞丅壛摗偝傫偑乽楢憐僎乕儉乿偱偲傏偗偨僸儞僩傪弌偟側偑傜丄怱偺拞偱偼柧擔偺嶌昳傊偺廳埑偲偨偨偐偭偰偄偨偲巚偆偲丄恖傪尒傞栚傪傕偭偲怺偔堢偰偰偄偐側偔偰偼側傜側偄偲帺夲偝偣傜傟傞丅栚偺慜偵偼丄斢廐偺偳傫傛傝偲偟偨塤偑峀偑偭偰偄傞丅偩偗偳丄偦偙偵偼傕偆弔偺夎偑惗傑傟偮偮偁傞偺偐傕偟傟側偄丅
丂丂2002/11/5(Tue)丂亙廐偼備偆偖傟亜
丂擔偑曢傟傞偺偑憗偔側偭偨丅搶嫗偱偼俆帪傪夁偓傞偲傕偆偲偭傉傝偲擔偑曢傟傞丅偙偺廡枛偼妛墍嵳媥壣偱丄偺傃偺傃偲塇崻傪怢偽偣傞偐偲巚偄偒傗丄栰曢梡偱擔偑曢傟偨丅搚梛擔偵偼丄抦恖偺寢崶幃偑偁傝丄惵嶳偵弌偐偗偨丅敄乆婥偯偄偰偄偨偙偲偱偁傞偑丄惵嶳捠傝傪曕偒側偑傜丄巹偼偙偙傪曕偔恖庬偱偼側偄偲嵞擣幆偟偨丅巹偵偼傗偼傝桍悾愳偺傎偲傝傗崙暘帥偺桸悈偺彫宎偑偁偭偰偄傞丅偟偐偟丄搶嫗偵弌偰偒偨偲偒偼丄儊僨傿傾偺僀儊乕僕丄僽儔儞僪偱搒怱偵摬傟偨傕偺偩偭偨丅偩偗偳丄恖娫偼僀儊乕僕偩偗偱惗偒傞偱偼側偔丄敡怗傝偱惗偒傞偲偄偆偙偲偵偁傞偲偒偐傜婥偯偒丄懡杸偱惗妶偡傞偙偲偵側偭偨丅偄傗丄懡杸乮亖惔悾乯偵廧傓傛偆偵側偭偰偐傜丄帺暘偺敡怗傝傪庢傝栠偟偨偲尵偊傞偐傕偟傟側偄丅
丂巹偺偙傟偐傜偺巇帠偼丄愭傪媫偖巇帠偱偼側偔丄幐傢傟偨傕偺傪庢傝栠偡巇帠偵側傞偩傠偆丅乽杒偺崙偐傜乿偑偦偆偱偁傝丄漟抳偝傟偨恖偨偪偲偦偺壠懓偑偦偆偱偁傝丄巹偨偪偺幮夛偺傎傫偲偆偺壽戣偑偦偙偵偁傞傛偆偵丅
丂丂2002/11/1(Fri)丂亙徏堜慖庤亜
丂僾儘栰媴嫄恖偺徏堜廏婌慖庤偑戝儕乕僌峴偒傪寛堄偟偨偲偄偆丅巹偵偲偭偰徏堜慖庤偼恖娫偲偟偰懜宧偟偰偄偨恖暔偺堦恖偩偭偨丅扤偩偭偰帺暘偑懪偪偨偄偵寛傑偭偰偄傞偺偵丄崅峑帪戙偐傜宧墦偺楢懕偵傕丄姶忣傪偁傜傢偵偡傞偙偲偺側偄徏堜慖庤偺婍検偺戝偒偝偼丄暲傒偱偼側偄偲巚偭偰偄偨丅偦偟偰丄僪儔僼僩夛媍偱傕丄慖傝岲傒偡傞慖庤偨偪偺拞偱丄嬸抯堦偮尵傢偢丄帺暘偺塣柦偵廬偄丄嫄恖偵擖抍偟偨丅擖抍屻傕偢偽敳偗偨幚椡傪傕偪側偑傜傕丄側偐側偐係斣傪懪偮偙偲偑偱偒偢丄幚椡憡墳偺懸嬾傪摼傜傟傞偙偲偑側偔偰傕丄偨偩扺乆偲帺暘偵岦偐偄丄恖乆偺婜懸傪忢偵忋夞傞幚愌傪廳偹偰偒偨丅側偐偱傕偡偛偄偺偼丄巐巰媴偑懡偄拞偱偺楢懕弌応偱偁傞丅斵偼帺暘傪偙偲偝傜庡挘偡傞偙偲傕側偔丄偨偩峴摦偵傛偭偰丄寢壥偵傛偭偰偁傜傢偟懕偗偨丅巹偼嫄恖僼傽儞偱偼側偐偭偨偑丄徏堜慖庤偺懪惾偩偗偼墳墖偟偨丅帋崌寢壥偺偄偐傫偵偐偐傢傜偢丄偦偺堦懪惾偩偗偱巹偺栚傪揃晅偗偵偟偰偔傟偨偺偼丄彮擭帪戙偺僸乕儘乕偩偭偨墹慖庤埲棃偺偙偲偩偭偨丅
丂婥攝傝朙偐偱丄廃傝傪巚偄尛傞婥帩偪傕恖堦攞嫮偐偭偨徏堜慖庤偑丄儊僕儍乕偵挧愴偡傞偲偄偆丅偙偺寛抐偼偳傫側偵偐嬯廰偺傕偺偩偭偨偺偩傠偆丅巹傕徏堜慖庤偺怱偺傗偝偟偝偼丄戝儕乕僌峴偒偺抐擮偵偮側偑傞偲巚偭偰偄偨丅偟偐偟丄怱偺傗偝偟偝偵怱偺嫮偝偑傑偝偭偨丅峫偊偰傒傞偲丄徏堜慖庤偼偼偠傔偰帺暘偺変傪捠偟偨偲偄偆偙偲偑偱偒傞偩傠偆丅偙偺寛抐偵懳偟偰丄怱偐傜廽暉傪憲傝偨偄丅嫄恖偺偨傔丄擔杮偺僾儘栰媴偺偨傔丄傕偆斵偼廫擇暘偵峷專偟丄恠偔偟偰偒偨丅偙傟偐傜偼嫄恖偺偨傔丄擔杮偺僾儘栰媴偺偨傔偱偼側偔丄帺暘偺偨傔偵慡椡傪恠偔偟偰傎偟偄丅偦偟偰丄偦偺偙偲偙偦偑丄崿柪傪怺傔傞擔杮幮夛偵惗偒傞巹偨偪偵傎傫偲偆偵桬婥傪梌偊偰偔傟傞偺偩偲丄巹偼巚偆丅偁傝偑偲偆両丂徏堜慖庤丅偦偟偰丄傛偄椃棫偪傪両
丂丂2002/10/30(Wed)丂亙妛墍嵳亜
丂崱擭傕僉儍儞僷僗偼妛墍嵳偺婫愡偵側偭偨丅崱擭丄搶嫗宱嵪戝妛偵偼丄僥儕乕埳摗偑傗偭偰偔傞傜偟偄丅杒挬慛漟抳栤戣恀偭惙傝偺帪婜偵丄壗偲傕僞僀儉儕乕側僎僗僩偱偁傞丅乮僥儕乕埳摗偼亀偍徫偄丄杒挬慛偺尋媶亁乮偩偭偨偭偗丠乯偺挊幰偱偁傞乯妛惗偨偪偺僙儞僗傕側偐側偐偄偄丅
丂妛墍嵳偲尵偊偽丄揙栭偟偨傝攽傑傝崬傒傪偟偰偄偨妛惗帪戙偺偙偲傪巚偄弌偡偺偩偑丄妛墍嵳偼妛惗偺偨傔偩偗偱偼側偔嫵堳偺偨傔偺傕偺偱傕偁傞偙偲傪嫵堳偵側偭偰偼偠傔偰抦偭偨丅嫵堳偵偲偭偰妛墍嵳偲偄偆偺偼嵒敊傪曕偄偰偄傛偄傛傊偽偭偨崰偵偁傞僆傾僔僗偺傛偆側傕偺偱丄壗偲傕偁傝偑偨偄傕偺偱偁傞丅崅峑帪戙偺壎巘偼丄廐偺懱堢嵳偺帪婜偵丄壴姫偺媨郪尗帯婰擮娰傪朘偹偰偄偨傕偺偩偭偨偑丄壎巘偺庼嬈偼愨昳偩偭偨丅偍偍傜偐偝偼恖傪堢偰傞傕偺偱偁傞丅偦偆偄偊偽丄懱堢嵳側傫偰僶僇僶僇偟偔偰傗偭偰傜傟側偄偲偄偆桭恖偼丄懱堢嵳偺帪婜丄塮夋娰偵擖傝怹偭偰偄偨丅偦偆偄偆偙偲傪嫋梕偡傞妛峑偩偭偨丅巹偼嵳傝岲偒偱挘傝愗偭偰偄偨偗傟偳傕丄傑偮傠傢偸幰偨偪傪嫋梕偡傞傑偮傝偼丄傑偨奿暿偩偭偨丅
丂傑偮傝偵梮傝嫸偆幰傕丄傑偮傠傢偸幰傕丄擇搙偲偼婣傜偸偙偺廐偺傂偲偲偒傪奿暿偵枴傢偭偰傎偟偄丅
丂丂2002/10/29(Tue)丂亙壏偐偝亜
丂妛惗偺儗億乕僩傪撉傒側偑傜丄偦偺壏偐偝偵嬃偐偝傟傞偙偲偑偁傞丅傕偪傠傫丄帺暘帺恎偺懱壏偲偺嵎偑壏偐偝傪姶偠偝偣傞偺偱偁傝丄偙傟偼摨帪偵巹偺懱壏偺椻偨偝偺偁傜傢傟偱傕偁傞丅帺暘帺恎偺夁嫀傪怳傝曉傞偲丄僩僎僩僎偟偄姶忣偑帺暘偺掙偵悂偒偩傑傝偺傛偆偵捑揵偟偰偄偨丅僩僎僩僎偟偝偵傆傟側偄傛偆偵偡傟偽丄摉偨傝忈傝偺側偄偙偲偟偐昞尰偱偒偢丄壗傕偺偐偑僩僎僩僎偟偝偵偐偡傞偲丄斲掕揑側侾偮偺尒曽偟偐偱偒側偔側偭偨丅偦偺傛偆側帺暘偐傜尒傞偲丄帺暘偺掙傑偱崀傝側偑傜壏偐偄偙偲偽傪朼偓偩偟偰偔傞妛惗偨偪偼丄僗僑僀偺堦尵偵恠偒傞丅偍偩偰偰偄傞傢偗偱傕丄沍傃偰偄傞傢偗偱傕側偄丅偨偩丄帺暘偺傕偭偰偄側偄壗偐傪傕偭偰偄傞懠幰偵懳偟偰丄宧堄傪昞偟偰偄傞偩偗偺偙偲偱偁傞丅
丂巹偺尒曽偼丄柧傜偐偵戝懡悢偺戝恖偨偪偺尒曽偲僘儗偰偄傞偵偪偑偄側偄丅偍偦傜偔挿偄娫丄帺暘偺拞偵挋傔崬傫偱偒偨懱壏偺掅偝偑丄巹偺尒曽偺搚戜偵偁傞丅傑偨丄懱壏偑偳傫偳傫掅偔側偭偰偒偨帪婜偵峔抸偝傟偨悽奅娤丄戝恖娤偑丄旕忢偵榗傫偩傕偺偩偭偨偺偐傕偟傟側偄丅偦傟偱傕丄堦杮偺儗乕儖偵忔傟偽恖惗偼帠懌傝傞偲峫偊傜傟偰偄偨帪戙偲斾傋偰丄崱偺庒幰偨偪偼偦偺撪柺偵偍偄偰寽柦偵惗偒偰偄傞偙偲偼娫堘偄側偄偲巚偆丅偨偩偦偺撪柺傪奜偺峴摦偵寢傃偮偗傞壦偗嫶偑尒偮偐傜側偄偩偗側偺偩丅
丂奜偺峴摦偵寢傃偮偐側偄撪柺偵偼堄枴偼側偄偲偄偆尒曽傕偁傞丅寢壥偑偡傋偰偲偄偆尒曽偩丅偩偑丄壗傜偐偺庤偑偐傝偑偁傟偽丄撪柺偱蹇偄偰偄傞偝偞攇偼戝偒側椡偵側傞偲偄偆尒曽傕偁傞丅偦偟偰丄尒偊側偄傕偺傪堢偰傞偺偑戝愗偩偲偄偆尒曽傕偁傞丅懌傝側偄傕偺傪巜揈偡傞曽朄傕偁傞丅偦偙偵偁傞傕偺偵婥偯偐偣傞曽朄傕偁傞丅惗偒傞曽朄丄妛傇曽朄偼偝傑偞傑偱偁傞丅
丂丂2002/10/28(Mon)丂亙擇暘朄傪挻偊偰亜
丂搶嫗偼廐惏傟偺夣惏偱偁傞丅10寧傕偁偲悢擔傪巆偡偺傒偲側偭偨丅偦偟偰丄偙偺寧傕偄傠傫側弌棃帠偑偁偭偨丅恎嬤側偲偙傠偱偼丄慜夞傕彂偄偨傛偆偵丄擔乆偺巇帠傪捠偟偰丄嫵偊傞懁偲妛傇懁偺娭學惈傪屌掕偟丄嫵偊傞懁偑100偱妛傇懁偑僛儘偱偁傞偙偲傪慜採偲偡傞偁傝曽偐傜丄扤傕偑帺暘帺恎偺拞偵偁傞棟榑傪傕偭偰偍傝丄偦偺棟榑傪柧傞傒偵偟丄岦忋傪傔偞偟偰懳榖傪峴偆偲偄偆偁傝曽傊偺揮姺偑丄嫵偊傞懁偺惉挿偵偮側偑傞偙偲傪懱姶偟偨偲偄偆偙偲偑偁傞丅偦偟偰丄墦偄偲偙傠偱偼丄僶儕搰偱僥儘偑婲偙傝丄儌僗僋儚偱寑応偑愯嫆偝傟丄偲傕偵懡悢偺巰幰傪弌偡偲偄偆弌棃帠偑偁偭偨丅偝傜偵偼丄擔杮偱傕侾恖偺崙夛媍堳偑嫢恘偵搢傟偨丅偦偟偰丄偳偆偄偆崙柉偺怰敾偑壓偝傟偨偺偐栿偺傢偐傜側偄摑堦曗慖偑廔傢偭偨丅
丂恎嬤側偙偲偑傜偲墦偄偙偲偑傜丅娭學偺側偄偙偲偺傛偆偵巚傢傟傞偑丄嬀偲偟偰峫偊傞偙偲傕偱偒傞傛偆偱傕偁傞丅僥儘偼懳榖偺側偄忬懺丄偁傞偄偼懳榖偺攋抅傪堄枴偟偰偄傞丅俋丒侾侾丄偦偟偰俋丒侾侾埲忋偵傾儊儕僇偺傾僼僈僯僗僞儞嬻敋埲棃丄悽奅拞偱懳榖偑攋抅偟偰偄傞丅懡悢攈偲彮悢攈偑偄傞応崌丄懡悢攈偑挳偔帹傪傕偨側偔偰偼丄懳榖偼惉棫偟側偄丅偮傑傝丄嫮幰偼帺傜偑嫮幰偱偁傞偙偲傪帺妎偟丄嫮幰偱偁傞偑備偊偵廃傝傪摜傒偮偗偵偟偰偄側偄偐偲偄偆椣棟傪傕偮偙偲偑媮傔傜傟傞丅偟偐偟側偑傜丄扤傕偑旐奞幰偲側傝丄偦傟備偊偵悽奅傪峔惉偡傞庡懱偱偁傞偲偄偆擣幆傪傕偰側偔側傝丄悽奅偼惼庛偝傪偁傜傢偵偟偰偄傞丅
丂嫵堢偵偍偄偰丄僒乕價僗傪採嫙偡傞懁偲僒乕價僗傪庴偗傞懁偲偄偆擇崁懳棫揑側娭學惈偑昻偟偄傕偺偱偁傞偺偲摨偠傛偆偵丄幮夛偵偍偄偰傕丄僐儞僩儘乕儖偡傞懁偲僐儞僩儘乕儖偝傟傞懁偲偄偆擇暘壔偝傟偨娭學惈偼惼庛惈傪泂傫偱偄傞丅僥儘儖偼偙偺惼庛惈傪撍偄偰偔傞丅偙傟偵懳峈偡傞庤抜偼丄僐儞僩儘乕儖傪嫮壔偡傞偙偲偱偼側偔丄尰嵼丄擇暘壔偝傟偨幮夛偺偄偢傟偺懁偵傕堦恖傂偲傝偺庡懱惈傪堢偰偰偄偔偙偲偵傛傝丄擇暘壔偝傟偨奯崻傪撪懁偐傜攋偭偰偄偔偙偲偩偲丄巹偼巚偆丅
丂擇暘壔偝傟偨奯崻偼撪懁偐傜攋傞傕偺偱偁傝丄奜偐傜庢傝奜偡傕偺偱偼側偄丅奜偐傜庢傝奜偟偰傕偦偙偵偼柍拋彉偲崿棎偑惗傑傟傞偩偗偱偁傞丅擔杮偺妛峑偵偮偄偰尵偊偽丄曃嵎抣嫵堢斸敾偲偦偺屻偺曃嵎抣捛曻偑偦偺椙偄椺偱偁傞丅壗堦偮曄傢傜偢丄崿棎偩偗偑憹偟壛傢偭偨丅曄傢傞偨傔偵偼丄撪懁偐傜攋傜側偔偰偼側傜側偄丅偦偟偰丄撪懁偐傜攋傞椡傪偨傔傞傕偺偼嫵堢偱偁傞丅偦偆偄偆堄枴偱丄僾儘僌儔儉壔偝傟偨乽嫵堢乿偲偼偍偝傜偽偟偨偄巹偩偗傟偳傕丄堎暥壔丒堎悽戙偺懳榖偺拞偱恖偑堢偮偲偄偆乽嫵堢乿偺椡偵偼戝偄側傞婜懸傪婑偣偰偄傞丅
丂丂2002/10/26(Sat)丂亙傎傫偺彮偟亜
丂師偺梊掕偑敆偭偰偄傞偺偱崱擔偼傎傫偺彮偟偩偗丅乽椪彴乿偲偼桙偡懁亅桙偝傟傞懁丄偁傞偄偼嫵偊傞懁亅妛傇懁偺娭學惈傪屌掕揑側傕偺偲偡傞偺偱偼側偔丄偦偺娭學惈傪梙偝傇傝偮偮丄偦偺応偐傜妛傃崌偄丄堢偪崌偆娭學傪惗傒弌偡傕偺丄偦偆偄偆幚姶傪帺暘帺恎偺戝妛嫵堢偺幚慔傪捠偟偰姶偠偮偮偁傞丅偁偁丄傕偆帪娫偩丅偱偼傑偨棃廡両
丂丂2002/10/25(Fri)丂亙僥儘儖嫋偡傑偠亜
丂崙夛媍堳偺愇堜峢婎偝傫偑僥儘儖偺嫢恘偱偦偺柦傪扗傢傟偨丅惌帯壠偺晄惓丄惌姱嵿桙拝偺栤戣偵儊僗傪擖傟偰偄偨偩偗偵偦偺嬝偐傜偺斊峴側偺偐傕偟傟側偄丅巆擮帄嬌側偙偲偼丄崙柉偺偨傔偵摥偄偰偄傞婬桳側惌帯壠偙偦偑僥儘儖偺懳徾偵側傝傗偡偄偙偲偩丅埨慡側幮夛傪抸偔偙偲偵偼敎戝側僐僗僩偲擔乆偺怣梡傪惗傒弌偡抧摴側幚慔偑昁梫偱偁傞丅偟偐偟丄偙傟傪嫼偐偡偺偼梕堈偱偁傞丅僥儘儖偼斱楎偱偁傝丄偦偙偵偼悺暘偺尵偄摝傟偺梋抧傕側偄丅
丂崙夛偼堦抳抍寢偟偰丄僥儘儖偵棫偪岦偐偭偰傎偟偄丅傑偢偼斊恖偺曔懆偲揙掙偟偨攚屻娭學偺媶柧偑媮傔傜傟傞丅偙偙偱摥偐偢偟偰壗偺偨傔偵寈嶡偑偁傞偺偐丅偦偟偰丄偙偺僥儘儖偑惌帯揑側攚宨傪傕偭偰偄偨応崌偵偼丄奺搣偵埲壓偺慬抲傪媮傔偨偄丅搣棙搣棯偺曗慖偼丄恗媊偲偟偰峴傢側偄丅曗慖偱偼丄愇堜偝傫偺惌帯棟擮偺宲彸幰傪懳徾偲偟偨怣擟搳昜傪峴偆丅偦偟偰丄偙傟傪僥儘儖偑婲偙偭偨偲偒偺婱廳側慜椺偲偡傞丅
丂嶦偟偨傕偺彑偪偱嵪傑偝傟傞傕偺偐丅巎幚偲偟偰偼堎榑偼偁偭偰傕柉庡庡媊偺堦偮偺惛恄偲偝傟偨乽斅奯巰偡偲傕帺桼偼巰偣偢乿偺惛恄傪惗偐偡偨傔偵偼丄僥儘儖偱偼壗堦偮摼傞傕偺偑側偄偲偄偆偙偲傪丄崙夛偺憤堄偱帵偝側偔偰偼側傜側偄丅惌帯壠偼丄帺傜偺婋婡偲偟偰庴偗偲傔偰傎偟偄丅僥儘儖偼柉庡庡媊偲巹偨偪偺幮夛偵懳偡傞朻摾側偺偩偐傜丅侾恖偺乮惌帯壆偱偼側偄乯惌帯壠傪幐偆偙偲偼崙柉偵偲偭偰偺寁傝抦傟側偄戝偒側懝幐偱偁傞丅偣傔偰柦偩偗偱傕彆偐偭偰偄傟偽偲巆擮柍擮偱偁傞丅崌彾丅
丂丂2002/10/24(Thu)丂亙榓帶晄摨亜
丂偐偮偰捠偭偰偄偨崅峑偵乽榓帶晄摨乮榓偟偰摨偣偢乯乿偲偄偆暥帤偑擖偭偨妟偑偁偭偨丅捠嬑搑忋丄俶俫俲儔僕僆偱崙夛拞宲傪暦偄偰偄偨丅乽晅榓棆摨乿偲偄偆偐丄怟攏偵忔偭偨傛偆側栰搣偺捛媦偲丄偢傜偟偨傝偡偐偟偨傝偟偰偄傞妕椈摎曎偑墑乆偲懕偄偰偄偨丅乽晅榓棆摨乿偼偦偺応偟偺偓偵偼側傞偗傟偳傕丄挿婜揑偵椡傪偨傔傞偙偲偵偼偮側偑傜側偄丅
丂偙傟偵懳偟偰乽榓帶晄摨乿偼壐傗偐偱戝憶偓偼偟側偄偺偩偗傟偳傕丄帺暘偺偁傝曽傪曐偪丄寎崌偟側偄偲偄偆峔偊偱偁傞丅崱擔偼壗傪彂偙偆偐偲僲乕僩僷僜僐儞偺慜偵岦偐偭偨傜丄傆偲乽榓帶晄摨乿偲偄偆偙偲偽偑晜偐傫偱偒偨丅侾俈丄俉擭傕慜偺妛峑偱偺擔忢惗妶偑偙偆偟偰帺暘偺拞偵捑揳偟偰偄傞偺偩偐傜丄嫵堢偲偄偆傕偺偼怺墦偱偁傞丅
丂丂2002/10/23(Wed)丂亙廽両弮偔傫亜
丂乽杒偺崙偐傜乿偱嫟墘偟偨崟斅弮偔傫偙偲媑壀廏棽偝傫偲丄寢偪傖傫偙偲撪揷桳婭偝傫偑侾俀寧俈擔偵晉椙栰偺嫵夛偱寢崶幃傪嫇偘傞偲偺偙偲丅拠恖偼媟杮壠偺憅杮汔偝傫偲偄偆偺偩偐傜丄乽杒偺崙偐傜乿偺榖側偺偐丄尰幚偺榖側偺偐丄傢偐傜側偔側傞傛偆側僪儔儅僠僢僋側榖偱偁傞丅
丂乽杒偺崙偐傜俀侽侽俀堚尵乿傪娤偰丄寢偪傖傫偵枺偣傜傟偨巹偼丄弮偔傫偑寢崶偡傞側傜偙偺彈惈偟偐側偄偲巚偭偰偄偨丅偲偙傠偑丄僪儔儅偺拞偩偗偱側偔丄僽儔僂儞娗傪撍偒攋偭偰丄尰幚偺俀恖偑寢崶偡傞偲偄偆僯儏乕僗傪抦傝丄壗偩偐婐偟偔偰偨傑傜側偄偺偱偁傞丅
丂乽杒偺崙偐傜乿偼僪儔儅偺傛偆偱偁傝丄僪儔儅傪挻偊偨壗偐偺傛偆偱傕偁偭偨丅傕偪傠傫丄弮偔傫偼媑壀廏棽偝傫偲偼暿恖側偺偩偗傟偳傕丄弮偔傫偺僉儍儔僋僞乕偼柧傜偐偵媑壀廏棽偝傫偐傜偵偠傒弌偟偰偍傝丄傑偨弮偔傫傪墘偠傞偙偲偑媑壀廏棽偝傫偺僉儍儔僋僞乕傪堢偰偰偄偭偨丅偦偟偰丄嵟廔夞偱丄偼偠傔偰乽摝偘偢偵乿岦偒崌偭偨弮偔傫偲偲傕偵曕偔僗僞乕僩儔僀儞偵偮偄偨彈惈偑寢偪傖傫偱偁傝丄偦偺俀恖傪墘偠偨俀恖偑寢偽傟偨丅乽杒偺崙偐傜乿偼栶幰偲偲傕偵帇挳幰傪堢偰偰偒偨僪儔儅偱偁傝丄偙偺僪儔儅偺婣寢偑俀恖偺寢崶偲側偭偨偙偲偑丄乽杒偺崙偐傜乿傪墳墖偟懕偗偰偒偨巹偵偲偭偰丄壗偲傕尵偊偢婐偟偄偙偲側偺偱偁傞丅
丂壗傪尵偭偰偄傞偺偩偑傛偔傢偐傜側偄暥復偵側偭偨偑丄壗偼偲傕偁傟丄偍傔偱偲偆両偙傟偐傜傕嶳偁傝丄扟偁傝偺恖惗傪乽摝偘偢偵乿曕傫偱偄偭偰傎偟偄偲巚偄傑偡丅偍偦傜偔偙偺寢崶偺徹恖偼丄慡崙偵悢愮枩恖偼偄傞乽杒偺崙偐傜乿偺僼傽儞偩偲巚偄傑偡偺偱丅
丂丂2002/10/22(Tue)丂亙挳偔偙偲亜
丂崱擭偺僛儈偼暤埻婥偑偄偄丅偙偺棟桼偺堦偮偼丄僛儈偺慖峫傪妛惗偵擟偣偨偙偲偵偁傞偩傠偆丅嫵巘乮巹乯偼丄榖傪偡傞偙偲偑偱偒傞妛惗偵栚偑峴偒偑偪偩偑丄妛惗偨偪偼堘偆丅挳偔偙偲偑偱偒傞妛惗偨偪傪慖傫偱偄傞丅挳偔偲偄偆塩傒偼丄応傪巟偊傞戝偒側塩傒偱偁傞丅栚偵偼尒偊側偄偗傟偳傕丄挳偒庤偺幙偲偄偆偺偼丄僐儈儏僯働乕僔儑儞偵偍偄偰寛掕揑側偙偲側偺偱偁傞丅
丂嫵巘偺巇帠偼丄惡傪忋偘丄惗搆偨偪傪堷偭挘偭偰偄偔傕偺偩偲偄偆崻怺偄愭擖娤偑偁傞丅偟偐偟丄備偭偨傝偲偟偨帪娫偺棳傟傞嬻娫傪憂傞偙偲偑偱偒傞嫵巘偼丄挳偒忋庤側恖偱偁傞丅傑偨丄挳偒忋庤側妛惗偼丄僴僢偲偝偣傜傟傞傛偆側傗傢傜偐偄嫵巘亅巕偳傕娭學偺偁傞嫵堢幚廗傪塩傓偙偲偑偁傞丅
丂暦偒暘偗偺側偄巕偳傕偐傜丄暦偒暘偗偺偁傞戝恖傊丅偙傟偑惉弉偺堦偮偺偼偭偒傝偲偟偨摴嬝側偺偐傕偟傟側偄丅巹偨偪偑偙傟傑偱偺嵨寧傪偐偗偰憂傝忋偘偰偒偨僛儈偼丄乬挳偔乭僛儈側偺偩偲偄偆偙偲偵夵傔偰婥偯偔偙偲偑偱偒偨丅
丂丂2002/10/21(Mon)丂亙寧梛擔偺挬亜
丂愭廡枛丄僛儈偺帒椏傪帺戭偵傕偭偰婣傞偺傪朰傟偰丄戝妛偵抲偄偨傑傑偩偭偨偺偱丄寧梛擔偵挬憗偔弌嬑偟偰梊廗傪偟傛偆偲偄偮傕傛傝憗偔壠傪弌偨丅挬憗偗傟偽摴偼嬻偄偰偄偰丄僗僀僗僀偲戝妛傑偱峴偗傞偐偲巚偄偒傗丄偙傟傑偱偱嵟崅偺廰懾偵姫偒崬傑傟偰丄偲傫偩栚嶼堘偄偩偭偨丅搶嫗偺挬偺廰懾傗嫲傞傋偟丅巹偺挬憗偔偲偄偆偺偼丄恖乆偺乬晛捠乭偲偄偆偙偲傪偡偭偐傝朰傟偰偄偨丅
丂寧梛擔偺塉偺挬丄扤傕偑廳嬯偟偝傪書偊偰偄傞偵偪偑偄側偄偗傟偳傕丄捠傝傪媫偖恖乆偺巔偐傜偼丄偦傟偧傟偑偦傟偧傟偺帩偪応偱偨偨偐偭偰偄傞條巕偑偆偐偑偊偰丄惔乆偟偝傪姶偠偨丅偝偰丄偙傟偐傜偳傫側侾廡娫偑懸偪庴偗偰偄傞偺偩傠偆丅
丂丂2002/10/18(Fri)丂亙徍榓係侽擭戙亜
丂怴暦偼徍榓係侽擭戙偵撍擖偟偨丅巹偑惗傑傟偨帪戙偱偁傞丅偩偑丄徍榓係侽擭戙偵擖傞偲丄乬惗妶乭偺壙抣偑彊乆偵婓敄壔偟偰偄偔偺傪姶偠傞丅乬僑僣僑僣乭偟偨恖娫偺惗偒條偑師戞偵嬒幙壔偟偰偄偔偺偑偙偺帪戙偩偭偨偺偐傕偟傟側偄丅
丂偟偐偟丄妛惗偨偪偲怺偔偮偒崌偭偰傒傞偲丄崱偺帪戙偵偁偭偰傕丄乬僑僣僑僣乭偟偨帺暘傪戝愗偵怱偺墱怺偔偵偟傑偭偰偄傞妛惗偨偪偑偄傞偙偲偵婥偯偐偝傟傞丅乬摟柧壔乭偺埑椡偵峈偟偰丄乬僑僣僑僣乭偟偨帺暘傪庣傞偨傔偵丄偼傝偹偢傒偺傛偆偵惗偒偰偒偨帺暘偺夁嫀傪怳傝曉傞丅偦偟偰丄崱丄帺暘傪怳傝曉傝丄妛惗偨偪傪尒偮傔傞偲丄嫵堢夵妚偵嵟傕昁梫側偙偲偼丄偼傝偹偢傒偺偼傝傪堷偭偙敳偔偙偲偱傕側偔丄傂偭傁偑偡偙偲偱傕側偔丄乬僑僣僑僣乭偟偨帺暘傪偦偺傑傑偝傜偗弌偣傞傛偆側嬻娫偯偔傝偱偼側偄偩傠偆偐丅
丂偦偺偨傔偵偼丄偣傔偰帺暘乮亖戝恖乯偑傑偢乬僑僣僑僣乭惗偒偰偄偔偙偲偩傠偆丅偲偄偄偮偮丄偛懚偠偺捠傝丄巹偼慡慠乬僑僣僑僣乭偟偰偄傑偣傫偑丅偦傟偱傕丄婥帩偪偩偗偼乬僑僣僑僣乭偲丄挘傝愗傝偡偓偰揹怣拰偵傇偮偐傜側偄傛偆偵曕偄偰偄偒偨偄傕偺偱偡丅
丂丂2002/10/17(Thu)丂亙徍榓俁侽擭戙亜
丂巇帠偺娭學偱丄嵟嬤丄徍榓俁侽擭戙偺怴暦傪撉傫偱偄傞偺偩偑丄偦偙偐傜姶偠傜傟傞偺偼丄攕愴偐傜傑偩廫悢擭偟偐宱偭偰偄側偄偲偄偆嬞挘姶偱偁傞丅愴憟偺婰壇偑恖乆偺怱偵崗傒崬傑傟丄偦傟偑偳偆偟偰傕庣傜側偔偰偼側傜側偄堦慄偺傛偆側傕偺傪惗傒弌偟偰偄傞丅偍僇僱丄塰梍丄棫恎弌悽丄悽娫懱丄偙偆偟偨傕偺傛傝傕戝愗側乬惗妶乭偺壙抣偑丄偁傞峀偑傝偺拞偱嫟桳偝傟偰偄偨帪戙偺嬻婥傪姶偠傞偙偲偑偱偒傞丅偙偆偟偨偲偒丄怴暦偵杤擖偟側偑傜怱偑壐傗偐偵側傝丄怴偨側椡傪摼傞帺暘偵婥偯偔偙偲偑偁傞丅
丂愭傪媫偖偺傕偄偄偑丄偲偒偵偼棫偪巭傑偭偰丄堦愄慜傪怳傝曉偭偰傒傞偺傕丄怱偺暯埨偵寚偐偣側偄偙偲偐傕偟傟側偄丅
丂丂2002/10/16(Wed)丂亙巇帠亜
丂帠乮偙偲乯偵巇乮偮偐乯偊傞偲彂偄偰巇帠丅堦偮偺帠偵巇偊傞偙偲偱恖娫偼帺暘傪堢偰偰偄偔偺偩傠偆丅懡偔偺恖偑乽帺桼乿傪傕偰偁傑偟偰偄傞帪戙丅偙傟偐傜偼惗奤傪偐偗偰巇偊傞偵抣偡傞帠傪扵傞偙偲偑壽戣偵側偭偰偔傞偺偩傠偆丅崻柍偟憪偺乽帺桼乿偱偁傞偙偲傛傝傕丄帺暘屌桳偺乽巇偊傞帠乿偵曔傜偊傜傟偰偄傞傎偆偑丄偢偭偲帺桼偱偁傝摼傞丅偦偟偰丄帺桼傪扗偆傕偺傊偺掞峈偺嫆揰偲傕側傝摼傞丅
丂丂2002/10/15(Tue)丂亙怴暦偺側偄挬亜
丂怴暦偺側偄挬偼偡偽傜偟偄丅捑巚偺偲偒偑偢偭偲懕偔偐傜丅怴暦偺側偄挬偼廳嬯偟偄丅偝傑偞傑側悽帠偱怱傪傑偓傜偡偙偲偑偱偒側偄偐傜丅怴暦偺側偄挬偼巒摦偑憗偄丅帪娫傪偮傇偡傕偺偑側偄偐傜丅怴暦偺側偄挬偼帺暘帺恎傪撉傓傂偲偲偒丅偦傟偱傕丄側偤偩偐怴暦傪偲偭偰偄傞丅
丂丂2002/10/11(Fri)丂亙廽朇亜
丂乽帺桼乿偺斀懳傪乽懇敍乿偲峫偊傞偲丄偳偙傑偱乽帺桼乿傪媮傔偰傕乽帺桼乿偵偼側傝摼側偄丅偦偺傛偆側栤偄偐偗傪丄偁傞崅峑偺愭惗偐傜偄偨偩偄偨丅旜嶈朙偑媮傔偨乽帺桼乿傕傑偨偦偺傛偆側傕偺偩偭偨偺偱偼側偄偐偲丅
丂旜嶈朙偺乽懖嬈乿偵偼丄乽堦偮偩偗傢偐偭偰偄偨偙偲丄偙偺巟攝偐傜偺懖嬈乿偲偄偆堦愡偑偁傞丅摨悽戙偺峳傟偨妛峑傪惗偒丄峳傫偩怱傪嫟桳偟偰偄偨傕偺偲偟偰丄乽懖嬈乿偼嫟姶偱偒傞傕偺偩偭偨偑丄偙偺堦愡偼偳偆偟偰傕銬偵棊偪側偐偭偨丅乽巟攝偐傜偺懖嬈乿側傫偰傕偺偑偁傞偺偐丠丂偦偟偰丄乽巟攝偐傜偺懖嬈乿偑傢偐偭偰偄傞乮帺柧偺乯偙偲側偺偐丠丂巹偵偼偳偆偟偰傕棟夝偱偒側偐偭偨丅
丂乽帺桼乿偺斀懳偼丠偲巹偑恞偹傜傟偨傜壗偲摎偊傞偩傠偆偐丅乽帺暘偵廁傢傟偨忬懺乿偩傠偆偐丅乽帺乿暘偺棟乽桼乿偵偟偑傒偮偄偨忬懺偩傠偆偐丅乮崱偺恖乆偑捛偄媮傔偰偄傞乽帺桼乿傪乽帺乿暘偺棟乽桼乿偲巜揈偟偨偺偼丄巹偺愭攜偱偁傞乯丂彮側偔偲傕丄崱丄巹偑乽帺桼乿偺斀懳偲偟偰憐婲偡傞傕偺偼丄乽巟攝乿偱傕乽懇敍乿偱傕側偄丅
丂懠幰偲偺娭學偺拞偵偁傞帺暘傪庴偗擖傟丄偦偙偱偺帺暘偺棫偪怳傞晳偄丄偁傝傛偆傪峫偊傞偲偒丄彮側偔偲傕乽帺暘偵廁傢傟偨忬懺乿傛傝乽帺桼乿偱偁傞傛偆偵巚偊傞丅偍偦傜偔恖偑乽巇帠乿傪偡傞偺偼丄懠幰偲偺娭學偺栐偺栚偺拞偵乽嶲壛乿偡傞偨傔偱偁傝丄偦偺偙偲偵傛偭偰帺暘偵乽惂栺乿傪偐偗丄乽帺桼乿傪媮傔傞塣摦偵擖傞偺偩傠偆丅乽帺桼乿偲偼偍偦傜偔庴摦揑側傕偺側偺偩丅
丂偙偙傑偱彂偄偨偲偙傠偱楴曬両丂偨偭偨崱丄揹榖偑偐偐偭偰偒偰俀擭慜偺懖嬈惗偑搶嫗搒偺嫵堳嵦梡帋尡乮彫妛峑乯偵崌奿偟偨偲偺偙偲丅偡偛偔僙儞僗偺偄偄丄偟偐傕崻惈偺偁傞彈巕妛惗偩偭偨偺偱丄婌傃傕傂偲偟偍偱偁傝傑偟偨丅堦嶐擔丄嶐擔偺僲乕儀儖徿偵傕憹偟偰丄巹偵偲偭偰偼偆傟偟偔丄傑偨偍傔偱偨偄榖偱偟偨丅偙偺棑傪撉傫偱偔傟偰偄傞妛惗彅孨偵傕丄偤傂偲傕偁偒傜傔偢偵僠儍儗儞僕偟偰傎偟偄偲巚偄傑偡丅偱偼丄崱擔偼偙偺曈偱両
丂丂2002/10/10(Thu)丂亙暽嬻亜
丂廐惏傟偱偁傞丅憉傗偐側廐偺擔丅侾侽寧侾侽擔偼惏傟偺摿堎擔偲尵傢傟偰偄偰丄惏傟傞妋棪偑崅偄偦偆偱偁傞丅偦偟偰丄偦偺尵傢傟偺捠傝偺惵嬻丅搶嫗僆儕儞僺僢僋偲憡傑偭偰丄偙偺擔偑乽懱堢偺擔乿偱偁偭偨偙偲偵偼柧傜偐側堄枴偑偁偭偨偺偵丄宱嵪岠壥側傞傕偺偺偨傔偵丄侾侽寧侾侽擔偺乽懱堢偺擔乿偼幐傢傟偰偟傑偭偨丅恖乆偺惗妶偺儕僘儉偵傕側偭偰偄傞廽擔傪丄埨堈偵摦偐偡偙偲偼怲傫偱傎偟偄偲偙傠偱偁傞丅傑偁乽懱堢偺擔乿側傫偰柦柤偼丄偪傚偭偲墴偟偮偗偑傑偟偄偺偱丄乽椢偺擔乿偑偁傞偺側傜丄乽惵偺擔乿偵曄峏偟偰傕傜偄偨偄偲偄偆偺偑屄恖揑側堄尒偱偁傞丅偨偩丄摨偠棟孅偱丄恖乆偺惗妶偺儕僘儉偵側偭偰偄傞廽擔偺柤慜傪偦偆偦偆埨堈偵摦偐偡偙偲偼怲傫偱傎偟偄偲偄偆斀榑偑偁傞偩傠偆偐傜丄偙偺榖偼偙偺曈偵偟偰偍偙偆丅
丂偝偰丄擇擔懕偗偰擔杮弌恎偺僲乕儀儖徿庴徿幰偑抋惗偟偰丄嬃偄偰偄傞丅嶐栭丄彫幠愭惗偲摨偠塅拡慄尋媶強偵嬑傔傞桭恖偵丄乽僲乕儀儖徿丄偍傔偱偲偆両乿偲揹榖傪偐偗偨偲偙傠丄乽僆儗偠傖側偄傛乿偲尵傢傟丄乽偱傕丄摨偠僾儘僕僃僋僩傗偭偰偄偨傫偱偟傚偆乿偲恞偹傞偲丄乽偄傗丄椬偺尋媶幒偩偭偨乿偲偄偆曉帠丅埆偄偙偲尵偭偰偟傑偭偨偐側偲巚偭偰偄傞偲丄乽崱擔傕偆堦恖丄僲乕儀儖徿偲偭偨傜偟偄傛乿偲偄偆榖丅乽偊偭乿偲偼偠傔忕択偐側偲巚偭偰偄偨偑丄側傫偲庴徿偝傟偨偛杮恖傕乽僪僢僉儕乿偐偲巚偭偰偄偨傜偟偄丅揷拞偝傫偼傑偩係俁嵥偲偄偆偐傜嬃偒偱偁傝丄嬤偄悽戙偲偟偰偆傟偟偝傕偁傞丅乮嵟嬤丄嬤偄悽戙偺僯儏乕僗偲偄偊偽丄忣偗側偄斊嵾僯儏乕僗偽偐傝偩偭偨偐傜乯
丂偲偙傠偱丄妝偟偐偭偨偺偼丄彫幠愭惗偵偮偄偰婰偟偰偁偭偨嶐擔偺枅擔怴暦偺婰帠偱偁傞丅庴徿偺婌傃偺弖娫偑偨偄偦偆徻偟偔彂偄偰偁傞側偲巚偭偨偲偙傠丄偙偙侾俆擭娫丄僲乕儀儖徿偺敪昞偺擔偼丄婰幰偨偪偲帺戭偱懸偭偰偄傞偺偑峆椺偵側偭偰偄偨偲偄偆丅晛捠偩偲僺儕僺儕偟偦偆側偲偙傠偩偑丄侾俆擭娫傕婰幰偨偪傪帺戭偵彽偒丄敪昞偺擔傪妝偟傫偱偄偨偲偄偆偲偙傠偵丄彫幠愭惗偺戦梘偝偑偆偐偑偊傞丅偙偺俀恖偺庴徿偑巕偳傕偨偪偺壢妛傊偺偁偙偑傟傪惗傒弌偟丄妛傇偙偲偺妝偟偝偑峀偑傞宊婡偵側傟偽偲丄巚偆丅
丂丂2002/10/8(Tue)丂亙僐僗僉儞亜
丂廐偵側傞偲丄暉搰導愳枔挰偲偄偆偲偙傠偱僐僗僉儞丒僄儞丒僴億儞偲偄偆僼僅儖僋儘乕儗偺僼僃僗僥傿僶儖偑奐偐傟傞丅撿暷傾儖僛儞僠儞偱傂傜偐傟偰偄傞僐僗僉儞壒妝嵳偺擔杮斉偱丄慡崙偐傜侾侽侽傪挻偊傞僌儖乕僾偑嶲壛偟丄墘憈傪妝偟傓丅嵟嬤偱偼嶲壛僌儖乕僾偑憹偊丄柧偗曽傑偱墘憈偑懕偔偙偲傕偁傞丅戝妛帪戙偵柉懓壒妝偺僒乕僋儖偵擖傝丄僼僅儖僋儘乕儗偵偼偠傔偰弌夛偄丄拠娫偨偪偲僐僗僉儞偵弌応偡傞傛偆偵側偭偨丅偦偟偰丄側偤偩偐丄戝妛傪懖嬈偟偰偐傜傕偟傇偲偔弌応傪懕偗丄儊儞僶乕偺憹尭偼偁偭偰傕堦嶐擭傑偱侾俆擭楢懕偱弌応偟偰偒偨丅偩偑丄嶐擭丄僄儞僩儕乕偟偰楙廗傑偱偟偨偺偩偑丄捈慜偱搒崌偑偮偐偢寚応丄偦偟偰丄崱擭偼僄儞僩儕乕傕偣偢偵寚応偲側偭偨丅
丂侾侽寧偼巹偺巇帠偵偲偭偰傕斏朲婜偺堦偮偱丄僐僗僉儞弌応乮偲偦偺偨傔偺楙廗乯偼晧扴偩偭偨偗傟偳傕丄寚応偡傞偲側傞偲怱偵傐偭偐傝寠偑嬻偄偨傛偆偱偁傞丅僼僅儖僋儘乕儗偲偦偺拠娫偨偪偲偺弌夛偄偼丄柧傜偐偵巹偺恖奿宍惉偺偁傞晹暘傪扴偭偰偄偨丅暵偞偝傟偨怱偵姶忣偺昞弌偺婌傃傪嫵偊偰偔傟偨偺偼丄僼僅儖僋儘乕儗偩偭偨丅
丂崱傗拠娫偨偪偺扤傕偑摥偒惙傝偵側偭偨丅崱偟偐偱偒側偄偙偲偵偦傟偧傟椡傪拲偔帪偑棃偨偺偩傠偆丅俀侽擭屻偵嵞傃弌応偱偒傞傛偆偵丄崱傪廳偹偰偄偒偨偄丅
丂丂2002/10/7(Mon)丂亙塉偺偪惏傟亜
丂壠傪弌傞偲偒偵偼寖偟偄塉偩偭偨偑丄戝妛偵摓拝偡傞偲惵嬻偑尒偊偰偄偨丅傕偆搶偺嬻偵傕廐惏傟偺嬻偑峀偑偭偰偄傞丅嶐擔丄僛儈惗偑懡偔強懏偡傞儔僌價乕晹偺帋崌傪娤愴偟偰偒偨丅帋崌偲偄偭偰傕僗僞僕傾儉偱偼側偔丄戝妛偺僌儔僂儞僪偩偐傜丄尒偰偄傞曽偑帋崌偺棳傟偲偲傕偵堏摦偡傞偙偲偑偱偒偰丄椪応姶偁傆傟傞帪娫偩偭偨丅儔僌價乕偺帋崌傪惗偱娤偨偺偼偼偠傔偰偺偙偲偱丄偦偺敆椡偵埑搢偝傟偨丅偙偺擔偺偨傔偵楙廗傪廳偹偰偒偨妛惗偨偪偑偨偺傕偟偔尒偊偨丅廔椆娫嵺偺儁僫儖僥傿乕僉僢僋偱惿偟偔傕帋崌偵偼攕傟偨偑丄壗傜壙抣傪懝側偆傕偺偱偼側偐偭偨丅
丂丂2002/10/5(Sat)丂亙嫵堢幚廗島媊亜
丂崱擔偐傜俁擭惗岦偗偺嫵堢幚廗島媊偑偼偠傑偭偨丅傑偢戞堦夞偼崱擭嫵堢幚廗傪宱尡偟偨係擭惗偺懱尡択偱偁傞丅偄偮傕妛惗偺偙偲偽偵姶怱偡傞偺偱偁傞偑丄崱擭偼妛惗偺峔偊偵傕姶怱偟偨丅島媊偺埶棅偵懳偟偰擇偮曉帠偺夣戻丄偦偟偰壈偡傞偙偲偺側偄榖丅妛惗偺岦偒崌偆峔偊偼丄巹偨偪偵檢偲偟偨婥傪梌偊偰偔傟傞丅堦曽偱丄偙偺婱廳側妛傃偺婡夛傪柍抐偱寚惾偡傞妛惗傕偄偨丅岦偒崌偊側偄帺暘偲岦偒崌偆桬婥傪両
丂丂2002/10/4(Fri)丂亙僪儞丒僉儂乕僥亜
丂僙儖僶儞僥僗偺亀僪儞丒僉儂乕僥亁偼丄偝傑偞傑側撉傒傪壜擻偵偡傞偡偖傟偨僥僋僗僩偱偁傞丅偐偮偰戝妛堾帪戙偺僛儈偱丄偙偺亀僪儞丒僉儂乕僥亁傪撉傫偩偙偲偑偁偭偨丅儗億乕僩偱巹偑乽僪儞丒僉儂乕僥揑側惗偒曽偺尰戙揑側堄枴乿偵偮偄偰彂偄偨偲偙傠丄巜摫偺愭惗偐傜乽僪儞丒僉儂乕僥傪徧巀偡傞偁側偨偺暥復偲偁側偨偺惗偒曽偑慡偔堘偆乿偲徫傢傟丄巹傕嬯徫偟側偑傜傕偄偨偔彎偮偄偨偙偲偑偁傞丅
丂扤偵偱傕怱偺掙偱巚偭偨傛偆偵惗偒傞偙偲偑偱偒側偄帪婜偼偁傝丄暥復偲昞柺揑側偁傝傛偆偵婽楐傪泂傓偙偲偼偁傞丅媡偵偄偊偽丄暥復偲昞柺揑側偁傝傛偆偺婽楐偼丄恖偺惉挿偺婡夛偱偁傝丄彮側偔偲傕徫偆傋偒偙偲偱偼側偄丅
丂巹偑乽僪儞丒僉儂乕僥乿傪垽偡傞偺偼丄儖乕僪儕僢僸俀悽傪垽偡傞偺偲摨偠棟孅偱偁傝丄幐傢傟偨悽奅傪偄偮偔偟傓怱偐傜弌偨傕偺偱偁傞丅恀寱偵乽屻傠岦偒乿側偁傝傛偆傪捛媮偡傞恖乆傊偺偄偮偔偟傒偱傕偁傞丅偲偄偭偰丄巜摫偺愭惗傪愑傔傞偮傕傝傕栄摢側偔丄偨偩恖偺怱偺墱掙偼偳傫側執戝側愭惗偱傕傢偐傝偼偟側偄偲偄偆偩偗偺偙偲偱偁傞丅
丂嶰抮憟媍偺偲偒丄峴摦戉挿傪柋傔偨壨栰徆岾偝傫偼丄晧偗傞偙偲偼傢偐偭偰偄偨偗傟偳傕丄偦傟偱傕峴摦戉挿傪堷偒庴偗偨偲偄偆丅偙偙偵傕恀寱偵乽屻傠岦偒乿側偁傝傛偆偵帺傜傪曺偘傞恖偺巔偑偁傞丅彑偮偙偲傪怣偠丄彑偮偨傔偵偨偨偐偭偨恖埲忋偵悞崅側壗偐傪丄巹偼壨栰偝傫偺惗偒曽偵姶偠傞偺偱偁傞丅
丂楌巎偺徹柧偑100擭屻丄200擭屻偵峴傢傟傞偲偟偨側傜偽丄乽彑偪慻乿乽晧偗慻乿側傫偰偙偲偽偼偁傑傝偵傕旂憡偡偓傞傕偺偱偼側偄偐丅亀僪儞丒僉儂乕僥亁偺嶌昳偵栠傞側傜偽丄僪儞丒僉儂乕僥偺惗偒曽偲丄僪儞丒僉儂乕僥傪徫偆偙偲偱嬻嫊側帺暘偨偪傪枮偨偟偰偄偨婱懓偨偪偺惗偒曽偲丄偳偪傜偑屻悽傊偺堚嶻偲側偭偨偺偐丅偙傟偼堦栚椖慠偩傠偆丅朲偟偄帪戙偩偐傜偙偦丄亀僪儞丒僉儂乕僥亁傪撉傓傂偲偲偒傪傕偭偰丄柧擔偺巇帠偵岦偐偆備偲傝傪傕偪偨偄傕偺偱偁傞丅
丂丂2002/10/3(Thu)丂亙儖乕僪儕僢僸俀悽亜
丂僪僀僣偵峴偭偨偲偒丄巹偑嵟傕妝偟傒偵偟偰偄偨偺偑僲僀僔儏僶儞僔儏僞僀儞忛偱偁傞丅僨傿僘僯乕儔儞僪偺僔儞僨儗儔忛偺儌僨儖偵側偭偨偙偺忛偼丄崱傗悽奅揑側娤岝抧偲側偭偰偍傝丄儈乕僴乕側傕偺偼寵偄側偼偢偺乮傎傫偲偆偼岲偒側偺偐傕偟傟側偄偑丄偄偪偍偆寵偄側僼儕傪偡傞偼偢偺乯巹偺峴摦僷僞乕儞偐傜偄偊偽丄旔偗側偔偰偼側傜側偄儌僲側偺偩偑丄側偤偩偐峴偔慜偐傜偲偰傕庝偐傟偰偄偨偺偱偁傞丅
丂敀捁忛偲偄傢傟傞忛偺僼僅儖儉偺旤偟偝傕偝傞偙偲側偑傜丄偙偺忛傪抸偄偨儖乕僪儕僢僸俀悽偺惗奤偑巹傪庝偒偮偗偨偺偩傠偆丅侾俉係俆擭丄僪僀僣偺撿晹偺僶僀僄儖儞崙墹偺墹巕偲偟偰惗傑傟偨儖乕僪儕僢僸偼侾俉嵨偱墹埵偵廇偔丅偩偑丄偦偺崰丄僪僀僣偱偼杒晹偺僾儘僀僙儞偑僪僀僣摑堦偵岦偗偰拝乆偲弨旛傪惍偊偰偄偨丅嬤戙壔偲掗崙庡媊偺嫞憟偑偄傗偍偆側偔僪僀僣抧曽偵傕墴偟婑偣偨侾俋悽婭敿偽偵偁偭偰丄儖乕僪儕僢僸偼偁偨偐傕杮偐傜弌偰偒偨乽僪儞丒僉乕儂僥乿偺傛偆偵丄拞悽偺媨掛暥壔偵偁偙偑傟丄傂偨偡傜忛傪抸偔偙偲偵慡惛椡傪拲偓崬傫偱偄偔丅僶僀僄儖儞墹崙偺嵿惌偼攋抅偟偨丅偦偟偰丄儊儖僿儞偺悽奅偵柪偄崬傫偩儖乕僪儕僢僸偼丄熡恎偺椡嶌僲僀僔儏僶儞僔儏僞僀儞忛偵偼傢偢偐側娫偟偐懾嵼偡傞偙偲側偔丄侾俉俉俇擭丄嬤偔偺屛偱揗巰懱偲偟偰敪尒偝傟偨丅
丂帪戙嶖岆偺儊儖僿儞墹丒儖乕僪儕僢僸偱偁傞偑丄偙偺屻丄僾儘僀僙儞偺晉崙嫮暫楬慄傪撍偒恑傫偩僪僀僣掗崙偼丄擇搙偺悽奅戝愴偺庡栶偲側傝丄儓乕儘僢僷慡搚傪徟搚偲壔偡偲偲傕偵丄帺傜傕攋柵偡傞偙偲偵側偭偨丅偦偟偰丄俀侾悽婭偵擖偭偨崱丄儖乕僪儕僢僸偑抸偄偨僲僀僔儏僶儞僔儏僞僀儞忛偼丄悽奅拞偐傜娤岝媞偑朘傟傞僪僀僣偺婱廳側娤岝帒尮偵側偭偰偄傞丅
丂偙偙偐傜偼巹偺儊儖僿儞偱偁傞偑丄儖乕僪儕僢僸偼俀侽悽婭偺儓乕儘僢僷偺斶嶴側塣柦傪偳偙偐偱姶偠偲偭偰偄偨偺偱偼側偄偐偲巚偆偺偩丅偦偟偰丄嬤戙壔偲掗崙庡媊偺嫞憟偐傜崀傝偰丄傂偨偡傜拞悽偺儊儖僿儞偵摝旔偟丄偦偺僀儊乕僕傪忛偲偄偆偐偨偪偱悽偵巆偟偨偺偱偼側偄偐偲丅
丂巹偺尋媶幒偵偼丄僲僀僔儏僶儞僔儏僞僀儞忛偱庤偵擖傟偨忛偺億僗僞乕偑忺傜傟偰偄傞丅
丂丂2002/10/2(Wed)丂亙戜晽峫亜
丂戜晽偑丄傑傞偱崟慏偺傛偆偵丄傒偛偲側僐儞僩儘乕儖偱搶嫗榩傪捈寕偟偨丅戜晽偲暦偔偲丄偮偄婥暘偑崅梘偟偰丄偪傖傫偲棃偰偔傟傞偐偲婥偵側傝丄巇帠偑庤偵偮偐側偄巹偱偁傞丅崟慏偑傗偭偰偒偨偲偒丄婥傕偦偧傠側弇惗偨偪傪幎傝偮偗丄扺乆偲島媊傪峴偭偨偲偄傢傟偰偄傞暉戲桜媑偺恀帡偼丄偲偆偰偄偱偒偦偆偵傕側偄丅
丂偦傟偵偟偰傕丄俶俫俲偺俈帪偺僯儏乕僗偱戜晽忣曬傪墑乆偲傗偭偰偄偨偺偵偼嬃偄偨丅搶嫗偩偭偰擔杮偺堦抧曽偩傠偆丅搶嫗偵嫆揰傪偍偄偰偄傞儊僨傿傾偵偦偺姶妎偼偁傞偺偩傠偆偐丅搶嫗偵戜晽偑傗偭偰偒偨崰丄嬨廈偼夣惏偩偭偨傜偟偄丅夣惏偺嬨廈恖偼丄墑乆偲俁侽暘埲忋傕搶嫗偺戜晽忣曬傪尒偣偮偗傜傟偨偙偲偵側傞丅媡傪峫偊偰傒傞偲偙偺堎忢偝偑傢偐傞丅嬨廈偵戜晽忋棨偩偭偨傜丄偣偄偤偄俆暘傎偳傗偭偰師偺僯儏乕僗偩傠偆丅壂撽偩偭偨傜僯儏乕僗偵偝偊側傜側偄偐傕偟傟側偄丅偙偺慜偺壂撽偺戜晽丄偁傟偼偲偰偮傕側偔偡偛偐偭偨丅壂撽偺忋嬻偱傎偲傫偳掆懾偟偰偍傝丄傎傏堦拫栭偵傢偨偭偰栆埿傪傆傞偭偰偄偨丅偁偺戜晽偙偦丄俈帪偺僯儏乕僗傪捵偟偰偱傕曻塮偡傋偒乮曻塮偡傞偵抣偡傞乯戜晽偩偭偨乮偲丄巹偼巚偆乮徫乯乯丅崱夞偺戜晽偼丄偁偭偲偄偆娫偩偭偨丅寖偟偄晽塉偑悂偒偮偗偨帪娫傛傝俶俫俲偺僯儏乕僗偺傎偆偑挿偄偔傜偄偩偭偨丅
丂偦偆偦偆丄壂撽傛傝傕偭偲傂偳偄偙偲傕偁傞丅拞崙傗挬慛敿搰偵偦傟偨搑抂偵丄曬摴偑僾僣儞偲愗傟傞偙偲偩丅偙偺慜偺嬨廈傪偐偡傔偨戜晽偼丄挬慛敿搰偱栆埿傪傆傞偭偰偄偨丅戜晽旐奞偑傕偭偲徻偟偔曬摴偝傟偰偄傟偽丄彫愹庱憡偺杒挬慛朘栤偺偝偄傕丄巹偨偪偼漟抳帠審埲奜偺忣曬傪暋娽揑偵傕偮偙偲偑偱偒偨乮偐傕偟傟側偄乯丅壗偼偲傕偁傟丄抧媴偺棤懁偺偙偲傑偱徻偟偔曬摴偡傞偺偼尰幚揑偱偼側偄偩傠偆偗傟偳傕丄婥偵偟偼偠傔偨戜晽側傜偽丄嵟屻傑偱偮偒崌偆偖傜偄偺姶妎傪傕偪偨偄傕偺偩丅崙嫬傪墇偊偨搑抂偵娭怱傪側偔偟偰偟傑偆儊僨傿傾偺姶妎偐傜偼丄抧媴巗柉偼堢偨側偄偩傠偆偐傜丅偪側傒偵崱夞偺戜晽丄搶杒丄杒奀摴丄僒僴儕儞偱偺旐奞傪怱攝偟偰偄傑偡丅傝傫偛擾壠丄戝忎晇偐側丠
丂丂2002/9/30(Mon)丂亙僴儞僪儀儖亜
丂僴儞僪儀儖偲偄偆妝婍偑偁傞丅楅偺傛偆側妝婍偱侾偮偺妝婍偱侾偮偺壒偟偐弌偡偙偲偑偱偒側偄丅偟偐偟丄戝惃偱憈乮偐側乯偱傞偲丄旤偟偄壒怓偺嬋偑惗傑傟傞丅傎傫傕偺偺僴儞僪儀儖偼傕偺偡偛偔崅壙側偺偩偑丄彮偟彫偝側儈儏乕僕僢僋儀儖偩偲庤崰側抣抜偱峸擖偱偒傞丅巕偳傕偨偪偵儈儏乕僕僢僋儀儖傪嫵偊偰傒偨傜丄偄偮傕偼偁傑傝娭怱偺側偝偦偆側巕偳傕偨偪傕丄偲偰傕擬怱偵墘憈偟偰偄偨丅
丂杒奀摴偺崌廻傪廔偊偰丄嵟弶偺僛儈傪寎偊偨丅妛惗偨偪偵崌廻偺姶憐偵偮偄偰榖傪偟偰傕傜偭偨偲偙傠丄傒傫側偲堦弿偵嶌嬈傪偟偨偲偄偆宱尡偑偲偰傕怴慛偩偭偨傛偆偩丅戝崻偺廂妌傪峴偭偨偺偩偑丄侾杮侾杮偺戝崻偑僴儞僪儀儖偺傛偆側壒怓傪巚偄婲偙偝偣偨丅
丂峫偊偰傒傞偲丄崱偺幮夛偺拞偱丄偳偙傪岦偄偰傕丄晄宨婥偩丄晄嫷偩丄嫞憟偵彑偪敳偐側偔偰偼偲愨偊偢偣偒偨偰傜傟傞惡偑暦偙偊偰偔傞丅偙偺傛偆側拞丄嫞憟傛傝傕嫤摥偑媮傔傜傟傞丄偁傞偄偼嫞憟偺拞偵傕嫤摥偺婌傃偑偁傞擾嬈懱尡偑丄傕偆堦偮偺惗偒傞尨棟傪嫵偊偰偔傟偨傛偆偵巚偆偺偩丅
丂嫞憟丄嫞憟偲偄偆偗傟偳傕丄偙傟偱恖娫偺幙偑岦忋偟偰偄傞偐偲偄偆偲丄巹偺屄恖揑側姶妎偱偼丄偳偆傕偦偆偱偼側偄傛偆偵巚偊傞丅偒偪傫偲恖偺榖傪暦偔偙偲偑偱偒側偄揦堳丄恖偲屇媧傪崌傢偣傞偙偲偑偱偒側偄幮堳丄偙偆偟偨恖乆偵弌夛偆偨傃偵丄傎傫偲偆偵乬嫞憟乭側傞傕偺偑恖娫椡傪堢偰偰偄傞偺偐偲丄偼側偼偩夰媈揑偵側傜偞傞傪摼側偄丅偙傟偵懳偟偰丄嫤摥偺婌傃傪抦偭偨妛惗偨偪偼柧傜偐偵惉挿偟偰偄傞丅崱丄巹偨偪偺幮夛偵媮傔傜傟偰偄傞偺偼丄帺屓愑擟偲偄偆柤偺僿儃側撈彞傪嫮偄傞偙偲傛傝傕丄僴儞僪儀儖偺崌憈偺婌傃偵嶲壛偡傞婡夛傪弨旛偡傞偙偲偱偼側偄偩傠偆偐丅
丂丂2002/9/28(Sat)丂亙摨偠姌偺斞亜
丂俶俫俲偺僪僉儏儊儞僩恖娫偱丄媬媫堛椕偺嵟慜慄偱奿摤偡傞堦恖偺堛巘偺巔偑塮偟弌偝傟偨丅斵偺柤慜偼峳栘彯偝傫丅巹偺崅峑帪戙偺摨憢惗偱偁傞丅崅峑帪戙偵偼傆偔傛偐偩偭偨杍偑惔檞偵尋偓悷傑偝傟丄擔乆岦偒崌偭偰偄傞巇帠偺惁傑偠偝傪暔岅偭偰偄偨丅偦偺僙儞僞乕偵偼丄枅擔丄暯嬒俈恖偺惗巰偺嫬傪偝傑傛偆廳徢偺姵幰偑塣傃崬傑傟傞偦偆偱偁傞丅晄椂偺帠屘偱惗偒巰偵僊儕僊儕偑偐偐偭偨姵幰偲偦偺壠懓傪慜偵丄懄帪偺敾抐偲慖戰偑媮傔傜傟傞媬媫堛偼丄夁崜側楯摥偺偨傔摥偒庤偑彮側偄偲偄偆丅峳栘偝傫偼丄姵幰偺惗巰偵偐偐傢傞巇帠偺廳愑傪慜偵丄偨偩乽惤幚乿偩偗偑帺暘偺偱偒傞偙偲偩偲岅偭偰偄偨丅乽惤幚乿偲偄偆偙偲偽偼丄崅峑帪戙偺壎巘偑傛偔岅偭偰偄偨偙偲偽偱丄峳栘偝傫偼傑偝偵偙偺偙偲偽傪帺暘偺寣偲偟丄擏偲偟偰偄傞傛偆偵巚傢傟偨丅
丂嶐擔丄偙偺棑偵丄杒奀摴敀榁挰偺榁晇晈偺帠審傪婰偟偨偁偲丄僯儏乕僗僉儍僗僞乕丒捁墇弐懢榊偝傫偺乽偁偺偔偝丄偙傟偽偄乿傪偺偧偄偰傒偨傜丄壗偲摨偠帠審偑庢傝忋偘傜傟偰偄傞丅捁墇偝傫偼丄擔杮偺乽壠懓乿乽晇晈乿偺偁傝曽偲偄偆帇揰偐傜丄俋帪娫敿偵傕偍傛傇搟傝偑偳偺傛偆偵偟偰拁愊偝傟偰偒偨偺偐偲偄偆偙偲傪悇嶡偝傟偰偄偨丅巹偺帇揰偲偼傑偨堘偭偨妏搙偐傜偺暘愅偩偭偨偗傟偳傕丄悢偁傞帠審偺拞偐傜摨偠帠審偵傾儞僥僫偑摦偄偨偲偄偆偙偲偵婏嬾傪姶偠偨丅捁墇偝傫傕傑偨乮堦搙傕偍夛偄偟偨偙偲偼側偄偺偩偑乯巹偺崅峑偺戝愭攜偱偁傞丅
丂偁傑傝摨憢偲偄偆偺偱偮傞傓偺偼岲偒偱偼側偄偺偩偗傟偳傕丄摨偠嬻婥傪媧偆偲偄偆偙偲偼塭嬁椡偺偁傞偙偲偩偲巚偭偨丅妛峑偑傕偟嫵堢椡傪傕偮偲偟偨傜丄偦偺尮愹偼娗棟傗寛傑傝帠丄偁傞偄偼愻楙偝傟偨僇儕僉儏儔儉側偳偵偁傞偺偱偼側偔丄応偺椡丄応偺嬻婥偵偁傞偺偱偼側偄偩傠偆偐丅愭擔偺嫵堢曽朄嘦偺庼嬈偱丄乽庼嬈傪惉傝棫偨偣傞偨傔偵昁梫側傕偺偼丠乿偲偄偆栤偄偵懳偟偰丄乽妛傋傞嬻娫乿偲偄偆慺揋側偙偨偊傪曉偟偰偔傟偨妛惗偑偄偨偑丄懜宧偱偒傞愭払丄摨朁偲摨偠嬻婥傪媧偆偙偲偑偱偒偨偙偲偵壗偲側偔姶幱偟偰偄傞丅
丂丂2002/9/27(Fri)丂亙側偡傝偮偗亜
丂枅擔怴暦偺婰帠偵乽乽杒奀摴敀榁挰偺柍怑丄杧愳巗榊偝傫乮俈係乯偑慡恎偵朶峴傪庴偗巰朣偟偨帠審偱丄摴寈撓彫杚彁偼俀俆擔栭丄杧愳偝傫偺嵢丄摰梕媈幰乮俈侾乯傪彎奞抳巰梕媈偱戇曔偟偨丅摰梕媈幰偼俀侾擔偵乽晇偑俆乣俇恖偺庒幰偵偨偨偐傟偨乿偲捠曬偟偰偄偨偑丄挷傋偵懳偟乽夁嫀偺垽恖栤戣傗庰偺忋偱偺朶椡側偳偱嬯楯偝偣傜傟偨崷傒偑偁偭偨乿側偳偲梕媈傪擣傔偰偄傞偲偄偆丅
丂挷傋偱偼丄摰梕媈幰偼俀侾擔屵慜侾侾帪偛傠丄摨挰攱栰偺帺戭偱丄杧愳偝傫偲晇晈偘傫偐偵側傝丄摨擔栭傑偱偺娫丄墸傞丄偗傞側偳偟偰丄慡恎懪杘偵傛傞怱晄慡偱巰朣偝偣偨媈偄丅摰梕媈幰偼栺俋帪娫敿嬤偔丄堦曽揑偵朶峴偟偰偄偨偲嫙弎偟偰偄傞偲偄偆丅
丂摰梕媈幰偼摉弶丄乽晇偼嬤偔偺惗嫤慜偺帺斕婡偱僕儏乕僗傪攦偍偆偲偟偨嵺丄嬥栚摉偰偺庒幰偵廝傢傟偨偲尵偭偰偄偨乿偲愢柧丅偟偐偟丄摨彁偼乮侾乯惗嫤慜側偳偵憟偭偨愓偑側偄乮俀乯栚寕幰偑偄側偄乗乗側偳晄帺慠偲偟偰摰梕媈幰偐傜擟堄偱帠忣傪挳偄偰偄偨丅嵟嬤丄晇晈偘傫偐偑愨偊側偐偭偨偲偄偆丅乿偲偄偆傕偺偑偁偭偨丅
丂側偐側偐寖偟偄偛晇晈偩偭偨傛偆偩偑丄弶弌偺婰帠偱偼乽嬥栚摉偰偺庒幰偨偪偺嫢峴乿偲偄偆偙偲偑柍斸敾偵宖嵹偝傟偰偄偨丅乽杒奀摴敀榁挰乿偲偁傞丅巹偺摢偺拞偱偼丄乽偁偁丄崱傗杒奀摴偺揷幧偱傕庒幰偨偪偼峳傟偰偄傞偺偐丅偦傟傕暋悢偱偛榁恖傪廝偆偲偼壗偲傑偁斱楎側斊嵾偱偁傞偙偲偐丅庒幰梚岇攈偺巹偩偗傟偳傕丄峫偊曽傪夵傔側偔偰偼側傜側偄偺偐傕偟傟側偄丅乿偲偄偭偨傛偆側巚峫偑偐偗傔偖偭偨丅偲偙傠偑偙偺帠審偺惓懱偼丄擔杮偺乽庒幰乿偺栤戣偱偼側偔丄擔杮偺乽壠懓乿偺栤戣偩偭偨丅偦偟偰丄嵟傕拲栚偡傋偒偲巚傢傟傞偙偲偼丄偍偦傜偔乬晛捠偺乭偍偽偁偝傫偱偁偭偨偩傠偆偙偺梕媈幰偑丄嵾傪側偡傝偮偗傞偺偵乽庒幰乿傪慖傫偩偙偲偱偁傞丅
丂偙偺乬晛捠偺乭偍偽偁偝傫偼丄偒偭偲偲偭偝偵乽庒幰乿傪巚偄偮偄偨偺偩傠偆丅偩偑丄嵾傪恖偵側偡傝偮偗傛偆偲偡傞斱楎偝偲偲傕偵丄偦偺懳徾傪乽庒幰乿偵偟傛偆偲偡傞惛恄偼丄擔杮幮夛偺惛恄偦偺傕偺偱偼側偄偐丅嫵堢夵妚崙柉夛媍偼丄庒幰偵曭巇妶摦傪媊柋壔偡傞偙偲傪峫偊弌偟偨丅偟偐偟丄偙傟偼杮枛揮搢偱偁傝丄傎傫偲偆偺栤戣偼丄擔杮偺戝恖偑惉弉偺偐偨偪丄偁傞傋偒幮夛偺僨僓僀儞傪帵偡偙偲偑偱偒偰偄側偄偙偲偵偁傞偲偄偊傞偩傠偆丅惉弉偺僀儊乕僕偺側偄幮夛偱丄偳傫側婓朷傪傕偭偰庒幰偵惗偒傠偲偄偆偺偩傠偆偐丅惉弉偺僀儊乕僕偺偁傞幮夛丄椺偊偽丄怑恖偺悽奅丄媄偺悽奅偱偼丄庒幰偼嬃偔傋偒婸偒傪傕偭偰巇帠偵懪偪崬傫偱偄傞丅庒幰偵昁梫側傕偺偼僀儎側偙偲傪儉儕儎儕傗傞変枬偱偼側偄丅偁偁偄偆戝恖偵側傝偨偄丄偙偆偄偆幮夛傪抸偒偨偄偲偄偆惉弉偺僀儊乕僕偱偁傝丄偦傟偑偁偭偰偙偦壓愊傒傪懴偊傞変枬偑惗傑傟傞偺偩偲丄巹偼巚偆丅
丂乬晛捠偺乭偍偽偁偝傫偑傗偭偰偟傑偭偨乬側偡傝偮偗乭丄偦偟偰偙傟傪専徹傕偣偢偵敪昞丄曬摴偟偨乬晛捠偺乭戝恖偨偪偺乬岆曬乭丄偙偺棤偵偼尒摝偡偙偲偺偱偒側偄曃尒偑愽傫偱偄傞丅偦偟偰丄師悽戙偺幮夛偺扴偄庤偵懳偡傞偙偺曃尒偼丄曻偭偰偍偗偽丄彨棃丄巹偨偪帺恎偺庱傪峣傔傞傕偺偲側傞偩傠偆丅
丂丂2002/9/26(Thu)丂亙挬偺朘栤媞亜
丂庼嬈偑巒傑偭偨丅堦擔偵偟偰旀傟偑恎懱慡懱傪廝偭偰偄傞丅偙偺愭偑巚偄傗傜傟傞丅偝偰丄嶐擔丄尋媶幒偵傗偭偰偒偨妛惗偼丄乽戝妛偺愭惗偭偰丄岲偒彑庤側偙偲傪偟傖傋偭偰偄傜傟偰偄偄偱偡偹偊丅僆儗傕戝妛偺愭惗偵側傠偆偐側乿偲偺偨傕偆偨丅乽偁偼偼偼偼乿丅庒偄偭偰偄偄偹偊丅愭偑尒偊側偄偐傜恖娫偼愭偵恑傔傞偺偱偁偭偰丄愭偑尒偊偨傜恑傓桬婥側傫偰偳偙偐傜傕惗傑傟側偄偱偟傚偆偹丄偒偭偲偳傫側巇帠偱偁偭偰傕丅
丂偝偰丄崱挬偼丄怴尋媶幒偵傔偢傜偟偄朘栤媞偑偁偭偨丅數偱偁傞丅僴僩偝傫偼丄巹偑僲乕僩僷僜僐儞偵岦偐偭偰偄傞丄偪傚偆偳栚偺慜偵崀傝偨偭偰偒偰丄僈儔僗墇偟偵偙偪傜傪僕儘僕儘偲尒偰偄傞丅偁傫傑傝僕儘僕儘偲尒偰偄傞傕偺偩偐傜丄偙偪傜傕僕儘僕儘偲尒曉偟偨傜丄岦偙偆傕僉儑儘僉儑儘偟側偑傜傕丄嬤婑偭偰偔傞丅偲偄偆傢偗偱僈儔僗侾枃傪妘偰偰丄媫愙嬤偲憡惉偭偨傢偗偩偑丄偄傠傫側朘栤媞偑傗偭偰偔傞乽戝妛偺愭惗乿偭偰巇帠偼丄偦偆埆偔傕側偄偐側偲巚傢側偄偱傕側偄乮巐廳斲掕乯崱擔偙偺崰偱偁傞丅
丂丂2002/9/25(Wed)丂亙弌斂亜
丂崱擔偐傜屻婜偺庼嬈偑僗僞乕僩丅搶嫗偼偪傚偆偳廐晽偑怱抧傛偄帪岓偵側傝丄妛傃偵偼嵟揔側僔乕僘儞傪寎偊偰偄傞丅壞偼旘傃夞傝丄廐偵崢傪棊偪拝偗傞偲偄偆偺偼丄婥岓偵崌偭偨惗妶偺條幃偩偲巚傢傟丄崱壞偼崜弸傪旔偗傞偙偲偑偱偒丄偁傝偑偨偐偭偨丅
丂偝偰丄偝傑偞傑側弌棃帠偺拞偵丄幮夛偺曄壔傪姶偠傞偙偲偑偁傞丅偦偺堦偮偑崱夞偺杒挬慛丒漟抳帠審偱偺壠懓偺曽乆偺揙掙捛媦傇傝偱偁傞丅壠懓偺曽乆偼奜柋徣偐傜偺愢柧偵擺摼偡傞偙偲側偔丄旐奞幰偺懌愓丄帠幚偺夝柧傪媮傔偰偄傞丅偙傟傑偱偺擔杮幮夛偩偲丄悽娫偲偄偆僔僗僥儉偑偁傝丄偍忋偺偄偆偙偲偵偼偁傑傝媡傜傢偢偵丄傑偨愑擟偺捛媦偵偍偄偰傕乬側偁側偁乭偱嵪傑偣傛偆偲偡傞孹岦偑嫮偐偭偨傛偆偵巚偆丅
丂偲偙傠偑丄崱夞偺帠審偱偼丄帠幚偺夝柧傊偺嫮偄堄巙偑偁傜傢傟偰偄傞丅帠幚偺夝柧傊偺嫮偄堄巙偲偟偰巚偄弌偡偺偑乮塮夋亀備偒備偒偰恄孯亁乯偱偁傞丅偙偺塮夋偼丄堦恖偺擔杮孯偺暫巑偺婏柇側巰偺恀憡傪偁偒傜偐偵偡傋偔峴摦偡傞墱嶈尓嶰傪捛偭偨婼婥敆傞僪僉儏儊儞僩偱偁傞丅
丂巹偼偢偭偲抦傝偨偄偲巚偭偰偄傞偙偲偑偁傞丅愴昦巰偟偨偲偄傢傟偰偄傞慶晝偺偙偲偱偁傞丅慶晝偼彚廤傪庴偗丄侾俋係俆擭俁寧偵墶恵夑偱朣偔側偭偰偄傞丅恎懱偑偁傑傝忎晇偱偼側偐偭偨偲暦偄偰偄偰愴昦巰偲偄偆偙偲偵懳偟偰壗偲側偔擺摼偟偰偄偨偑丄俁侽戙偺摥偒惙傝偺恖娫偑偦偆娙扨偵巰偸傢偗偑側偄丅傑偨丄恎懱偑偁傑傝忎晇偱側偄恖娫偵懳偟偰丄巰偵帄傞傛偆側孭楙傪嫮偄偨偲偡傟偽丄廫暘側斊嵾偱偁傞丅
丂偙偆偟偨偙偲偼丄擔杮拞偵揮偑偭偰偄傞偙偲偩傠偆丅偦偟偰丄傒傫側偑姮擡偟側偑傜丄帺暘偺嫻偩偗偵擺傔偰丄愴屻傪寽柦偵惗偒偰偒偨偙偲偩傠偆丅偟偐偟丄巹偨偪偺幮夛偵傕乬側偁側偁乭偱偼嵪傑偣偨偔側偄怱偑堢偭偰偒偨偺偱偼側偄偩傠偆偐丅彫愹庱憡偺杒挬慛朘栤傪偒偭偐偗偲偟偰丄娯崙偱傕漟抳帠審偺壠懓傜偑惡傪偁偘偼偠傔偨偲偄偆丅偙偺攇栦偼丄寛偟偰彫偝偄傕偺偱偼側偄丅乮摨帪偵偙偺帠審偵曋忔偡傞攜偵偮偄偰偼丄捁墇弐懢榊偝傫偺乬偁偺偔偝偙傟偽偄乭傕嶲徠偝傟偨偄乯
丂丂偁偺偔偝偙傟偽偄
丂丂2002/9/23(Mon)丂亙廐塉亜
丂搶嫗偼塉偺擔梛擔偵側傝傑偟偨丅偙偺偲偙傠廡枛偼揤婥偑偖偢偮偔偙偲偑懡偄傛偆偱偡丅擔杮楍搰偺惣偺嬨廈偐傜搶偺搶嫗偵弌偰偒偰丄嵟傕婫愡偺堘偄傪姶偠偨偺偑俋寧偱偟偨丅楍搰偺搶偼丄廐塉偑懡偔丄攡塉傛傝傕偙偺帪婜偺傎偆偑崀悈検偑懡偄偦偆偱偡丅堦曽丄楍搰偺惣偼丄攡塉偵偼戝塉偑崀傝傑偡偑丄廐偼斾妑揑偵揤婥偑傛偔丄崅壏偱偡丅偍偦傜偔僆儂乕僣僋奀偺崅婥埑偑娭學偟偰偄傞偺偩偲巚偄傑偡偑丄廐塉偑崀傞偛偲偵壞偑墦偞偐傝丄廐偑嬤偯偄偰偄傞傛偆側婥偑偟傑偡丅
丂嶐栭丄懖嬈惗偲媣偟傇傝偵揹榖偱榖傪偟傑偟偨丅岅渂偑側偔乽偑傫偽偭偰偹乿偲偟偐尵偊側偄巹偵懳偟偰丄斵偼乽愭惗偼偑傫偽傝偡偓側偄傛偆偵丅乽偄偄乿壛尭偱偍婅偄偟傑偡乿偲椳偑弌傞傛偆側偁傝偑偨偄偙偲偽傪偐偗偰偔傟傑偟偨丅偙偲偽傪朼偖偙偲偺戝愗偝傪傂偟傂偟偲姶偠偰偄傑偡丅
丂丂2002/9/20(Fri)丂亙廐擔榓亜
丂廐晽偑怱抧傛偄婫愡偵側傝傑偟偨丅嶐斢偼帺揮幵偱偺婣戭偺摴拞偑敡姦偔丄偟偽傜偔慜傑偱偺壞偺弸偝偲偼暿偺悽奅偱偟偨丅杮擔丄戝妛偺屻婜偺庼嬈偑巒傑傝傑偟偨丅挿偄僔乕僘儞偱偡偑丄偄偮傕偺傛偆偵姰憱傪傔偞偟偰傏偪傏偪偄偒偨偄偲巚偄傑偡丅
丂丂2002/9/19(Thu)丂亙栠傝擖嫃亜
丂壞偺娫丄夵廋偟偰偄偨尋媶幒偺岺帠偑廔傢傝丄愭擔丄怴偟偄尋媶幒偑巒摦偟偨丅暻偲彴偑儕僯儏乕傾儖偝傟丄柺愊偑侾丏俆攞偵側偭偨尋媶幒偼偐側傝夣揔偱丄婥暘堦怴偲偄偭偨偲偙傠偱偁傞丅偳偆傕昻朢惈側恖娫偱丄怴偟偄偲偙傠偵廧傓偲壗偩偐埆偄傛偆側婥偑偟偰偟傑偆偺偩偑丄傗偼傝昁梫側夣揔偝偼僷儚乕傪惗傒弌偡丅昻朢惈偺崻掙偵偁傞偺偼丄昻偟偄恖乆偑偄傞拞偱丄帺暘偩偗偑怱抧傛偄曢傜偟傪偡傞偺偼偍偐偟偄偺偱偼側偄偐偲偄偆丄媽嵍梼揑側敪憐偱偁傞偑丄偙傟偱偼楢崌愒孯揑側瑗楬偵擖傝崬傓傛偆側婥偑偡傞丅偁偝傑嶳憫偵棫偰偙傕偭偨楢崌愒孯偺儊儞僶乕偑挰偵崀傝偨偲偒丄偁傑傝偺埆廘偐傜惓懱偑偽傟偰寈嶡偵偮偐傑偭偨偲偄偆榖偑偁傞偑丄廘偗傟偽悽偺偨傔偵側偭偰偄傞偲偄偆傢偗偱偼側偄丅恖娫偵偼帺傜偺岾暉傪捛媮偡傞偲偄偆尃棙丄偄傗媊柋偑偁傝丄摨帪偵丄懠幰偺岾暉傪摜傒偵偠傞傋偒偱偼側偄偲偄偆媊柋偑偁傞丅帺傜偺岾暉傪捛媮偡傞偙偲傪埆偲媻抏偟丄偦偺惗傪懠幰偺庤抜偲偡傞偙偲傪嫮梫偡傞偲偒丄慡懱庡媊偺晄岾偑朘傟傞偺偱偁傞丅偙傟偼塃丒嵍傪栤傢偢摨偠偙偲偱偁傞丅
丂彫愹庱憡偑杒挬慛傪朘栤偟偨丅偦偟偰丄漟抳帠審偲偄偆僷儞僪儔偺敔傪奐偄偰偒偨丅俉柤偺巰朣偲偄偆帠幚偼丄彫愹庱憡傕偍偦傜偔惵揤偺杵杼偩偭偨偙偲偩傠偆丅傢偐偭偰偄傟偽丄偦偺敪昞偺応偵僲僐僲僐偲弌岦偄偰偄偔傢偗偑側偄偐傜偱偁傞丅峴曽晄柧偺巕偳傕傜傪懸偪懕偗偰偄偨壠懓偺曽乆偼傑偙偲偵婥偺撆偱偁傝丄尵梩傕側偄丅庱憡偑朘栤偡傞偲側傟偽丄壗傜偐偺彑嶼偑偁傞偵偪偑偄側偄偲巚傢傟偨偩傠偆偟丄摉擔挬偺壠懓偺曽乆偺昞忣偼婓朷偵偁傆傟偰偄偨丅偦偟偰丄偁偺寢枛丅婓朷傪梌偊傜傟偨偩偗巆崜偱偁偭偨丅
丂栭傢偢偐側帪娫僥儗價傪娤偨偩偗偺巹偵偲偭偰傕丄偙偺寢枛偼崜偔丄柊傟側偄傛偆側傕偺偱偁偭偨丅壠懓傪棟晄恠偵幐偄丄偦偟偰婓朷傪帩偪偮偯偗丄棤愗傜傟傞丅偙偺偙偲偼偐偔傕嬯偟偄傕偺偱偁傞偺偐丅摉帠幰偺柍擮偵偔傜傋傟偽丄傎傫偺傎傫偺傢偢偐偱偁傞偑丄憐憸偡傞偙偲偼偱偒傞丅
丂偦偟偰丄妏搙傪曄偊傟偽丄挬慛敿搰偐傜嫮惂楢峴偝傟偰偒偨恖乆偺壠懓傕丄摨偠傛偆側巚偄傪傕偭偨偼偢側偺偩丅偙偺帠審偐傜妛傇傋偒偙偲偼丄杒挬慛憺偟偲偄偆姶忣偱傕側偔丄偳偭偪傕偳偭偪偲偄偆嫃捈傝偱傕側偔丄恖乆偵懳偟偰棟晄恠偵壛偊傜傟傞崙壠朶椡傪嫋偡傋偒偱偼側偄偲偄偆偙偲偩偲丄巹偼巚偆丅
丂漟抳偝傟偨擔杮崙愋傪傕偮恖乆偑杒挬慛偵崙壠朶椡傪壛偊傜傟偨偺偲摨偠傛偆偵丄杒挬慛偺懱惂偵斀懳傪彞偊傞杒挬慛偺恖乆傕傑偨崙壠朶椡傪壛偊傜傟偰偒偨丅傑偨丄岺嶌慏偵忔偭偰偄偨岺嶌堳偨偪傕帺傜偺岾暉傪捛媮偡傞偙偲傪嫋偝傟偢丄奀偺憯孄偲徚偊偰偄偭偨丅斵傜傕傑偨崙壠朶椡偺媇惖幰偱偁傞偲尵偊傞偩傠偆丅堷偒梘偘傜傟偨岺嶌慏偵偼忔堳偺嫃廧嬻娫偡傜側偐偭偨偲尵傢傟偰偄傞丅
丂怉柉抧巟攝偺帪戙偵丄挬慛敿搰偱偼懡偔偺恖乆偑寣傪棳偟丄帺桼傪扗傢傟偰偄傞丅偙偺乬彏偄乭偲偄偆傕偺偑丄嬥惓擔偺撈嵸偲杒挬慛偺崙壠朶椡傪懚懕偝偣傞偨傔偺乬宱嵪墖彆乭偵側傞偲偟偨傜丄挬慛敿搰偺恖乆偼擇搙偵傢偨偭偰丄擔杮偵怤偝傟傞偲偄偆偙偲偵側傞偺偱偼側偄偐丅乬宱嵪墖彆乭偼丄杒挬慛偺崙壠朶椡偺懚懕傪嫋偝側偄偲偄偆偙偲偲僙僢僩偱峴傢傟側偔偰偼側傜側偄丅擔杮恖漟抳偩偗偱側偔丄杒挬慛偵廧傓恖偨偪偵傕丄憐憸椡傪摥偐偣偨偄丅側偤側傜偽丄斵傜偼娔崠偺拞偵偍傝丄巹偨偪偼娔崠偺奜偵偄傞偐傜偩丅娔崠偺奜偵偁傞幰偨偪偺柍娭怱偼丄娔崠偺拞偵偄傞幰偨偪偺愨朷偵捠偢傞偲偄偆偙偲偱偁傞丅偦偟偰丄偙偺娭學偼偄偮媡揮偟側偄偲傕尷傜側偄丅
丂怴偟偄尋媶幒偐傜搶偺嬻偵寧偑尒偊偰偄傞丅杒挬慛偺恖乆傕摨偠寧傪尒偰偄傞偙偲偩傠偆丅崱偼夣揔側怴偟偄尋媶幒偑娔崠偲側傜側偄偨傔偵傕丄崙偲偄偆僼傿僋僔儑儞偲偦偙偵惗偒傞恖乆傪暘偗偰尒偮傔傞偙偲偺戝愗偝傪怺偔峫偊偰偄偒偨偄偲巚偆丅
丂丂2002/9/16(Mon)丂亙嫟妛亜
丂僔儕傾僗側榖偐傜撪椫僱僞偵媫揮夞偟偰嫲弅偩偑丄幚偼巹偼抝巕峑偺弌恎偱偁傞丅彫妛峑丄拞妛峑偼抧尦偺岞棫偵捠偭偰偄偨偑丄崅峑偼巹棫偺抝巕峑偵捠偭偨丅俋擭娫丄偄傗梒抰墍偐傜擖傟傞偲侾俀擭娫丄抝彈偑偩偄偨偄敿悢偢偮偺嬻娫偵恎傪偍偄偰偄偨偺偱丄抝偟偐偄側偄抝巕峑偵偠偭偝偄偵峴偭偨偲偒偺僔儑僢僋偼尵梩偵偱偒側偄傎偳偩偭偨丅乽僆儗偺惵弔傪曉偣両乿偲嫨傃偨偄傛偆側婥暘偩偭偨丅乬僴僀僗僋乕儖乭偵彈巕偑偄側偄偺偼抳柦揑偱偁傞丅偦偟偰丄乽嫟妛偵偟傠乿偲偄偆嬻偟偄嫨傃惡傪忋偘側偑傜丄偦傟偐傜偺俁擭娫丄汷攌偵弌傜傟傞擔傪巜愜傝悢偊側偑傜丄帺暘偺慖戰傪庺偭偰偄偨丅
丂偝偰丄愭擔丄崅峑帪戙偺壎巘傛傝庤巻偑棃偨丅壗偲偦偙偵偼乽偲偆偲偆彈巕傪擖傟傞偙偲偵側傝傑偟偨丅偪傑偨偱偼戝偼偟傖偓偱偡乿偲偁傞偱偼側偄偐丅乽僈僈乕儞両夨偟偄両両両両両乿
丂傕偆俀侽擭傎偳慜偺偙偲偲偼尵偄側偑傜丄乽傕偭偲憗偔偟偰偔傟傛乿偲偮傇傗偄偰偄傞帺暘偑偄偨丅偦傟偵偟偰傕丄屻攜偺偨傔偵偙偺橣岕傪慺捈偵婌傋偽偄偄傕偺偺丄壗偲巹偺怱偺偝傕偟偄偙偲偐丅偄傗丄偁傞偄偼愴慜丒愴拞偵妛峑偵捠偭偨恖偨偪傕丄愴屻嫵堢傪傒偰摨偠傛偆偵巚偭偨偐傕偟傟側偄丅
丂偙偺暥復傪彂偒側偑傜丄崅峑帪戙偵巹偑峫偊偰偄偨偙偲傪傆偲巚偄弌偟偨丅偦傟偼乽彈巕偑偄側偔偰丄抝巕偩偗側偺偼柧傜偐偵娫堘偭偰偄傞丅抝巕偩偗偺悽奅偵惗偒偰偄偰傕丄悽奅偺敿暘偟偐擣幆偟偨偙偲偵偼側傜側偄偱偼側偄偐乿偲偄偆傕偺偩偭偨丅傕偪傠傫丄彈巕偲堦弿偵偄偨偄偑偨傔偺洓棟孅偺傛偆側傕偺偩偭偨偑丄巚偄弌偟偰傒傞偲側偐側偐偄偄慄偄偭偰偄傞丅
丂崱偺栤戣偵堷偒偮偗偰偄偊偽丄巹偺姶妎偼乽傾儊儕僇偐傜偺忣曬偩偗偱偼丄悽奅偺敿暘乮傕偪傠傫埲壓乯偟偐棟夝偟偨偙偲偵側傜側偄偱偼側偄偐乿偲偄偆姶妎偩偭偨偺偱偼側偄偩傠偆偐丅
丂曣峑傕嫟妛偵側傞偲偄偆偙偲偩偟丄偦傠偦傠摨憢夛偵偱傕弌惾偟傛偆偐側丅側傫偰傕偪傠傫丄僂僜偩偗偳丄偁偺壓僱僞偩傜偗偩偭偨曎榑戝夛偑崱屻偳偆側傞偺偐丄婥偑偐傝偱偁傞丅偦傟偐傜丄偙傟傑偱婥妝偵懌傪塣傫偱偄偨曣峑偵丄偙傟偐傜傕婥妝偵懌傪塣傫偱偄偄偺偩傠偆偐偲巚偆傛偆偵側偭偨偺偼丄側偤偱偟傚偆偐丅
丂丂2002/9/11(Tue)丂亙俋丒侾侾埲崀亜
丂俀侽侽侾擭俋寧侾侾擔偺徴寕偼朰傟傞偙偲偼偱偒側偄丅乽攋柵乿偲乽埫崟乿偺帪戙傪梊姶偝偣偨丅偟偐偟丄偦偺捈屻偺悽奅拞偺恖乆偐傜婑偣傜傟偨傾儊儕僇傊偺摨忣偲僥儘儕僘儉傊偺堎媍怽偟棫偰偼丄傎偺偐側乽婓朷乿傪姶偠偝偣傞傕偺偩偭偨丅偲偙傠偑丄偦偺屻丄僥儘儕僘儉偵懳偟偰乽曬暅乿偲偄偆柤偺愴憟傪巇妡偗偨傾儊儕僇偺峴摦偵偼丄乽愨朷乿傪姶偠偨丅斶嶴偺枮偪偨恖椶偺楌巎偺拞偱恖乆偑擲傝嫮偔堢傫偱偒偨堦嬝偺岝傪丄乽朶椡乿偱摜傒偵偠傞傕偺偩偭偨偐傜偩丅
丂嶁杮棿堦偼乬俋丒侾侾乭偵傛偭偰怴偨側帠懺偑惗偠偨偺偱偼側偄偲偄偆丅偨偩乬俋丒侾侾乭偵傛偭偰悽奅偺偁傝傛偆偑柧傞傒偵弌偝傟偨偩偗偩丄偲丅嫮幰偑庛幰傪柵傏偡悽奅偺偁傝傛偆偼丄嬤戙俆侽侽擭傪偼傞偐偵挻偊偰丄儂儌丒僒僺僄儞僗偺楌巎偵偝偐偺傏傞偲丄嶁杮偼尵偆丅
丂庬懓偑憡憟偆帪戙偐傜壗傕恑曕偡傞偙偲側偔丄嫮幰偑庛幰傪柵傏偟懕偗偰偄傞偺偩偲偟偨傜丄偦偟偰丄偙偺偙偲偑恑曕偩偲巚偄懕偗偰偄傞偺偩偲偟偨傜丄偍偧傑偟偄寢枛偑懸偭偰偄傞丅偼偨偟偰恖椶偵偲偭偰嫮偝偲偼崱傕側偍柍忦審偵壙抣偁傞傕偺偱偁傝懕偗偰偄傞偺偩傠偆偐丅嫮偝偼彅恘偺寱偱偁傝丄偦傟傪奜偵岦偗偨傜廃傝傪埿埑偱偒傞偑丄偍偺傟偵岦偗偨傜攋柵傪彽偔丅峲嬻婡傕傑偨嫮偝乮懍偝乯亖暥柧偺徾挜偱偁偭偨偑丄偍偺傟偵岦偐偭偨偲偒攋柵偵偮側偑偭偨丅
丂偁傜備傞傕偺偵偼椉媊惈偑偁傞丅偄偄偙偲偽偐傝偺傕偺側偳側偄丅実懷揹榖偼曋棙偩偑丄巊偄曽偵傛偭偰偼嫢婍偵憗曄傢傝偡傞丅尨敪偼嬃偔傋偒僄僱儖僊乕傪惗傒弌偡偑丄帠屘偑偁傟偽攋柵偑懸偭偰偄傞丅偡偽傜偟偄僥僋僲儘僕乕偼丄摨帪偵嫲傞傋偒晲婍偵憗曄傢傝偡傞丅偙傟偼偍偦傜偔塻棙側愇婍傪嶌偭偨恖椶偑丄偦偺摴嬶傪摨朎偵岦偗偨偲偒丄傕偺偡偛偄椡傪敪婗偡傞偙偲偵婥偯偄偰埲棃丄嫟捠偟偰偄傞偙偲偩傠偆丅
丂偙傟偐傜偺恖椶偺壽戣偼丄偄偐偵柵傃傑偱偺摴傪備傞傗偐偵曕傓偐偺堦揰偵偐偐偭偰偄傞偩傠偆丅乬墑柦乭偙偦偑壽戣偱偁傝丄偦偺偨傔偵偼丄偙傟傑偱攟偭偰偒偨壢妛媄弍偺偁傞晹暘傪抐擮偡傞偙偲偑媮傔傜傟傞偩傠偆丅傑偢偼乬妀暫婍乭乬尨敪乭傪抐擮偡傞偙偲丄偙傟偑僀儔僋傪峌寕偡傞慜偵傗傞傋偒壽戣偵偪偑偄側偄丅嶁杮棿堦偺乬旕愴乭偺巚憐偼丄恖椶偺崱屻偺壽戣偲偟偰揑妋偱偁傞丅乽朶椡乿乽椡乿傊偺抐擮偙偦偑丄怴偟偄抦宐傪惗傒弌偡偐傜偱偁傞丅偦偺偨傔偵偼丄傑偢悽奅偑懳榖偱偒傞傛偆側巇慻傒傪妋偐側傕偺偵偟偰偄偐側偔偰偼側傜側偄丅
丂乬俋丒侾侾乭埲崀丄巹偨偪恖椶偑惗偒墑傃偰偄偔偨傔偺曽朄偼丄乽椡乿偵偼側偄丄乽壢妛媄弍乿偵傕側偄丅偨偩丄乽椡乿傪抐擮偟丄乽壢妛媄弍乿偺偁傞晹暘傪抐擮偡傞寛抐偲塸抦偵偁傞丅崱丄巹偼偦偆巚偭偰偄傞丅
丂丂2002/9/8(Sun)丂亙杒偺崙偐傜廔復亜
丂廡枛丄乽杒偺崙偐傜2002堚尵乿傪娤傑偟偨丅姶摦偟偨偺偼嵟屻偵棳傟偨僥儘僢僾丅僉儍僗僩丄僗僞僢僼偑惎偺悢傎偳傕偄偰丄偙偺嶌昳偑戝惃偺恖乆偵傛偭偰巟偊傜傟偰偄傞偙偲傪夵傔偰抦傝傑偟偨丅乽2002堚尵乿偐傜搊応偟偨寢偪傖傫偙偲丄撪揷桳婭偺岲墘偵傕枺椆偝傟傑偟偨丅偙傟傑偱僇儔儕僆偺俠俵偟偐抦傜側偐偭偨偺偱偡偑丄撪揷桳婭偼慺惏傜偟偄偺堦尵偵恠偒傑偡丅偙傟傑偱杒偺崙偐傜傪巟偊偰偒偨暲傒偄傞柤桪偨偪偵堦曕傕堷偗傪偲偭偰偄側偄偲姶偠傑偟偨丅傛偔尒傞偲丄撪揷桳婭偼丄乽杒偺崙偐傜1987弶楒乿偱搊応偟偨傟偄偪傖傫偙偲丄墶嶳傔偖傒宯偱偁傝丄弮偼恻梋嬋愜偺枛丄弶楒偺恖偵偨偳傝偮偄偨偲偄偆尵偊傞偐傕偟傟傑偣傫丅
丂搑拞丄傇偮偔偝尵偭偰偄偨偙偲傕偁傝傑偟偨偑乮巹乯丄21擭娫偺僪儔儅偲偄偆偺偼尷傝側偔僗僑僀偲巚偄傑偡丅偐偮偰丄婥擄偟偄摗揷徣嶰偑乮巹偑戝偄偵懜宧偟偰偄傞巚憐壠偱偡偑乯丄崟斅屲榊偲偄偆恖暔偺憿宆偵偮偄偰丄戝偄側傞巀帿傪憲偭偰偄偨偙偲傪巚偄弌偟傑偡丅乽夣妝偺慡懱庡媊乿偲偄偆幮夛晽挭偵峈偄側偑傜崟斅屲榊偑曕偄偨偙偺21擭娫丄巹偼弮偲摨偠傛偆偵丄偄傗弮偲偼慡偔斀懳偵丄尰幚偲偐偗棧傟偨僗乕僷乕儅儞偵側偭偰偄偔崟斅屲榊偵乮崟斅屲榊偺憿宆偵乯斀敪傪偄偩偄偨偙偲傕偁傝傑偟偨丅偟偐偟丄嵟廔復丄懛偺夣傪揗垽偡傞杴梖側崟斅屲榊偵丄怱偐傜偄偲偍偟偝傪姶偠傑偟偨丅
丂乽杒偺崙偐傜乿偼丄崙柉揑側暥壔偺嵿嶻偩偲巚偄傑偡丅偙偆偟偨僪儔儅傪丄恖暔傪偳偺偔傜偄憿宆偱偒傞偺偐丄偦偟偰嫟桳偱偒傞偺偐丄偦偆偟偨帇揰偐傜崙偺朙偐偝傪寁傞丄偦傫側暔嵎偟偑偁偭偰傕偄偄偺偱偼側偄偐偲巚偄傑偡丅偁傝偑偲偆両丂乽杒偺崙偐傜乿
丂丂2002/9/4(Wed)丂亙椃偼摴楢傟亜
丂俋寧侾擔偐傜係擔傑偱偺杒奀摴丒旤塴挰崌廻偐傜偪傚偆偳崱婣偭偰偒傑偟偨丅傒偭偪傝擾嶌嬈傪偟偰丄娤岝傕偟偰丄栭傕懱堢娰偱塣摦傪偟丄堸傓偲偄偆乬梸挘傝乭崌廻偱偟偨偑丄堦恖偺棧扙幰傕弌偡偙偲側偔丄傎偲傫偳僩儔僽儖傕側偔丄婣娨偡傞偙偲偑偱偒丄儂僢偲偟偨偺堦尵偱偡丅乮傑偩婣戭拞偺妛惗傕偄傞偲巚偆偺偱丄埨怱偡傞偺偼憗偄偱偡偑乯
丂堦擔偵悢廫夞偺僩儔僽儖傪宱尡偟丄偦偺夁敿悢偑巹偺寁夋惈偺側偝偵婲場偟偰偄偨慜夞偺杒奀摴崌廻偐傜俁擭丄崱夞偺崌廻傪徫婄偱廔偊傞偙偲偑偱偒偨偙偲偼丄昅愩偵恠偔偟偑偨偄婌傃偱偁傝傑偟偨丅偛懚偠偺傛偆偵丄巹偼帺暘彑庤側恖娫偱丄婥偺岦偔傑傑丄晽偺悂偔傑傑丄堦恖椃側傜乽僩儔僽儖傕僩儔儀儖傛乿偲偽偐傝偵儂僀儂僀偲捒摴拞傪偔傝傂傠偘傑偡偑丄廤抍傪傑偲傔傞偙偲偼戝偺嬯庤偲棃偰偄傑偡丅偙偺惈奿偺寚娮偑儌儘偵弌偨偺偑俁擭慜偺杒奀摴崌廻丅偦偟偰丄偙偺俁擭娫丄帺暘偺寚娮傪曗偆偵偼偳偆偟偨傜偄偄偐丄偄傠偄傠帋峴嶖岆偟側偑傜惗偒偰偒傑偟偨丅
丂偦偟偰丄偙偺壞丄嵞傃杒奀摴傊丅巹偺寚娮傪捈偡尞偼丄乽懳榖乿偵偁傞偲偄偆偙偲偱丄撈抐愱峴傪怲傒丄妛惗偲乽懳榖乿傪偟側偑傜崌廻傪嶌偭偰偄偙偆偲峫偊傑偟偨丅偦偺寢壥偑偙偺崌廻偱偟偨丅巇帠偵廇偒丄堦偮偺偙偲傪惉偟悑偘傞偙偲偑偙傫側偵傕擄偟偄偺偐偲偄偆偙偲傪巚偄抦傝丄偦偟偰堦偮偺暻傪妛惗偨偪偲偲傕偵撍攋偟傑偟偨丅師偵傕暻偼懸偪庴偗偰偄傑偡丅偟偐偟丄暻傪乬偲傕偵乭忔傝墇偊偨偲偄偆懱尡偼丄偨偟偐側姶妎偲偟偰恎懱偺拞偵懅偯偄偰偄傑偡丅巹偼丄崱擭偺妛惗偨偪偲偲傕偵丄偦偟偰俁擭慜偺妛惗偨偪偲偲傕偵丄暻傪忔傝墇偊偨偺偩偲巚偭偰偄傑偡丅
丂恖惗偲偄偆椃傕傑偨丄婔懡偺嶳乆傪乬偲傕偵乭忔傝墇偊偰偄偔傕偺偱偼側偄偐偲丄峫偊偰偄傑偡丅椃偼摴楢傟丄悽偼忣偗丅偦偟偰丄師偺椃傊丅廔傢傝側偒椃丅
丂丂2002/8/30(Fri)丂亙杒偺崙偐傜亜
丂俋寧侾擔偐傜僛儈崌廻偱杒奀摴丒旤塴挰傪朘偹傞梊掕偱偁傞丅擾嬈懱尡偲擾壠偺曽乆偲偺岎棳偑庡側栚揑偱偁傞偑丄晉椙栰偑嬤偄偲偄偆偙偲傕偁偭偰丄亀杒偺崙偐傜亁偺儘働抧傪朘偹偰傒傛偆偲偄偆榖偵側偭偨丅亀杒偺崙偐傜亁偺儘働抧傪朘偹傞偺偱偁傟偽丄僪儔儅傪偼偠傔偐傜娤偰偄偙偆偲偄偆偙偲偱丄壗尙偐偺價僨僆壆傪朘偹曕偄偨偑丄尒帠偵戄偟弌偟拞偱偁傞丅
丂亀杒偺崙偐傜丂乣堚尵乣亁偺曻塮傪慜偵丄摨偠傛偆偵價僨僆傪娤偰偍偙偆偲偄偆恖偨偪偑懡偄偺偩傠偆丅亀杒偺崙偐傜亁偺儘働抧傪朘偹偰傒傛偆偲巚偭偨偲偒偼丄偦傠偦傠傎偲傏傝傕惲傔偨偩傠偆偐傜偄偭偪傚偆峴偭偰傒傞偐偲偄偆偮傕傝偩偭偨偑丄恾傜偢傕棳峴偵忔傞偙偲偲側偭偨丅偦傟偱傕壗偲偐價僨僆傪擖庤偟偰丄栭偵側傞偲亀杒偺崙偐傜亁偺悽奅偵傂偨偭偰偄傞丅
丂1981擭偺亀杒偺崙偐傜亁偼傗偭傁傝偄偄丅愨柇側巕栶偵宐傑傟偨偲偄偆偙偲傕偁傞丅弮傕丄寀傕丄媰偐偣傞偟丄懚嵼姶偑偁傞丅巕偳傕偺怱偑昤偗偰偄傞丅偦偟偰丄巕偳傕偼恊偩偗偱側偔丄偨偔偝傫偺戝恖偵尒庣傜傟側偑傜丄偨偔偝傫偺戝恖偐傜梴暘傪媧偄庢傝丄惉挿偟偰偄偔偺偩偲偄偆偙偲偵夵傔偰婥偯偐偝傟傞丅
丂亀杒偺崙偐傜亁偺暔岅偱傕偦偆偩偑丄巕偳傕偼戝恖偺偙偲偽傪暦偄偰惗偒偰偄傞傢偗偱偼側偄丅偙偲偽偺岦偙偆偵偁傞戝恖偺恖娫偲偟偰偺偁傝傛偆傪挳偄偰偄傞丅巹傕傑偨丄巕偳傕偩偭偨崰丄暦偒暘偗偺傛偄乮巹偺尵偆偙偲偵巀摨偟偰偔傟傞乯戝恖傛傝傓偟傠丄棫偪偼偩偐偭偰偔傞偑偙偪傜傪巕偳傕埖偄偟側偄戝恖傪岲傑偟偔巚偭偨偙偲傪巚偄弌偡丅堦弿偵亀杒偺崙偐傜亁傪娤側偑傜丄巹偑乽巕偳傕偼偮傜偄傛丄戝恖偵娵傔崬傑傟傞傕傫側乿偲尵偆偲丄摨嫃恖偼乽巕偳傕偩偐傜偩傑偝傟傞偙偲偑偁傞丅偱傕丄巕偳傕偩偐傜偩傑偝傟側偄偙偲傕偁傞乿偲尵偭偨丅乽側傞傎偳乿偲巚偭偨丅巕偳傕偼宱尡偑敄偄偑丄惗偒傞姩偼傑偩憠偣嵶偭偰偄側偄丅
丂旤塴崌廻偼怴偟偄帋傒偱偁傞丅帠屘偺側偄傛偆偵婩傝丄婥傪偮偗偰峴偭偰偙傛偆偲巚偆丅僽儔僂儞娗偺拞偺亀杒偺崙偐傜亁偲偼傑偨堘偆乽杒偺崙乿偑丄巹偨偪偺慜偵懸偪庴偗偰偄傞偙偲偩傠偆丅
丂丂2002/8/29(Thu)丂亙寵傢傟傞棟桼亜
丂偦偺愄丄亀垽偝傟傞棟桼亁偲偄偆杮偑弌偰儀僗僩僙儔乕偲側偭偨偑乮挊幰偑棧崶偡傞偲偄偆僆僠傕偮偄偨乯丄傾儊儕僇偑乽寵傢傟傞棟桼乿偵偮偄偰婥偵偟巒傔偰偄傞傜偟偄丅
丂枅擔怴暦偺婰帠偵傛傞偲師偺傛偆偵婰偝傟偰偄傞丅
丂乽暷崙柋徣偺僶僂僠儍乕曬摴姱偼俀俉擔丄悽奅偵峀偑傞斀暷庡媊偺幚懺偲尨場傪扵傞偨傔丄俋寧俆丄俇擔偵暷崙撪奜偺愱栧壠栺俀侽恖傪廤傔偰尋媶夛媍傪奐偔偲敪昞偟偨丅暷惌晎摉嬊幰栺俆侽恖偑朤挳偟丄奜岎惌嶔偵斀塮偝偣傞偲偄偆丅偙偺偲偙傠丄乽挻戝崙偺恎彑庤乿偲旕擄偝傟傞偙偲偑栚棫偮暷崙偩偑丄乽寵傢傟偰偄傞乿偲偄偆帺妎傗擸傒傕偁傞傛偆偩丅乿
丂恎挿190僙儞僠偺柍憃偺栆幰傕擸傫偱偄傞傜偟偄丅傑偨丄師偺傛偆偵傕婰偝傟偰偄傞丅
丂乽曬摴姱偼乽偄偔偮偐偺抧堟偱恖乆偑暷崙傪寵偭偰偄傞尨場丄棟桼乿傪棟夝偡傞偙偲偺昁梫惈傪巜揈丅摉嬊幰偑夛媍傪捈愙朤挳偡傞偩偗偱側偔丄忣曬挷嵏嬊偑夛媍屻偵傑偲傔傞暘愅傕斀暷庡媊傊偺懳嶔偺庤妡偐傝偵側傞偲岅傝丄摿偵峀曬晹栧側偳偱栶棫偮偩傠偆偲婜懸傪帵偟偰偄傞丅乿
丂偍偺傟傪尒偮傔捈偦偆偲偡傞偲偙傠偑壗偲傕傾儊儕僇傜偟偄偲尵偊傞偑丄乽寵傢傟偰偄傞偙偲乿偼乽峀曬晹栧乿偺僀儊乕僕愴棯偱偳偆偙偆偡傞偙偲偱傕側偄偩傠偆丅傾儊儕僇偑乽寵傢傟傞棟桼乿傪暘愅偡傞偨傔偵丄暿偵愱栧壠傪俀侽恖傕廤傔傞昁梫傕側偄丅偨偩丄旐奞栂憐偺壛奞幰偲偄偆帺屓憸傪庴偗巭傔傟偽嵪傓偙偲偩丅
丂悽奅娐嫬夛媍偵弌惾偟丄擇巁壔扽慺偺攔弌検傪庢傝寛傔偨嫗搒愰尵傪斸弝偟丄僷儗僗僠僫偺榓暯偵恠椡偟丄僀儔僋晲椡峌寕傪巚偄偲偳傑傞側傜偽丄偄偮偱傕傾儊儕僇傪巟帩偡傞弨旛偼偱偒偰偄傞丅偁側偨偼巚偭偰偄傞埲忋偵嫮偄偺偩丅偁側偨偺偔偟傖傒偱庛偄幰偨偪偼奆悂偒旘傫偱偟傑偆偺偩丅偦偺偙偲傪帺妎偟偰偄偨偩偒偨偄丅
丂丂2002/8/28(Wed)丂亙僠儍僢僾儕儞亜
丂婣崙偟偰偐傜僠儍僢僾儕儞偺塮夋偵柌拞偵側偭偰偄傞丅亀將偺惗妶亁亀儌僟儞僞僀儉僘亁側偳丄庛幰丒昻幰偵壏偐偄傑側偞偟傪拲偖僠儍僢僾儕儞偺塮夋偼丄嶦敯偲偟偨帪戙偵偁偭偰怱傪榓傑偣偰偔傟傞丅乽揇朹偵傕嶰暘偺摴棟乿偲偼丄擔杮偺尒帠側偙偲傢偞偱偁傞偑丄扤偩偭偰傢偢偐側摴棟偵偡偑偭偰惗偒偰偄傞丅傢偢偐側摴棟偙偦偑恖娫偑恖娫偱偁傞強埲偱傕偁傠偆丅偩偐傜丄偦偺傢偢偐側摴棟傪斲掕偝傟傞側傜偽丄夊傪傓偔偟偐側偔側傞丅揇朹偺摴棟傪儂僀儂僀擣傔傛偆側傫偰尵偆婥偼栄摢側偄偑丄偦偺傢偢偐側摴棟偐傜揇朹偑帺傜偺椙怱偵婥偯偒丄傑偨揇朹埲奜偺恖傕揇朹傕帺暘傕摨偠恖娫偱偁傞偙偲偵婥偯偗傞傛偆側娭學惈偼戝愗偵偡傋偒偙偲偱偼側偄偩傠偆偐丅
丂僐儈儏僯働乕僔儑儞傪朶椡偵傛偭偰愗傞偙偲丄偙傟偼旐奞幰偵嫰偊傪梌偊傞丅偦偺偨傔偵丄朶椡傪峴偆懁偑嫮幰偱偁傞偲巚傢傟懕偗偰偒偨丅偨偟偐偵丄僐儈儏僯働乕僔儑儞傪朶椡偵傛偭偰愗傞偙偲偼丄傛傝尃椡偺偁傞懁偺傒偑傕偮摿尃偱偁傞丅堦斒偵丄巕偳傕偼戝恖偵懳偟偰丄僐儈儏僯働乕僔儑儞傪朶椡偵傛偭偰愗傞偙偲偼擄偟偄丅偟偐偟丄戝恖偑巕偳傕偵懳偟偰丄僐儈儏僯働乕僔儑儞傪朶椡偵傛偭偰愗傞偺偼丄壠晝挿惂偺壓偱偼偟偽偟偽峴傢傟偰偒偨丅偩偑丄崱丄俢倁側偳偺栤戣偑柧傜偐偵偝傟傞拞偱丄朶椡偵埶懚偡傞幰偺庛偝偵岝偑偁偰傜傟傛偆偲偟偰偄傞丅
丂屄恖偺栤戣偲摨偠偙偲偑崙傗惌帯慻怐偺儗儀儖偱傕尵偊傞偩傠偆丅僐儈儏僯働乕僔儑儞傪朶椡偵傛偭偰抐偪愗傞偙偲偼丄斊嵾偱偁傞丅僐儈儏僯働乕僔儑儞傊偺搘椡傪掹傔偨偲偒丄偦偙偼傕偆愴憟傊偺堦棦捤偱偁傞偲偄偊傞丅
丂恖椶偑恖椶傪柵傏偟恠偔偡偩偗偺朶椡乮亖暫婍乯傪庤偵偟偨偲偒丄朶椡偼丄恖椶偺壜擻惈傪峀偘傞庤抜偱偼側偔丄恖椶偵偲偭偰偺嵟戝偺揋偵側偭偨偼偢偱偁傞丅偲偙傠偑丄僀儔僋峌寕偵岦偐偆尰嵼偺傾儊儕僇偺巔偼丄恖椶偑偙傟傑偱攟偭偰偒偨塩堊傪戜柍偟偵偡傞偐偺傛偆偱偁傞丅戞嶰幰偐傜尒傟偽丄傾儊儕僇偼190僙儞僠偺戝抝偺傛偆偵嫮偔丄僷儞僠傪嬺傜偭偨傜摢偑悂偭旘傃偦偆側傎偳偺惁傒偑偁傞丅堦曽偺僀儔僋偼丄偦偙傜偺埆僈僉偵偡偓偢丄偱偒傞偙偲偲偄偊偽憢僈儔僗偵愇傪搳偘偮偗傞偔傜偄丄偺傛偆偵巚偊傞丅偳偙偵傕丄傾儊儕僇偑婄怓傪曄偊偰僀儔僋傪峌寕偟側偗傟偽側傜側偄棟桼側偳尒偁偨傜側偄傛偆偵巚偊傞丅
丂傾儊儕僇偑朶椡偵埶懚偡傟偽偡傞傎偳丄巹偨偪偼傾儊儕僇偺俢倁抝揑庛偝傪尒傞偙偲偵側傞偩傠偆丅埶懚徢偐傜棫偪捈傞偵偼丄婥偯偒偑昁梫偱偁傞丅偟偽偟偽婥偯偒偼偳傫掙宱尡偵傛偭偰傕偨傜偝傟傞偲偄偆丅偟偐偟丄抧媴偼丄傾儊儕僇偺偳傫掙宱尡傑偱懸偭偰偄傜傟側偄偩傠偆丅偦傟偵儀僩僫儉偱傾儊儕僇偼偳傫掙傪尒偨偼偢偱偼側偄偐丅
丂愴憟偵岦偐偆帪婜丄偦偟偰椻愴偺帪婜丄傾儊儕僇偼婌寑墹僠儍僢僾儕儞傪寵偄丄敆奞偟偨丅僠儍僢僾儕儞偺塮夋偵偼丄暋娽嬀偑旛偊傜傟偰偄偰丄偦偙偐傜偼懡條側傕偺偺尒曽偑壜擻偱偁偭偨偐傜偱偁傞丅傾儊儕僇偺惓媊偲僠儍僢僾儕儞偺塮夋偼憡梕傟側偄傕偺偩偭偨丅偦偟偰丄崱丄扨娽嬀偱悽奅傪暍偆偙偲傪堄恾偟偰偄傞僽僢僔儏戝摑椞偵丄僠儍僢僾儕儞偺塮夋傪曺偘偨偄丅乮偝偝偘偮偮両乯
丂丂2002/8/27(Tue)丂亙岎捠帠屘亜
丂嶐擔偵堷偒懕偒丄岎捠帠屘娭楢偺僯儏乕僗偺榖戣丅
丂杮擔偺枅擔怴暦偺僯儏乕僗偵傛傞偲丄擔杮偺岎捠帠屘偵偼師偺傛偆側摿挜偑偁傞偲偄偆丅
丂乽寈嶡挕偵傛傞偲丄擔杮偱偼岎捠帠屘偺巰幰悢偺栺係侾亾偑曕峴幰傗帺揮幵棙梡幰丅暷崙栺侾俁亾丄僼儔儞僗栺侾係亾丄僀僊儕僗栺俀俋亾偵斾傋奿抜偵妱崌偑崅偄丅摿偵曕峴幰偺巰幰偺敿悢埲忋偑帺戭嬤偔偱帠屘偵憳偭偰偄偨丅乿
丂偮傑傝丄擔杮偱偼丄帺摦幵偑曕峴幰傗帺揮幵棙梡幰傪偼偹傞帠屘偺妱崌偑丄彅奜崙偲偔傜傋偰偼傞偐偵崅偄偲偄偆偺偱偁傞丅偮傑傝丄帺摦幵懳帺摦幵偲偄偆懳摍偺娭學偱帠屘偑婲偙偭偰偄傞傢偗偱偼側偔丄帺摦幵懳曕峴幰丒帺揮幵偲偄偆晄嬒峵側椡娭學偱帠屘偑婲偒偰偄傞偲偄偆偙偲偵側傞丅
丂偙傟偵懳偟偰丄崙搚岎捠徣偲寈嶡挕偱偼丄師偺傛偆側懳墳偵拝庤偡傞偲偄偆丅
丂乽偙偺偨傔丄椉徣挕偼乽幵拞怱乿偐傜乽恖拞怱乿偺摴楬娐嫬傪偮偔傞偨傔丄恖恎帠屘偺敪惗妱崌偑崅偄廧戭抧傗彜嬈抧偺栺侾乣俀暯曽僉儘傪摨僄儕傾偲偟偰巜掕偡傞丅僄儕傾撪偱偼丄楬懁懷傪奼暆偟丄嵟崅懍搙傪婯惂偡傞傎偐丄曕峴幰偲幵椉偺捠峴傪帪娫揑偵暘棧偡傞乽曕幵暘棧幃怣崋乿丄曕峴幰傪姶抦偟偨応崌偼墶抐曕摴偺惵怣崋帪娫傪墑挿偡傞乽曕峴幰姶墳怣崋婡乿側偳偺惍旛傪恑傔傞丅乿
丂偙偆偟偨庢傝慻傒偼丄偤傂偲傕傗偭偰偄偨偩偒偨偄丅巹偨偪偑巟暐偭偰偄傞惻嬥偼丄壗傛傝傕巹偨偪巗柉偺埨慡傪庣傝丄偦偺惗妶偺幙偺岦忋偺偨傔偵巊傢傟傞傋偒偱偁傞丅婰帠偵偼乽恖恎帠屘偺俀妱嶍尭傪栚巜偡乿偲偁傞偑丄偙偆偟偨偲偙傠偼墦椂偣偢偵乽俉妱乿嶍尭傪栚巜偟偰傎偟偄丅
丂曄傢傞偨傔偵昁梫側偙偲偼丄傗傝傗偡偄偲偙傠偐傜拝庤偡傞偺偱偼側偔丄傗傜偹偽側傜側偄偲偙傠偵拝庤偡傞偙偲偩偲巚偆丅奆偝傫傕丄偡偱偵埨慡偦偆側摴傪壗搙傕傎偠偔傝曉偡堦曽偱丄婋尟側摴傪曻偭偰偄傞岝宨傪偛棗偵側傜傟偨偙偲偑偁傞偩傠偆丅傑偨尒捠偟偺偄偄丄彮偟僗僺乕僪傪忋偘偨偔側傞丄偲偰傕帠屘偺婲偙傝偦偆偵側偄摴楬偱丄僱僘儈庢傝偵憳傢傟偨偙偲傕偁傞偐傕偟傟側偄丅偦偆偟偨摴楬偼尒捠偟偑傛偄忋偵丄搒崌傛偔寈嶡偑塀傟傞偪傚偭偲偟偨応強偑偁偭偨傝偡傞傕偺偩丅偮傑傝丄庢傝掲傑傝傪傗傝傗偡偄摴楬偱偁傞丅偙偺堦曽偱丄偙偙偱僗僺乕僪傪忋偘偨傜婋側偄偧偲巚傢傟傞傛偆側摴楬偱丄庢傝掲傑傝傪尒偐偗傞偙偲偼柵懡偵側偄丅
丂傗傝傗偡偄偲偙傠偐傜偱偼側偔丄傗傞傋偒偲偙傠偐傜拝庤偡傞丅傗傞傋偒偲偙傠乮昁梫側偙偲乯傪堦斣抦偭偰偄傞偺偼丄儐乕僓乕偱偁傝丄巗柉偱偁傞丅巹偼丄枅擔丄帺摦幵捠嬑傪偡傞傛偆偵側偭偰偐傜丄偳偙偺摴楬偑偳偺傛偆偵婋尟偱丄偳偙偺怣崋婡偺帪娫愝掕偑偳偺傛偆偵廰懾傪惗傒弌偟偰偄傞偺偐丄嫲傠偟偔傢偐傞傛偆偵側偭偨丅偒偭偲丄戭媫曋攝払側偳偱抧堟傪傑傢偭偰偄傞恖偨偪偼丄傕偺偡偛偄検偺桳梡側忣曬傪僗僩僢僋偟偰偄傞偙偲偩傠偆丅偦偺堦曽偱丄偄偔傜桳擻側摴楬愝寁扴摉幰偱偁偭偰傕丄偡傋偰傪尒墇偟偰揔愗側愝寁傪偡傞偙偲偼摓掙柍棟偩偲傕巚偭偨丅摴楬傕惗偒暔偱偁傝丄婘忋偺寁嶼偩偗偱偼偮偠偮傑偑崌偆傢偗偑側偄偐傜偱偁傞丅愝寁偟偰丄巤岺偡傞傑偱偼傑偩戞堦抜奒丄偦傟偐傜幚嵺偵塣梡偟側偑傜夵慞偟懕偗偰偄偐側偔偰偼側傜側偄丅屻幰偺傎偆偑偢偭偲戝愗側偙偲偱偁傞傛偆偵巚傢傟傞偺偩丅
丂傕偪傠傫丄偙偺榖偼丄帺暘偵傕曉偭偰偔傞偙偲偱偁傞丅巹偼丄帺暘偑傗傟傞妏搙乮亖傗傝傗偡偄偲偙傠乯偐傜庼嬈傪愝寁偡傞丅偟偐偟丄傗傞傋偒偲偙傠乮昁梫側偙偲乯傪堦斣抦偭偰偄傞偺偼丄妛傃庤偱偁傞丅妛傃庤偺宱尡偲婥偯偒傪偡偔偄偲傝側偑傜丄巹偼帺暘偺庼嬈偵偮偄偰偺夵慞傪峴偆丅巹偺椡検偺懌傝側偝偐傜乮亖傾僫儘僕乕偲偟偰偼帒嬥晄懌乯丄偡傋偰偺堄尒傪斀塮偝偣傞偙偲偼偱偒側偄偩傠偆丅傑偨丄妛傃庤偺堄尒偑岆夝偵婎偯偄偰偄傞偙偲偩偭偰偁傞偩傠偆丅偦偆偟偨偲偒偵偼丄愱栧壠偲偟偰偺尒幆傪傕偲偵丄妛傃庤偵愢柧偡傞愑擟傕偁傞偩傠偆丅偄偢傟偵偣傛丄愱栧壠偑抦傪撈愯偟丄戝廜偼偦傟偵廬偊偲偄偆帪戙偼廔傢傝傪崘偘偰偄傞偲丄巹偼巚偆偺偱偁傞丅
丂娞墛偱惗柦偺婋婡偵棫偭偨抦恖偑偄偨丅斵偼熡恎偺椡偱偝傑偞傑側椕朄傪扵偟夞傝丄偮偄偵娞墛傪姰帯偝偣傞偙偲偵惉岟偟偨偲偄偆丅偙傟偼偨傑偨傑偩偭偨偐傕偟傟側偄丅偟偐偟丄帺暘偺惗柦傪庣傝偨偄偲偄偆婥帩偪丄偁傞偄偼壠懓偺惗柦傪庣傝偨偄偲偄偆婥帩偪丄偙傟偼壗偵傕憹偟偰嫮偄傕偺偩丅偙偺嫮偄婥帩偪偑丄偟偽偟偽惓摎偵扝傝拝偔偲偄偆偺偼丄摉慠峫偊傜傟傞偙偱偁傞丅嵟嬤丄堛椕儈僗偑懕弌偟偰偄傞丅偙傟傕愱栧壠偲偟偰偺橖傝偑丄摉帠幰偺嫮偄婥帩偪傪偍傠偦偐偵偟偨寢壥偱偼側偄偩傠偆偐丅偙傟偐傜偺愱栧壠偼丄嫵慶乮僇儕僗儅乯偱偼側偔丄偮側偓庤乮僐乕僨傿僱乕僞乕乯偲偟偰偦偺椡傪敪婗偡傞偙偲偑媮傔傜傟偰偄傞偺偱偼側偄偩傠偆偐丅傕偼傗乽柉偼嬸偐偵曐偰乿偱偼丄幮夛偵枹棃偼側偄丅
丂丂2002/8/26(Mon)丂亙婋尟塣揮亜
丂悽偺拞丄擺摼偺偄偐側偄偙偲偼偄傠偄傠偁傞偗傟偳傕丄婥偵側偭偰偄傞偺偑岎捠帠屘娭楢偺僯儏乕僗偱偁傞丅
丂悢擔慜丄師偺傛偆側僯儏乕僗偑棳傟偨丅
乽惷壀導寈搰揷彁偼俀侾擔丄摨導搰揷巗杮捠俇丄塣揮庤丄倄梕媈幰乮俁侾乯傪嶦恖枹悑偺媈偄偱戇曔偟偨丅挷傋偱偼丄倄梕媈幰偼摨擔屵慜俆帪敿偛傠丄摨巗憡夑偺導摴偱戝宆僟儞僾僇乕乮栺侾俀僩儞乯傪帪懍俉侽僉儘偱塣揮拞丄屻懕幵偑偄傞偺傪抦傝側偑傜媫僽儗乕僉傪偐偗丄屻懕偺摨巗恄嵗丄僷僠儞僐揦堳丄俽偝傫乮俀侽乯偺儚僑儞幵傪帺暘偺僟儞僾偵捛撍偝偣偨媈偄丅俽偝傫偼擼嵙彎側偳偱堄幆晄柧偺廳懱丅挷傋偵懳偟丄倄梕媈幰偼乽俽偝傫偑帠屘尰応偺悢僉儘庤慜偐傜捛偄墇偦偆偲僷僢僔儞僌傗偁偍傝傪孞傝曉偟偰偄偨偺偱傗偭偨乿側偳偲嫙弎丅摨彁偼丄僟儞僾偵捛撍偡傟偽幵偺塣揮幰偑巰偸偐傕偟傟側偄偲摨梕媈幰偑擣幆偟偰偄偨偲傒偰丄嶦恖枹悑傪揔梡偟偨丅帠屘屻丄倄梕媈幰偼乽帠屘傪婲偙偟丄侾恖偗偑恖偑偄傞乿偲帺暘偱侾侾侽斣偟偨丅尰応偼暆俇儊乕僩儖偺曅懁侾幵慄偱丄捛偄墇偟壜擻側捈慄摴楬丅乮枅擔怴暦乯乿
丂偙偆偄偭偰偼壗偩偑丄倄梕媈幰偺婥帩偪偼傛偔傢偐傞丅乽曅懁侾幵慄偺捛偄墇偟壜擻側捈慄摴楬乿偱丄乽僷僢僔儞僌傗偁偍傝傪孞傝曉乿偝傟偰偼丄恎偺婋尟傕姶偠傞偩傠偆偟丄乽傆偞偗傞側乿偲偄偆婥帩偪偑惗傑傟傞偺偼丄偟偛偔摉慠側偙偲偱偁傞丅偦偟偰丄僽儗乕僉傪摜傫偩偲偙傠丄屻傠偺幵偼巭傑傟偢偵寖撍丅偙偺婰帠傪撉傓偲丄倄梕媈幰偼丄帺傜侾侾侽斣偟偰丄揔愗側傾僼僞働傾乕傪偟丄庢傝挷傋偵懳偟偰惓捈偵宱堒傪榖偟偰偄傞偙偲偑揱傢偭偰偔傞丅偲偙傠偑丄偙傟偵懳偡傞寈嶡偺張嬾偼丄壗偲乽嶦恖枹悑乿偱偁傞丅庢傝挷傋偱倄梕媈幰偼堦弖乽巰傫偱偟傑偊乿偲巚偭偨偲偐楻傜偟偨偺偐傕偟傟側偄丅偩偑乽巰傫偱偟傑偊乿偲巚偆偙偲偲乽嶦恖乿偺娫偵偼戝偒側奐偒偑偁傞偩傠偆丅偦偟偰丄偄偮傕偼壛奞幰偵戝娒偵巚偊傞寈嶡偑丄旐奞幰偑帠審傪偒偭偐偗傪偮偔偭偨偲巚傢傟傞偙偺帠審偱丄側偤偩偐乽嶦恖枹悑乿偲偄偆嵟傕廳偄嵾傪揔梡偟偰偄傞丅
丂懕偄偰丄杮擔偺僯儏乕僗偱偁傞丅
丂乽撊栘導寈撊栘彁偼俀俆擔丄棎朶側塣揮傪拲堄偝傟偨偙偲偵暊傪棫偰曕峴幰俁恖傪偼偹偨偲偟偰丄摨導撊栘巗戝媨挰丄夛幮堳俽梕媈幰乮俀俇乯傪彎奞偺媈偄偱嬞媫戇曔偟偨丅挷傋偵傛傞偲丄俽梕媈幰偼摨擔屵屻俈帪俁侽暘偛傠丄摨巗戝媨挰偺巗摴偱忔梡幵傪塣揮拞丄慜偐傜曕偄偰偒偨抝惈夛幮堳乮俀俋乯偵乽婋側偄側乿偲偡傟堘偄偞傑偵戝惡偱尵傢傟偨偙偲偵棫暊丅幵傪屻戅偝偣偰丄抝惈偲丄堦弿偵曕偄偰偄偨嵢乮俀俆乯丄巓乮俀俉乯偺俁恖傪偼偹丄偦傟偧傟偵係廡娫偐傜俀廡娫偺偗偑傪晧傢偣偨媈偄丅尰応偼曕摴偺側偄暆栺俇儊乕僩儖偺摴楬丅抝惈傜偼嬤偔偺嵳傝偵峴偔搑拞偩偭偨丅乮撉攧怴暦乯乿
丂嵳傝偵峴偔搑拞偺摴楬偱丄恎偺婋尟傪姶偠傞傛偆側棎朶塣揮傪偝傟偨偲偒丄堦尵拲堄偡傞偖傜偄丄恖娫偲偟偰摉偨傝慜偺偙偲偩傠偆偟丄偄傗傓偟傠巗柉偲偟偰傗傞傋偒偙偲偩偲偄偊傞偩傠偆丅幚嵺丄巹偼丄嫹偄摴偱偺帺摦幵偺棎朶塣揮偵偼丄偟偽偟偽乽婋側偄側乿偱偼嵪傑側偄偖傜偄偺偒偮偄拲堄傪孞傝曉偟偰偄傞丅帺揮幵俀恖忔傝傪嫃忎崅偵拲堄偡傞堦曽偱丄帺摦幵偺棎朶塣揮偵拲堄偟偨偙偲傪偐偮偰堦搙傕尒偨偙偲偺側偄寈嶡偺戙傢傝偵丅偲偙傠偑丄偙偺僯儏乕僗偱偼丄乽婋側偄乿塣揮傪偟偰丄乽婋側偄側乿偲尵傢傟偨偙偲偵暜寖偟偨俽梕媈幰偑丄側傫偲俁恖傪偼偹傞偲偄偆朶嫇偵弌偰偄傞偺偱偁傞丅抝惈夛幮堳偨偪偼丄偳傫側偵偐嫲晐傪姶偠偨偙偲偩傠偆丅惗偒偨怱抧偼偟側偐偭偨偺偱偼側偄偐丅偲偙傠偑丄偙傟偵懳偡傞寈嶡偺張嬾偼丄壗偲乽彎奞嵾乿偱偁傞丅妋偐乽彎奞嵾乿偲偼丄奨妏偱堦敪墸傜傟傞偺偲摨偠嵾偱偼側偄偩傠偆偐丅
丂幵偱恖傪鐎偙偆偲偟丄幚峴偡傟偽丄偙傟偼柧傜偐偵乽嶦恖枹悑乿偱偁傞丅揝偺夠偱丄惗恎偺恖娫傪廝偆偺偱偁傞偐傜丅巹偼偼偭偒傝偄偭偰擔杮幮夛偱惗偒傞偙偲偑晐偄丅儅僫乕偺埆偄恖娫偵懳偟偰偪傚偭偲拲堄偡傟偽丄偄偮嶦偝傟偰傕偍偐偟偔側偄傛偆側幮夛偱偁傞偐傜偩丅偦偟偰丄偦偆傗偭偰嶦偝傟偰傕丄柧傜偐偵嶦偝傟懝側巇慻傒偵側偭偰偄傞幮夛偱偁傞偐傜偩丅偙偆偟偨幮夛傪偮偔偭偰偄傞偺偼丄巗柉偺埨慡傪庣傞偨傔偱偼側偔丄崙壠偺儊儞僣傪庣傞偨傔偵偁傞乬朄偺斣恖乭偨偪偺巇慻傒側偺偱偼側偄偐偲巚偆丅
丂幵偱埿奷偡傞偙偲偼丄廳戝側斊嵾偱偁傞丅埿奷偝傟傞懁偑庣傜傟側偔偰偼側傜側偄偟丄埿奷偡傞懁偼尩敱傪庴偗側偔偰偼側傜側偄丅偙偆偟偨摉偨傝慜偺偙偲偡傜側偟摼側偄幮夛偵偁偭偰丄偳偆傗偭偰巕偳傕偨偪傪惓偟偔堢偰偨傜偄偄偺偐丄巹偵偼栄摢傢偐傜側偄丅
丂丂2002/8/25(Sun)丂亙帪嵎儃働亜
丂儓乕儘僢僷偵岦偐偭偰弌敪偟偨偺偼丄俉寧俇擔丒擔杮帪娫侾侾帪敿丅僼儔儞僋僼儖僩嬻峘偵摓拝偟偨偺偼丄摨擔丒尰抧帪娫侾俇帪敿偱偟偨丅帪嵎偑俈帪娫偁傝傑偡偺偱丄擔杮帪娫偱偼俀俁帪敿偲偄偆偙偲偵側傝傑偡丅側傫傗偐傫傗偁偭偰丄儂僥儖偵拝偄偨偺偼丄侾俋帪偖傜偄丅擔杮帪娫偱偼恀栭拞偺俀帪崰偱偡丅挬宆恖娫偵偼偮傜偄堦擔偩偭偨傛偆偱偡偑丄栭宆恖娫偺巹偵偲偭偰偼丄傛偆傗偔尦婥偑弌巒傔傞偲偄偭偨姶偠偱丄偦傟偐傜僼儔儞僋僼儖僩偺奨傪嶶嶔丄僆乕僾儞僇僼僃偱峠拑偲働乕僉傪枴傢偄偛偒偘傫偱偟偨丅儂僥儖偵栠偭偰俀俀帪崰乮儓乕儘僢僷偼栭侾侽帪嬤偔傑偱柧傞偄偺偱偡乯偵廇怮丅擔杮帪娫偱偼柧偗曽偺俆帪崰偱偡丅偦偟偰丄挬偼憉夣側栚妎傔丅堦擔偱帪嵎傪崕暈乮丠乯偟傑偟偨丅
丂偲偙傠偑丄擔杮偵栠偭偰偐傜偼戝曄偱偡丅儓乕儘僢僷帪娫偵夁忚揔墳偟偰偟傑偄丄埲慜傛傝寖偟偔栭拞偵栚偑嶀偊傢偨傝傑偡丅巹偵偲偭偰帪嵎偑儅僀僫僗俈帪娫偲偄偆偺偼丄偁傑傝偵傕偪傚偆偳搒崌偑傛偐偭偨偺偱偡丅堦擔偑俁侾帪娫偵側傝傑偡偐傜丅堦曽偱丄婣傝偺僾儔僗俈帪娫偼丄侾俈帪娫偱堦擔傪廔偊側偔偰偼側傜偢丄揔墳偵幐攕偟偰偟傑偄傑偟偨丅偄偭偦婣傝偼惣夞傝偵偟偰丄僔傾僩儖偁偨傝偱儅儕僫乕僘娤愴偱傕偟偰栠偭偰偔傟偽丄僶僢僠儕偩偭偨偺偱偟傚偆偑丅
丂丂2002/8/16(Fri)丂亙壺偺搒亜
丂惗傑傟偰偼偠傔偰儓乕儘僢僷偵峴偭偰偒傑偟偨丅婣崙搑忋偺旘峴婡偱擔杮偺僥儗價傪尒偰偄傞偲丄俶俫俲俈帪偺僯儏乕僗偱儓乕儘僢僷戝峖悈傪曬摴偟偰偄傞偱偼偁傝傑偣傫偐丅僗僀僗丒儐儞僌僼儔僂儓僢儂偱戝塉偵憳偄傑偟偨偑乮憡曄傢傜偢偺塉抝偱偡乯丄偁偺偲偒偺岤偄塤偐傜偺愨偊娫側偄塉偑彫偝側戲丄偦偟偰愳傪捠偭偰暯抧偵棳傟崬傒丄崱夞偺戝峖悈偵側偭偨偺偱偟傚偆丅
丂僪僀僣丒僗僀僗丒僼儔儞僗傪弰傞乬偙偰偙偰乭偺僣傾乕偱丄僗僀僗偱偼塉偲柖偱堦悺愭偼埮偺傛偆側忣偗側偄擔乆偱偟偨偑丄壺偺搒僷儕偵偼姶摦偟傑偟偨丅奨慡懱偑堦偮偺暥壔傪宍惉偟偰偄偰丄壗偐堦偮偺寶暔傪尒偰偄偰傕丄慡懱偵棳傟傞堄巙偺傛偆側傕偺傪姶偠傞偙偲偑偱偒傞丄偦偺傛偆側搒巗偱偟偨丅
丂墷廈峴偒傪巚偄棫偭偨偺偼丄崱壞丄尋媶幒偑夵廋岺帠偺偨傔偵巊偊側偄偲偄偆偙偲偑堦偮偺偒偭偐偗偱偟偨丅偆偩傞傛偆側擔杮偺壞偺拞丄壠偱僶僥偰偄傞傛傝傕丄巚偄愗偭偰弌偐偗偰傒傛偆偲寛抐偟傑偟偨丅偙傟傑偱恖椶偑抸偄偰偒偨暥壔偺執戝偝偵斾傋偰丄帺暘偲偄偆懚嵼偺偁傑傝傕偺偪偭傐偗偝偵婥偯偐偝傟傞椃偵側傝傑偟偨丅婣偭偰偒偨傜擔杮傕彮偟偼椓偟偔側偭偰偒偨傛偆偱偡丅
丂丂2002/8/4(Sun)丂亙奊擔婰亜
丂壞媥傒偺廻戣晽偵奊擔婰偵僩儔僀偟偰傒傑偟偨丅乮偠偮偼巇帠偐傜偺摝旔偱偡乯
丂崱擔丄嫵夛妛峑偱偒傚偆偗偮愼傔傪妝偟傒傑偟偨丅

丂榓巻傪洜晽愜偵愜偭偰丄斅偱嫴傫偱妏傪愼椏偵偮偗傑偡丅
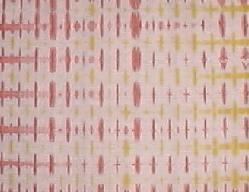
丂嶰妏宍偱愜傞偲師偺傛偆偵僇儔僼儖側柾條偑偱偒傑偡丅

偙傟偼徟偘偨怓偺榓巻偱嶌偭偨傕偺偱偡丅
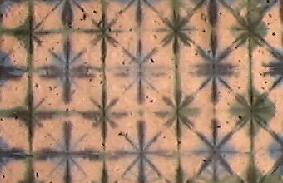
丂愼傔暔偲偄偆偲擄偟偄偐偲巚偄傑偟偨偑丄梒抰墍擭挿偝傫埲忋偩偲廫暘偵偱偒傞傛偆偱偡丅巕偳傕偨偪偺嶌昳偼丄僴僢偲偡傞傛偆側慛傗偐側弌棃塮偊偱丄戝恖傕婄晧偗偱偟偨丅偙偺偁偲丄巕偳傕偨偪偼丄帺暘偨偪偱愼傔偨榓巻傪巊偭偰丄偆偪傢傪嶌傝傑偟偨丅偍庤惢偺偛帺枬偺乬偆偪傢乭偱偙偺壞偺弸偝傕偳偙偐偵悂偒旘傇偙偲偱偟傚偆丅
丂弨旛傪偟偰壓偝偭偨曽乆丄偁傝偑偲偆偛偞偄傑偟偨丅傑偝偟偔幐攕偲偄偆傕偺偺側偄偒傚偆偗偮愼傔丄妝偟偄偱偡傛丅巕偳傕偨偪偲堦弿偵挧愴偟偰傒偰偼偄偐偑偱偟傚偆偐丠
丂丂2002/8/4(Sun)丂亙嵞尒亜
丂弸偐偭偨壞偩偑丄師偼楍搰拞偑僗僐乕儖偵尒晳傢傟偰偄傞丅搶杒偑戝塉偲偄偆偙偲偩偭偨偑丄偄傛偄傛擔杮楍搰傕擬懷偵側傝偮偮偁傞偺偐傕偟傟側偄丅
丂偝偰丄嶐擭偺僐儔儉偱丄儓乕儘僢僷偵峴偭偰偒偨偲恀偭愒側僂僜傪偮偒傑偟偨偑乮偁傞妛惗偵搟傜傟傑偟偨丂乮__乯乯丄崱擭偙偦傎傫傕偺偺儓乕儘僢僷傊峴偔梊掕丅柧擔偐傜弌敪偱偡丅偼偠傔偰偺儓乕儘僢僷偱偪傚偭偲妝偟傒偱偡丅傑偨傎傫偲偐僂僜偐傢偐傜側偄傛偆側暥復傪彂偄偰偄傑偡偑丄婣崙傑偱偟偽傜偔偺娫丄峏怴偼偍媥傒偱偡丅崱搙偺儓乕儘僢僷峴偒偑傎傫偲偐僂僜偐偼丄嵞奐屻偺僐儔儉偱偍妋偐傔壓偝偄丅偦傟偱偼丄僗僐乕儖偮偒偺撿崙偺壞傪偍妝偟傒壓偝偄丅
丂丂2002/8/2(Fri)丂亙棆塤亜
丂奜偼棆塤偑峀偑傝丄堫岝偑鄪傔偄偰偄傞丅偡傫偱偺偲偙傠偱棆塉偵偼憳傢偢偵彆偐偭偨偑丄僑儘僑儘偲偄偆壒偺壓丄憗懌偵曕偄偰偄偨偲偒偼僴儔僴儔僪僉僪僉偩偭偨丅乽抧恔丂偐傒側傝丂壩帠丂偍傗偠乿偲偼傛偔尵偭偨傕偺偩丅偐傒側傝偼偐側傝晐偄丅僪僢僈乕儞両丂崱丄偡偖嬤偔偵棆偑棊偪偨丅棆偝傑偵偼偔傟偖傟傕偛梡怱両
丂丂2002/8/1(Thu)丂亙梀傏偆亜
丂俈寧偑嫀傝丄崱擔偐傜俉寧偑巒傑偭偨丅偁偁丄俈寧傛丄擆偼側偤偐偔傕憗懌偵嫀傝備偔偺偐丅偦偟偰丄偁偁丄俉寧傛丄擆偼側偤偄偮傕俈寧傛傝傕憗懌側偺偐丅
丂偄偮傑偱傕廔傢傜側偐偭偨傛偆側婥偑偡傞俆寧偲俇寧偵斾傋偰丄偁偭偲偄偆娫偵俈寧偑夁偓嫀偭偨丅偙偺嵨偵側偭偰傕壞媥傒偺廻戣偵捛傢傟偰偄傞丅俉寧偼彮偟弌偐偗偨傝傕偡傞偺偱丄巹偵巆偝傟偨帪娫偼彮側偄丅
丂愭擔丄偁傞妛夛偵嶲壛偟偰丄崱丄彫丒拞丒崅偺嫵堢尰応偱偼丄乽巇崬傒偺帪娫側偟偵丄椏棟傪弌偣偲尵傢傟偰偄傞乿傛偆側忬懺偱偁傞偲偄偆嫵巘偺曽乆偺榖傪偆偐偑偭偨丅嶨柋偲乽嬑柋傪偟偰偄傑偡乿偲偄偆彂椶嶌傝摍偺偨傔偵嫵嵽尋媶傪偡傞帪娫偑側偄偲偄偆丅
丂偁傞偲偙傠偱丄乽戝妛偺愭惗偭偰偄偄偱偡偹丅摨偠僲乕僩偱壗擭傕島媊偟偰偄傞偭偰偄偆偠傖偁傝傑偣傫偐乿偲尵傢傟偨丅巚傢偢丄乽偁側偨偑偍傗傝偵側偭偨傜偄偐偑偱偡偐乿偲偐偮偰偺愮梩偡偢偺傛偆側偙偲偽傪曉偦偆偲巚偭偨偑丄戝恖偘側偄偲巚偄丄偖偭偲偙偲偽傪撣傒崬傫偩丅
丂巹偺崅峑帪戙偺壎巘偼丄屵慜俀帪偵婲偒偰丄惗搆偨偪偺暥復傪揧嶍偟偰偄傞丅壎巘偺壠偵偼丄侾枩嶜嬤偄杮偑暲傃丄彴偑崱偵傕捑傑傫偲偟偰偄傞丅
丂堦棳偺儔乕儊儞壆偝傫偼丄奺抧傪傑傢偭偰堦棳偺怘嵽傪廤傔丄尋媶傪廳偹丄偍媞偺恎懱偲偙偙傠偵煄傒偄傞堦攖偺儔乕儊儞傪嶌偭偰偄傞丅扤傕丄儔乕儊儞壆偝傫偑偒偪傫偲儔乕儊儞傪嶌偭偰偄傞偐偙偲傪徹柧偡傞偨傔偵朿戝側彂椶傪採弌偟傠偲偼尵傢側偄偩傠偆丅朿戝側彂椶傪採弌偝偣傞偙偲偑丄偆傑偄儔乕儊儞偵偁傝偮偔曽朄偲偼偲偆偰偄巚偊側偄偐傜偱偁傞丅
丂偟偐偟丄嫵堢尰応偱偼丄崱偙偆偟偨傾儂傜偟偄偙偲偑傕偭偲傕傜偟偄晽傪偟偰峴傢傟偰偄傞丅傢偞傢偞傑偢偄儔乕儊儞傪嶌傜偣偰偍偄偰丄巕偳傕偨偪偵傑偢偄傕偺傪怘偊偲偄偆偺偱偼丄戝恖傕丄巕偳傕傕丄婥偺撆偲偟偐尵偄傛偆偑側偄丅
丂暥壔偺幙偼丄偳傟偩偗嫮偄偙偩傢傝傪傕偪丄偦偟偰偦偺偙偩傢傝傪怺傔傞偨傔偺帇栰傪峀偘傜傟傞偐偵偐偐偭偰偄傞丅廻戣傕偄偄偗偳丄偍偍偄偵梀傫偱丄帺暘偺帇栰傪堢偰偰偄偒偨偄傕偺偱偁傞丅嫵巘偨偪傛丄梀傏偆丅嫵巘偨偪偺梀傃偺峀偑傝丄怺傒偑丄枹棃偺幮夛偺扴偄庤傪堢偰偰偄偔偺偩偐傜丅