『こころ』
夏目漱石(新潮文庫)(1914)
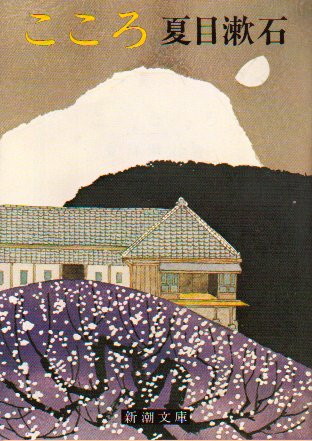 高校の現代文教科書にも掲載されている夏目漱石の代表作。人間の罪に迫るテーマを内包しているため、その読みが倫理的な読みに限定され、従来、下「先生と遺書」のみがクローズ・アップされてきた。だが、作家秦恒平氏や文学者小森陽一氏の画期的な読み直しを通して、この作品に「新らしい命が宿」ったといっても過言ではないだろう。
高校の現代文教科書にも掲載されている夏目漱石の代表作。人間の罪に迫るテーマを内包しているため、その読みが倫理的な読みに限定され、従来、下「先生と遺書」のみがクローズ・アップされてきた。だが、作家秦恒平氏や文学者小森陽一氏の画期的な読み直しを通して、この作品に「新らしい命が宿」ったといっても過言ではないだろう。
秦恒平氏は、『こころ』を題材とする授業の中で、『こころ』の登場人物である「先生」「奥さん(御嬢さん)」「私」の歳はそれぞれいくつかという課題を出している。この課題を頭に入れながら読み進めると、著者の漱石は、作品の中に、それぞれの歳を明らかにするための手がかりをいくつも用意していることが明らかになる。たとえば、「奥さん(御嬢さん)」の父親は、日清戦争で戦死したと書いてある。「奥さん(御嬢さん)」は、そののち、小石川に引っ越し、女学校に通っている。その小石川の家で大学生の下宿人であった「先生」と女学生の「奥さん(御嬢さん)」は出会っている。日清戦争は明治27年から28年にかけて起こっており、「先生」が死んだのは明治45年(大正元年)である。これを計算するだけでも、「先生」が死んだのは30代、そのとき「奥さん(御嬢さん)」はさらに若かったことが推測できる。秦氏の論証は、さらに緻密であり、ほとんど精度プラス・マイナス1年で、登場人物の年齢を明らかにされている。(『東工大「作家」教授の幸福』参照)
高校時代、私は下「先生と遺書」を読み、「K」も「先生」も、失恋とか、明治の精神に殉ずるとか、そういう理屈で死を選んだのではなく、圧倒的な寂しさが彼らを覆ったのではないだろうか、と書いた。そして、この圧倒的な寂しさと折り合って、人生を編み上げていくためには、一人で生まれ、一人で死ぬという人間存在の寂しさを哲学的に追究するよりも、「いい加減」「適当」といった実践原理を大事にすることが有効ではないか、と書いた。つまり、私は、何一つ「K」や「先生」の「思想」を信じていなかったのだ。ほとんど「私」の「両親」のような古い人間の立場から「K」や「先生」を断罪していた。その後、私は大学に進み、学問の道を志した。一転して私は、「K」や「先生」に近い立場になった。そして、「K」や「先生」の立場から「両親」「世間」を軽蔑するようになった。というよりも、自分の中にある「両親」「世間」なるものを軽蔑するようになったのだ。だが、それもまた行き詰まった。そして、今、「こころ」を読み返してみると、漱石が下「先生と遺書」の前に、上「先生と私」、中「両親と私」を置いていることの意味がおぼろげに見えるようになった。「先生」と「両親」(あるいは欧米と日本)を二項対立的に置くのではなく、もう一つの軸として「新らしい命を宿」すであろう「私」をきっと置いたのだ。あるいは、もう一つの軸とは、「私」ではなく、まだ見ぬ「新らしい命」だったのかもしれない。
「淋しい」というキーワードを通して、人のこころのあやと、人と人とのつながりのあやうさを描写している『こころ』は、まさしく読みの宝庫である。風雪を越えてきた文学作品には読み手の成熟に応じて、多様な読みを許す深みがある。
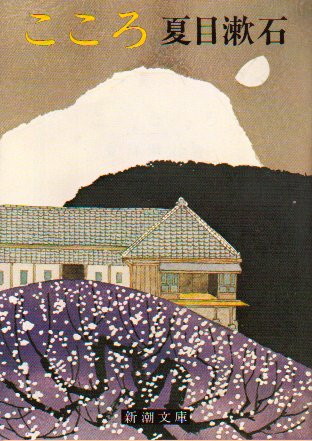 高校の現代文教科書にも掲載されている夏目漱石の代表作。人間の罪に迫るテーマを内包しているため、その読みが倫理的な読みに限定され、従来、下「先生と遺書」のみがクローズ・アップされてきた。だが、作家秦恒平氏や文学者小森陽一氏の画期的な読み直しを通して、この作品に「新らしい命が宿」ったといっても過言ではないだろう。
高校の現代文教科書にも掲載されている夏目漱石の代表作。人間の罪に迫るテーマを内包しているため、その読みが倫理的な読みに限定され、従来、下「先生と遺書」のみがクローズ・アップされてきた。だが、作家秦恒平氏や文学者小森陽一氏の画期的な読み直しを通して、この作品に「新らしい命が宿」ったといっても過言ではないだろう。