『将棋の子』
大崎善生(講談社、2001)
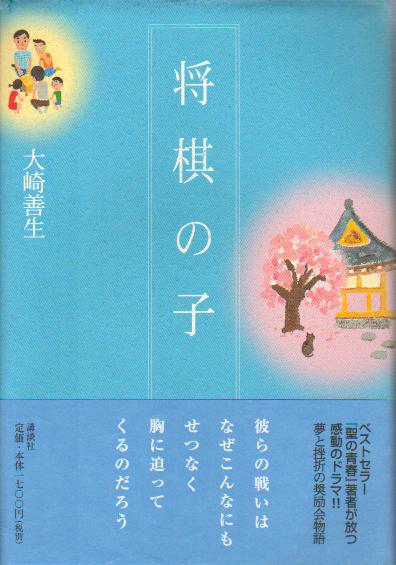 著者の大崎善生は、1957年生。日本将棋連盟に勤め、棋士たち、そして奨励会員という棋士の卵たちと同じ空気を吸い、彼らの痛み、苦しみを見つめ、感じてきた。大崎の卓越した人間に対する温かいまなざしと、冷徹な現実を見つめ、それを書き切る厳しさは、「第13回新潮学芸賞」を受賞した前著『聖の青春』において、証明済みであった。その著者が、10年間にわたる『将棋世界』編集長の職をなげうち、書き綴った乾坤一擲の一冊が、この『将棋の子』である。
著者の大崎善生は、1957年生。日本将棋連盟に勤め、棋士たち、そして奨励会員という棋士の卵たちと同じ空気を吸い、彼らの痛み、苦しみを見つめ、感じてきた。大崎の卓越した人間に対する温かいまなざしと、冷徹な現実を見つめ、それを書き切る厳しさは、「第13回新潮学芸賞」を受賞した前著『聖の青春』において、証明済みであった。その著者が、10年間にわたる『将棋世界』編集長の職をなげうち、書き綴った乾坤一擲の一冊が、この『将棋の子』である。
この本は、「将棋棋士を夢見てそして志半ばで去っていった奨励会退会者の物語である」。全国から神童とうたわれた将棋の天才たちが、叩く門が<奨励会>である。何せ全国から自信満々の強者どもが集まってくるわけであり、並大抵の棋力では入会はおぼつかない。そして、たとえ入会できたとしても、そこから想像を絶するような過酷な競争が待ち受けている。たいてい6級で入会した少年たちは、21歳で初段、26歳で4段というハードルを越えなければならない。このハードルにつまづいた者は、退会という結末が待ち受けている。なかでも、プロ棋士を目前にした3段リーグは、あまりにもし烈な競争の場であり、半年間のリーグ戦でわずか2名しか突破できない。すべての年代にチャンスが均等にあると考えるならば、同年齢集団でわずかに4名しかプロ棋士への道は開かれていないことになる。全国でわずかに4名である。そればかりではない。空前の七冠を獲得した羽生王将たちの世代は、怒濤の集団であり、ほかの世代を蹴散らしながら、この競争を駆け上がっていった。したがって、ここに前後する世代では、同年齢集団でわずかに4名という枠すら残されていないのである。
大崎は、名人をめざして上京し、将棋に青春を捧げながら、夢半ばで散っていった多くの若者たちを、すぐそばで見続けてきた。そして、この物語を書くために、日本将棋連盟を辞めた。著者と同郷の北海道から、上京し、貧しい家族ながらも家族みんなで支え合いながら、最後は力尽き、夢やぶれた成田2段の話が、この物語の中心をなしている。成田2段と家族の生と死、またほかの夢やぶれし者たちの生き方、どれも暗闇の中のともしびのごとく、光っている。ともしびを書くのではなく、深い闇を書き切ることで、彼らの生をキラキラと浮かび上がらせている著者の筆力は、見事というよりも、凄絶ですらある。
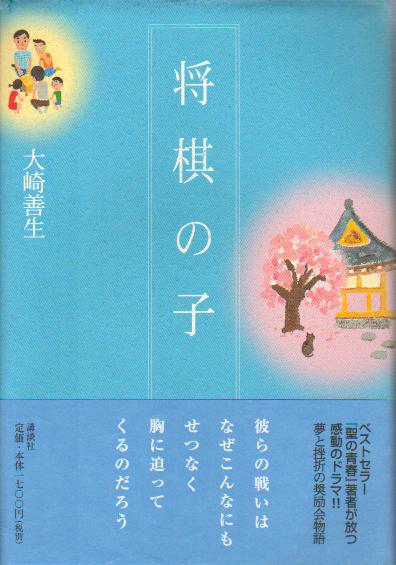 著者の大崎善生は、1957年生。日本将棋連盟に勤め、棋士たち、そして奨励会員という棋士の卵たちと同じ空気を吸い、彼らの痛み、苦しみを見つめ、感じてきた。大崎の卓越した人間に対する温かいまなざしと、冷徹な現実を見つめ、それを書き切る厳しさは、「第13回新潮学芸賞」を受賞した前著『聖の青春』において、証明済みであった。その著者が、10年間にわたる『将棋世界』編集長の職をなげうち、書き綴った乾坤一擲の一冊が、この『将棋の子』である。
著者の大崎善生は、1957年生。日本将棋連盟に勤め、棋士たち、そして奨励会員という棋士の卵たちと同じ空気を吸い、彼らの痛み、苦しみを見つめ、感じてきた。大崎の卓越した人間に対する温かいまなざしと、冷徹な現実を見つめ、それを書き切る厳しさは、「第13回新潮学芸賞」を受賞した前著『聖の青春』において、証明済みであった。その著者が、10年間にわたる『将棋世界』編集長の職をなげうち、書き綴った乾坤一擲の一冊が、この『将棋の子』である。