『自殺する子どもたち』
エレーヌ・リザシュ/シャルタル・ラバット(筑摩書房、1997)
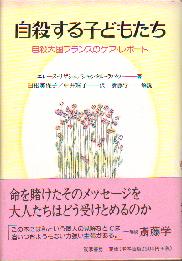 日本社会において自殺が見逃せない勢いで増えている。最も多いのは、中高年層であり、男性が女性よりもかなり大きい値を示している。昨年、日本における男子の平均寿命は、自殺の増加によって下がっている。このくらい、自殺は大きな社会問題となりつつある。この一方で、減少傾向にあった子どもたちの自殺もまた増加しつつある。子どもたちの自殺は、たとえ数は少なくても、自殺という現象を知る上で、さらに自殺からわたしたちを救う上で、学ぶべきことが多いと思われる。というのも、自殺というのは、究極的には自己の否定であり、若年層の自殺にそのことが顕著にあらわれるからである。経済的な問題が中高年の自殺の原因であるとよくいわれるが、中高年の自殺においても根っこにあるのは自己肯定感の欠如ではないかと私は考える。同じ苦境に立たされても、自分は生きるに値するという自己肯定感があれば、対処の仕方はまた変わってくる。
日本社会において自殺が見逃せない勢いで増えている。最も多いのは、中高年層であり、男性が女性よりもかなり大きい値を示している。昨年、日本における男子の平均寿命は、自殺の増加によって下がっている。このくらい、自殺は大きな社会問題となりつつある。この一方で、減少傾向にあった子どもたちの自殺もまた増加しつつある。子どもたちの自殺は、たとえ数は少なくても、自殺という現象を知る上で、さらに自殺からわたしたちを救う上で、学ぶべきことが多いと思われる。というのも、自殺というのは、究極的には自己の否定であり、若年層の自殺にそのことが顕著にあらわれるからである。経済的な問題が中高年の自殺の原因であるとよくいわれるが、中高年の自殺においても根っこにあるのは自己肯定感の欠如ではないかと私は考える。同じ苦境に立たされても、自分は生きるに値するという自己肯定感があれば、対処の仕方はまた変わってくる。
この本は、自殺大国フランスの自殺を試みた子どもたちに対するケア・レポートである。「フランスでは毎年、四万人にのぼる二十四歳以下の若者が自殺を図り、千人近くが命を落とす」という。さらに、「自殺を試みた十五歳から二十四歳の若者のうち五五パーセントが、計画的なものではなかった」という。自殺を試みる子どもたちは、何度も繰り返す可能性があり、最初のケアがとても大事であるという。病院への移送、胃の洗浄から蘇生にあたるフランスの救急医療の人々の働きは、感動的なものがある。自殺は病であり、手厚いケアをする必要があるものである。本書を読むことで、心は傷つきやすいものであること、しかし、ケアによる回復の光があることに気づかされる。心の傷を隠蔽し、ケアを怠るために自己責任ということばを使うわが国のありようを、自分自身から変えていかなくてはならないと思わされる一冊である。
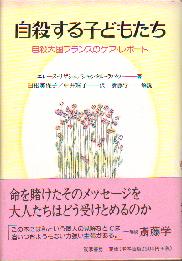 日本社会において自殺が見逃せない勢いで増えている。最も多いのは、中高年層であり、男性が女性よりもかなり大きい値を示している。昨年、日本における男子の平均寿命は、自殺の増加によって下がっている。このくらい、自殺は大きな社会問題となりつつある。この一方で、減少傾向にあった子どもたちの自殺もまた増加しつつある。子どもたちの自殺は、たとえ数は少なくても、自殺という現象を知る上で、さらに自殺からわたしたちを救う上で、学ぶべきことが多いと思われる。というのも、自殺というのは、究極的には自己の否定であり、若年層の自殺にそのことが顕著にあらわれるからである。経済的な問題が中高年の自殺の原因であるとよくいわれるが、中高年の自殺においても根っこにあるのは自己肯定感の欠如ではないかと私は考える。同じ苦境に立たされても、自分は生きるに値するという自己肯定感があれば、対処の仕方はまた変わってくる。
日本社会において自殺が見逃せない勢いで増えている。最も多いのは、中高年層であり、男性が女性よりもかなり大きい値を示している。昨年、日本における男子の平均寿命は、自殺の増加によって下がっている。このくらい、自殺は大きな社会問題となりつつある。この一方で、減少傾向にあった子どもたちの自殺もまた増加しつつある。子どもたちの自殺は、たとえ数は少なくても、自殺という現象を知る上で、さらに自殺からわたしたちを救う上で、学ぶべきことが多いと思われる。というのも、自殺というのは、究極的には自己の否定であり、若年層の自殺にそのことが顕著にあらわれるからである。経済的な問題が中高年の自殺の原因であるとよくいわれるが、中高年の自殺においても根っこにあるのは自己肯定感の欠如ではないかと私は考える。同じ苦境に立たされても、自分は生きるに値するという自己肯定感があれば、対処の仕方はまた変わってくる。