『自分を愛するということ』
香山リカ(講談社現代新書、1999)
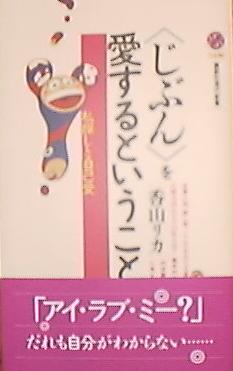 最近、講談社現代新書が面白い。1990年の日本社会のリアリティを読み解く手がかりを提供してくれている。この本は、精神科医で現代のサブカルチャーに関する考察を続けている香山リカが、専修大学で行った講義を書き下ろしたもので、1980年代から1990年代にかけての日本人の心性がわかりやすく辿られている。著者の年齢は私よりもちょっと上かと思いきや、1960年生まれということで思ったよりもうちょっと上だった。
最近、講談社現代新書が面白い。1990年の日本社会のリアリティを読み解く手がかりを提供してくれている。この本は、精神科医で現代のサブカルチャーに関する考察を続けている香山リカが、専修大学で行った講義を書き下ろしたもので、1980年代から1990年代にかけての日本人の心性がわかりやすく辿られている。著者の年齢は私よりもちょっと上かと思いきや、1960年生まれということで思ったよりもうちょっと上だった。
それはさておき、本書では、多重人格、ストーカー、アダルト・チルドレンという三つのキーワードを手がかりに、<自分探し>をする人々の生きにくさのありようを探っている。その中で明らかにされたのは、等身大の自己を受け容れることの難しさである。「すばらしいほんとうの自分がどこかにいるはず」と思いこみ、今までの自分との連続性の上にではなく、非連続な地平において<自分探し>をするわたしたちは、カルトに安易に取り込まれる身体になっている。
わたし自身のことを思い返すと、小学校の時に骨折した同級生が妙にうらやましかったことがある。腕を骨折して吊っているという特別な状態がうらやましかったのである。また、大学時代、友人と話をしていて、「平凡な普通人であるよりも異常な天才でありたい」と彼が語っていたことを思い出す。平凡だけど、結構いいヤツの自分というふうにうけいれることができないのだ。わたしたち1960年代生まれは、バブルの時代に青春時代を迎え、平凡であることをバカにする心性を身につけてしまった。エクセレント(卓越している者)であることを懸命に求め、自我が肥大化する中で、今自我のなかみの空虚さに気づかされ、苦しみもがいている。
では、高度経済成長的平凡に戻ればいいのか。わたしはそうは思わない。わたしたちの世代のエクセレント志向の中には、高度経済成長期の小市民的な平凡に対するアンチ・デーゼがあったように思うのだ。テレビ、マイカー、マイホームをもち、夏休みに家族旅行をして、これでよしとする。そういう生き方に対する反抗があったように思うのだ。等身大の自己を受け容れることができないということと、高度経済成長的平凡を受け容れることができないということがどこかでつながっているのではないか。そうであるならば、わたしたちの課題は、単に等身大の自己を受け容れて癒されてしまうのではなく、癒されない身体から癒されない社会への想像力を紡ぎだして、そこにおいて一定の役割を自分に課すことではないだろうか。わたしの感覚に近いのは、Mr.ChildrenのTomorrow Never Knowsにある「果てしない闇の向こうに手を伸ばそう 癒えることない痛みならいっそ引き連れて 少しぐらいはみ出したっていいさ 夢を描こう 誰かのために生きてみたって Tomorrow never knows」である。

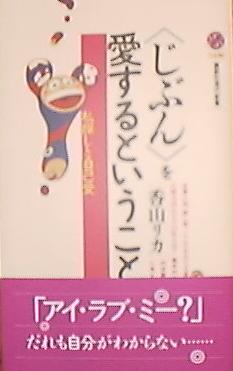 最近、講談社現代新書が面白い。1990年の日本社会のリアリティを読み解く手がかりを提供してくれている。この本は、精神科医で現代のサブカルチャーに関する考察を続けている香山リカが、専修大学で行った講義を書き下ろしたもので、1980年代から1990年代にかけての日本人の心性がわかりやすく辿られている。著者の年齢は私よりもちょっと上かと思いきや、1960年生まれということで思ったよりもうちょっと上だった。
最近、講談社現代新書が面白い。1990年の日本社会のリアリティを読み解く手がかりを提供してくれている。この本は、精神科医で現代のサブカルチャーに関する考察を続けている香山リカが、専修大学で行った講義を書き下ろしたもので、1980年代から1990年代にかけての日本人の心性がわかりやすく辿られている。著者の年齢は私よりもちょっと上かと思いきや、1960年生まれということで思ったよりもうちょっと上だった。