『いのち、響きあう』
森崎和江(藤原書店、1998)
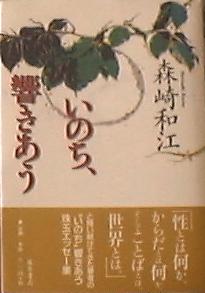 著者の森崎和江は、『地の底の笑い話』の上野英信や谷川雁たちとともに、筑豊の炭坑地帯に住み、そこで人間が生きるという営みと効率性・利潤を求める近代のシステムとの相克を見つめつづけてきた。この本は、森崎がまだ幼い頃にもった二つの疑問、「なぜ大人は生まれたばかりの子を殺すのか」、そして「なぜ男は、女の子を殺すのか」という重く暗い問いを、自らのからだにふれながら、問い進めた本である。わたしが印象的だったこの本の一節を紹介しよう。
著者の森崎和江は、『地の底の笑い話』の上野英信や谷川雁たちとともに、筑豊の炭坑地帯に住み、そこで人間が生きるという営みと効率性・利潤を求める近代のシステムとの相克を見つめつづけてきた。この本は、森崎がまだ幼い頃にもった二つの疑問、「なぜ大人は生まれたばかりの子を殺すのか」、そして「なぜ男は、女の子を殺すのか」という重く暗い問いを、自らのからだにふれながら、問い進めた本である。わたしが印象的だったこの本の一節を紹介しよう。
「ある日、友人と雑談をしていました。私は妊娠五か月目に入っていました。/笑いながら話していた私は、ふいに、『わたしはね……』と、いいかけて、『わたし』という一人称がいえなくなったのです。/いえ、ことばは一呼吸おいて発音しました。でも、それは、もう一瞬前の『わたし』ではありませんでした。」
森崎は、子どもを孕んだ自身のからだを語ることばがないことに気づき、唖然とした感覚をもつ。そして、産む、生まれるという人間にとっての根源的な経験をめぐる大きな領域が空白のまま残されていることを発見するのである。
そののち、森崎は、ある事件をきっかけとして、自身のセクシュアリティがからだから奪われていくという経験をする。エロスを取り戻すために、森崎は、自分自身のセクシュアリティとさまざまな他者のセクシュアリティを受けとめる、長くつらい心の旅を遍路するのである。
今、森崎は70歳を過ぎ、この『いのち、響きあう』という一冊に、おんなのからだ、エロスからとらえた、「いのちのライフサイクル」論とでもいうべき、思索のことばを残してくれた。子どもが一つのいのちであることが、これまでの歴史のなかでもおそらく最も軽視され、奪われている今、いのちとエロスという観点から人間のライフサイクル、世代継承をとらえなおすことが切に求められているように思う。

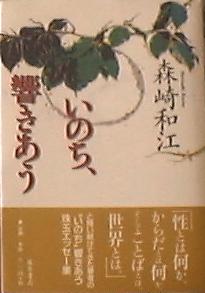 著者の森崎和江は、『地の底の笑い話』の上野英信や谷川雁たちとともに、筑豊の炭坑地帯に住み、そこで人間が生きるという営みと効率性・利潤を求める近代のシステムとの相克を見つめつづけてきた。この本は、森崎がまだ幼い頃にもった二つの疑問、「なぜ大人は生まれたばかりの子を殺すのか」、そして「なぜ男は、女の子を殺すのか」という重く暗い問いを、自らのからだにふれながら、問い進めた本である。わたしが印象的だったこの本の一節を紹介しよう。
著者の森崎和江は、『地の底の笑い話』の上野英信や谷川雁たちとともに、筑豊の炭坑地帯に住み、そこで人間が生きるという営みと効率性・利潤を求める近代のシステムとの相克を見つめつづけてきた。この本は、森崎がまだ幼い頃にもった二つの疑問、「なぜ大人は生まれたばかりの子を殺すのか」、そして「なぜ男は、女の子を殺すのか」という重く暗い問いを、自らのからだにふれながら、問い進めた本である。わたしが印象的だったこの本の一節を紹介しよう。