『家族という神話』
ステファニー・クーンツ(岡村ひとみ訳)(筑摩書房、1998)
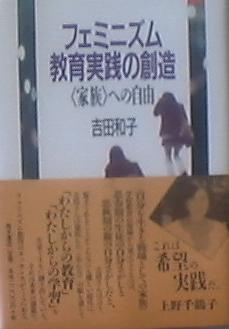 「アメリカン・ファミリーの夢と現実」という副題をもつこの本は、家族研究のバイブルというにふさわしい一冊である。わたしたち現代の日本人が「家族」ということばにもつイメージは、1950-60年代のアメリカ・ホームドラマに強い影響を受けているといわれている。例えば、NHKで放映された「大草原の小さな家」が理想の家族像の形成に果たした役割は大きいといえよう。ところが、本家本元のアメリカにおいても、テレビドラマなどで語られるような、大家族の中での団らんと親子の親愛の情に満ちた家族など、どの時代にもあり得なかったことのであることが、この本で明らかにされている。
「アメリカン・ファミリーの夢と現実」という副題をもつこの本は、家族研究のバイブルというにふさわしい一冊である。わたしたち現代の日本人が「家族」ということばにもつイメージは、1950-60年代のアメリカ・ホームドラマに強い影響を受けているといわれている。例えば、NHKで放映された「大草原の小さな家」が理想の家族像の形成に果たした役割は大きいといえよう。ところが、本家本元のアメリカにおいても、テレビドラマなどで語られるような、大家族の中での団らんと親子の親愛の情に満ちた家族など、どの時代にもあり得なかったことのであることが、この本で明らかにされている。
そもそも大家族においては親子の親愛の情に満ちた関係などつくりようがなかった。生産共同体である大家族においては、子育てはマージナルな仕事でしかなかったからである。そして、都市化、消費社会化が進展し、そこに核家族と親子の密接な関係が生み出された。ところがこうして誕生した教育家族は、人々が進んで選択した家族像であるというよりはむしろ、生産手段を剥奪された都市民がいやおうなく選ばざるを得なかった家族像であった。そして今、愛情家族というイデオロギーの下に、国家は、子どもを育てる公共空間を創り、維持するという役割を放棄し、家庭にその役割を押しつけようとしている。
一橋大学の元学長であった阿部謹也さんの話によると、ゼミ生に自分史を書かせ、語らせたところ、異口同音に母親に対しての憤りが噴出したという。家庭に子育てのすべての責任を押しつけ、子どもが社会階層のどこに位置づくかもあたかも家庭の自助努力によって決まるかのような体裁をとった結果がこれである。これでは母親は浮かばれない。わたしたちはエキセントリックな母親の向こうに一つのいびつなシステムを読みとらなくてはならない。これは幼児虐待についても同じである。
ステファニー・クーンツのこの作品は、19世紀以降のアメリカ社会における家族をめぐる言説の緻密な検証を通して、理想の家族像に縛られることの危うさと、家族さえ満たされればすべてのことは解決するという神話の虚構を明らかにしている。家族はわたしたちの生活における大切な一つのユニットであるが、決してわたしたちの生き方のすべてではない。家族論の研究はここから始められなくてはならない。

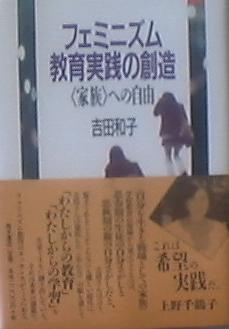 「アメリカン・ファミリーの夢と現実」という副題をもつこの本は、家族研究のバイブルというにふさわしい一冊である。わたしたち現代の日本人が「家族」ということばにもつイメージは、1950-60年代のアメリカ・ホームドラマに強い影響を受けているといわれている。例えば、NHKで放映された「大草原の小さな家」が理想の家族像の形成に果たした役割は大きいといえよう。ところが、本家本元のアメリカにおいても、テレビドラマなどで語られるような、大家族の中での団らんと親子の親愛の情に満ちた家族など、どの時代にもあり得なかったことのであることが、この本で明らかにされている。
「アメリカン・ファミリーの夢と現実」という副題をもつこの本は、家族研究のバイブルというにふさわしい一冊である。わたしたち現代の日本人が「家族」ということばにもつイメージは、1950-60年代のアメリカ・ホームドラマに強い影響を受けているといわれている。例えば、NHKで放映された「大草原の小さな家」が理想の家族像の形成に果たした役割は大きいといえよう。ところが、本家本元のアメリカにおいても、テレビドラマなどで語られるような、大家族の中での団らんと親子の親愛の情に満ちた家族など、どの時代にもあり得なかったことのであることが、この本で明らかにされている。