『フェミニズム教育実践の創造』
吉田和子(青木書店、1997)
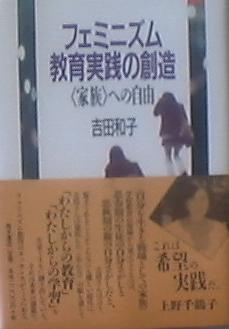 この本は、高度経済成長以後の激動の30年間を、商業科の教師として高校生とともに歩みつづけた一人の女性教師、吉田和子の記録である。吉田は1967年秋、東京都の高校商業科教員試験に合格する。吉田の教職生活は、その門出からけっして平坦なものではなかった。教員採用試験に合格しても、女性教師はなかなか採用されることがなかった時代のことである。「おんな」であるというハンディ、「身体障害者」であるというハンディをいやおうなく背負って、吉田が教師としての第一歩を踏み出すエピソードは、あまりにも鮮烈である。面接時の校長の「本校の商業科人事では、新採用、しかも女を採用した前歴はない」という厳しい口調と、そのあとに続く、「君は身体障害者で“びっこ”であると記録にあるが、先生方の前で歩いてみてほしい」という発言。祝福と期待が与えられるはずの儀式で、あろうことかまなざされる存在として学校空間に放り投げられたのである。このエピソードには、「おんな」「障害者」というまなざされる存在、すなわち「おとこ」「健常者」といった他者が構築した世界像に投げ込まれた者として、その教職生活を踏み出さざるを得なかった吉田の教職生活の原点が見事に表現されている。
この本は、高度経済成長以後の激動の30年間を、商業科の教師として高校生とともに歩みつづけた一人の女性教師、吉田和子の記録である。吉田は1967年秋、東京都の高校商業科教員試験に合格する。吉田の教職生活は、その門出からけっして平坦なものではなかった。教員採用試験に合格しても、女性教師はなかなか採用されることがなかった時代のことである。「おんな」であるというハンディ、「身体障害者」であるというハンディをいやおうなく背負って、吉田が教師としての第一歩を踏み出すエピソードは、あまりにも鮮烈である。面接時の校長の「本校の商業科人事では、新採用、しかも女を採用した前歴はない」という厳しい口調と、そのあとに続く、「君は身体障害者で“びっこ”であると記録にあるが、先生方の前で歩いてみてほしい」という発言。祝福と期待が与えられるはずの儀式で、あろうことかまなざされる存在として学校空間に放り投げられたのである。このエピソードには、「おんな」「障害者」というまなざされる存在、すなわち「おとこ」「健常者」といった他者が構築した世界像に投げ込まれた者として、その教職生活を踏み出さざるを得なかった吉田の教職生活の原点が見事に表現されている。
最初の赴任校である下町の商業高校で、吉田は、着任早々、自らがおんなであるということと、教師であるということのひきさかれた感覚を痛切に味わっている。「愛嬌プラス美人」という基準で企業への学校推薦候補者が決められる職員会議、さらには同じ高校のカップルが妊娠に至りながらも女子生徒だけが“自主退学”させられ、男子生徒はそのまま通っているという不条理。これに加えて、教師であることがもうすでに「アンビバレント」な性格をもっている。教師が生徒から学ぶとき、そこにはしばしば、固有名詞の生徒の傷つき、苦しみが横たわっている。一人の生徒の傷つき、苦しみは、感受性の豊かな教師に内省を促し、新たな実践への展望を気づかせてくれることもある。しかし、そのときにはもう当の生徒とはかかわることができないかもしれない。着任早々、教師である以上逃れられないさまざまな不条理に直面した吉田は、大人の代弁者でありながらなおかつ子どもの自分づくりの支え手でもあるという教師であることの両義性を生き抜くことに自分の道を求める。このことは、自分自身の「生の負性」を切り捨てることなく、「生の負性」を通して他者とつながっていく回路の模索でもあった。
1970年代以降、日々の生徒とのかかわりを通して「生徒の変化の裏に親たちの生き方の変化があること」に気づいた吉田は、ホームルーム空間に生徒たちの家族関係をもちこみ、家族関係の編み直しの実践を試みる。「わたしの一六年間」と題する生徒一人ひとりの生育史を素材とする実践である。仲間の「自由になりたい」には共感的だが、親の「自由にさせてほしい」には手厳しい生徒たちに、親の代弁者としてすっくと立ち、親を前にしたときには生徒の代弁者となってしまう自分を見つめながら、吉田は次のように言う。「教師は決して親と生徒の当事者になることなどできないのである。できることがあるとすれば、異文化としての他者同士として、当事者たちを出会わせることかもしれない」教師であることの両義性を生きながら、学びの媒介者として生徒や父母と向き合う構えがここにある。
「わたしの一六年間」から出発した吉田の家族関係の編み直し実践は、次第に生徒の家族というミクロポリティックスから家父長制の呪縛にある近代家族というマクロポリティックスの核心へと切り込んでいく。「学びの当事者性」への徹底したこだわりが、学歴社会システムの周辺に位置する商業高校の生徒たちを、その周辺的存在のゆえに、学びの主体に据えることに成功している。家族から解放されたいと願う生徒たちだが、これまでの伝統的な家族像に変わるイメージをもてないために、結果的に結婚が人生のゴールという空虚な家族神話に取り込まれていく。皮肉なことに彼らの家族への反逆もまた家父長制の再生産の装置として機能しているのである。そこに吉田が対置したのが、本書の副題でもある「<家族>への自由」であった。同じように学びから解放されたいと願う生徒たちに必要なことは、学びからの解放ではなく、学びへの解放であったのだ。吉田のいう「三重のマイノリティー(①女であること、②子どもであること、③九〇%の生徒が高卒学歴で終わるノンエリートであること)の存在である商業高校の女性高校生の声の回復をはかり、語る・聴くの多様な関係性を通して、学びの当事者性確立をはかること」は、まさしく生徒の学びへの解放の過程であった。同時にこの過程は、「教師であるわたし自身も職場での男の基準に合わせて生きることをやめ、<おんな>であるわたしがやりたい仕事をやる。自分をあるがままに生きられる教育実践をする」、吉田の自分自身との格闘の歴史でもあった。
「おんな」であり、「障害者」であり、教師であるということの両義性を生き抜くことを試みた吉田のライフヒストリー(個人史)は、著者の自分自身であることへの徹底した沈潜ゆえに、女性教師の生活世界を色濃く映し出すことになった。その一方で、フェミニズム理論との出会い、マイノリティである自分自身を生きる他者との出会い、そして激動の時代の中で自分の生き方を模索する生徒との出会いを通して、著者が自らの個人的な経験を捉え直し、意味づけ直し続けていることが、個人的なこだわりから出発した教育実践に社会的なひろがりを与えている。
教育実践は教師の個人史の一局面であることによってのみ、ラディカルな政治的実践でありうる。フェミニズムが拓いた「個人的なことは政治的である」という認識を、学校・教室という魑魅魍魎な権力空間のなかで、未来をひらく実践として表現した吉田の教育実践は、単に教育学の枠内に留まらず、他の社会科学にも多大な影響を与える可能性を秘めているように思う。この著書は、教師の教育実践への解放のみちすじを指し示す実践記録であるとともに、日本におけるフェミニズム実践の誕生の記録として、語り伝えられるものとなるだろう。 (『人間と教育』誌より転載 執筆:高井良健一)

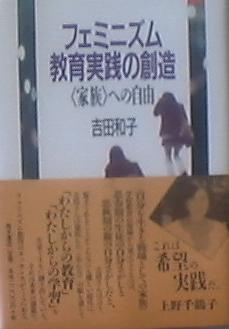 この本は、高度経済成長以後の激動の30年間を、商業科の教師として高校生とともに歩みつづけた一人の女性教師、吉田和子の記録である。吉田は1967年秋、東京都の高校商業科教員試験に合格する。吉田の教職生活は、その門出からけっして平坦なものではなかった。教員採用試験に合格しても、女性教師はなかなか採用されることがなかった時代のことである。「おんな」であるというハンディ、「身体障害者」であるというハンディをいやおうなく背負って、吉田が教師としての第一歩を踏み出すエピソードは、あまりにも鮮烈である。面接時の校長の「本校の商業科人事では、新採用、しかも女を採用した前歴はない」という厳しい口調と、そのあとに続く、「君は身体障害者で“びっこ”であると記録にあるが、先生方の前で歩いてみてほしい」という発言。祝福と期待が与えられるはずの儀式で、あろうことかまなざされる存在として学校空間に放り投げられたのである。このエピソードには、「おんな」「障害者」というまなざされる存在、すなわち「おとこ」「健常者」といった他者が構築した世界像に投げ込まれた者として、その教職生活を踏み出さざるを得なかった吉田の教職生活の原点が見事に表現されている。
この本は、高度経済成長以後の激動の30年間を、商業科の教師として高校生とともに歩みつづけた一人の女性教師、吉田和子の記録である。吉田は1967年秋、東京都の高校商業科教員試験に合格する。吉田の教職生活は、その門出からけっして平坦なものではなかった。教員採用試験に合格しても、女性教師はなかなか採用されることがなかった時代のことである。「おんな」であるというハンディ、「身体障害者」であるというハンディをいやおうなく背負って、吉田が教師としての第一歩を踏み出すエピソードは、あまりにも鮮烈である。面接時の校長の「本校の商業科人事では、新採用、しかも女を採用した前歴はない」という厳しい口調と、そのあとに続く、「君は身体障害者で“びっこ”であると記録にあるが、先生方の前で歩いてみてほしい」という発言。祝福と期待が与えられるはずの儀式で、あろうことかまなざされる存在として学校空間に放り投げられたのである。このエピソードには、「おんな」「障害者」というまなざされる存在、すなわち「おとこ」「健常者」といった他者が構築した世界像に投げ込まれた者として、その教職生活を踏み出さざるを得なかった吉田の教職生活の原点が見事に表現されている。