『私たちはどのような時代に生きているのか』
辺見庸×高橋哲哉(角川書店、2000)
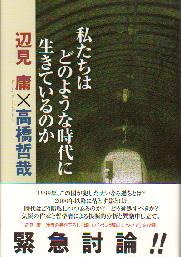 この本は、東京新聞文化部の企画として行われた「1999を問う」というタイトルでの辺見庸と高橋哲哉の対談を一冊の本にしたものである。辺見庸は、国家と個人の関係についてその身体を通して考え続けている最も信頼できる作家であり、高橋哲哉は、歴史を記憶するという人間の倫理を出来事の衝撃性のリアリティとつなげて考えているアクティブな哲学者である。今後の日本社会の行方を大きく左右しかねない法案の成立に対して、緊張感に欠けたジャーナリズム、マスコミの中で、この2人の対談を企画した東京新聞の勇気には心打たれる。さて、1999年の第百四十五通常国会にて成立した「周辺事態法(ガイドライン法案)」「盗聴法」「国旗・国歌法」「改正住民基本台帳法」の法案について、2人は厳しく深く語り合っていく。対談では、現実を見据えることなく、記憶を忘却の彼方に追いやり、心地よい観念にひたっている社会の風潮が厳しく批判され、出来事に直面し、異質と出会うことで、身体性を回復し、全体主義に穴を穿つ道が探られる。2人の議論はきわめて具体的なので、読者にとっても説得力がある。本書の中で最も共感したのは、元従軍慰安婦の女性の証言について、高橋が次のように語っているくだりである。「元慰安婦の人たちの話というのは、言葉のレベルでは、それは違う、そんなはずはないなどと、いろいろ言われます。ただそんなの当たり前なんですよ。僕らだって一週間前の自分の経験を記憶だけで言えって言われたら全部不正確になりますよ。それが五十年前ですからね。ただ厳然と動かないのは、むしろ身体的記憶なんですね。まさにそれがリアリティをあかしだてている。そういうものが、言葉のレベルで考えている人たちがすっかり忘れてしまった時期に戻ってくるということがあると思うんです。」身体に宿るリアリティが証言者の語りと自由主義史観の論者の言葉遊びとを大きく分かつものであるように思われるのである。
この本は、東京新聞文化部の企画として行われた「1999を問う」というタイトルでの辺見庸と高橋哲哉の対談を一冊の本にしたものである。辺見庸は、国家と個人の関係についてその身体を通して考え続けている最も信頼できる作家であり、高橋哲哉は、歴史を記憶するという人間の倫理を出来事の衝撃性のリアリティとつなげて考えているアクティブな哲学者である。今後の日本社会の行方を大きく左右しかねない法案の成立に対して、緊張感に欠けたジャーナリズム、マスコミの中で、この2人の対談を企画した東京新聞の勇気には心打たれる。さて、1999年の第百四十五通常国会にて成立した「周辺事態法(ガイドライン法案)」「盗聴法」「国旗・国歌法」「改正住民基本台帳法」の法案について、2人は厳しく深く語り合っていく。対談では、現実を見据えることなく、記憶を忘却の彼方に追いやり、心地よい観念にひたっている社会の風潮が厳しく批判され、出来事に直面し、異質と出会うことで、身体性を回復し、全体主義に穴を穿つ道が探られる。2人の議論はきわめて具体的なので、読者にとっても説得力がある。本書の中で最も共感したのは、元従軍慰安婦の女性の証言について、高橋が次のように語っているくだりである。「元慰安婦の人たちの話というのは、言葉のレベルでは、それは違う、そんなはずはないなどと、いろいろ言われます。ただそんなの当たり前なんですよ。僕らだって一週間前の自分の経験を記憶だけで言えって言われたら全部不正確になりますよ。それが五十年前ですからね。ただ厳然と動かないのは、むしろ身体的記憶なんですね。まさにそれがリアリティをあかしだてている。そういうものが、言葉のレベルで考えている人たちがすっかり忘れてしまった時期に戻ってくるということがあると思うんです。」身体に宿るリアリティが証言者の語りと自由主義史観の論者の言葉遊びとを大きく分かつものであるように思われるのである。
それにしても先人の努力によって得られた個人の内面の自由を国家に明け渡してしまった1999年のツケは大きい。2000年代は、1999年プロジェクトを巡って厳しくせめぎ合う時代になるだろう。このとき、忘れてはならないのは、誰もが犠牲者になり得るという想像力である。自分と犠牲者とは紙一重であるという想像力である。2人の対談は次のような言葉でしめくくられている。
「高橋 犠牲者の側に立つ議論はいま、皆が受益者だと思っているせいなのか、シニカルに笑われる時代です。皆どこかで誤解をしているんじゃないですか。自分たちが永遠に受益者であり、永遠に『強者』だと。誤解ですよ、完全な。
辺見 いや、誤解ではありません。倒錯です、もはや。しかも、巧妙に仕組まれた…」

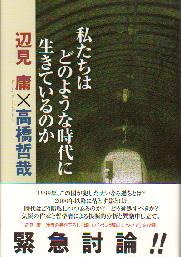 この本は、東京新聞文化部の企画として行われた「1999を問う」というタイトルでの辺見庸と高橋哲哉の対談を一冊の本にしたものである。辺見庸は、国家と個人の関係についてその身体を通して考え続けている最も信頼できる作家であり、高橋哲哉は、歴史を記憶するという人間の倫理を出来事の衝撃性のリアリティとつなげて考えているアクティブな哲学者である。今後の日本社会の行方を大きく左右しかねない法案の成立に対して、緊張感に欠けたジャーナリズム、マスコミの中で、この2人の対談を企画した東京新聞の勇気には心打たれる。さて、1999年の第百四十五通常国会にて成立した「周辺事態法(ガイドライン法案)」「盗聴法」「国旗・国歌法」「改正住民基本台帳法」の法案について、2人は厳しく深く語り合っていく。対談では、現実を見据えることなく、記憶を忘却の彼方に追いやり、心地よい観念にひたっている社会の風潮が厳しく批判され、出来事に直面し、異質と出会うことで、身体性を回復し、全体主義に穴を穿つ道が探られる。2人の議論はきわめて具体的なので、読者にとっても説得力がある。本書の中で最も共感したのは、元従軍慰安婦の女性の証言について、高橋が次のように語っているくだりである。「元慰安婦の人たちの話というのは、言葉のレベルでは、それは違う、そんなはずはないなどと、いろいろ言われます。ただそんなの当たり前なんですよ。僕らだって一週間前の自分の経験を記憶だけで言えって言われたら全部不正確になりますよ。それが五十年前ですからね。ただ厳然と動かないのは、むしろ身体的記憶なんですね。まさにそれがリアリティをあかしだてている。そういうものが、言葉のレベルで考えている人たちがすっかり忘れてしまった時期に戻ってくるということがあると思うんです。」身体に宿るリアリティが証言者の語りと自由主義史観の論者の言葉遊びとを大きく分かつものであるように思われるのである。
この本は、東京新聞文化部の企画として行われた「1999を問う」というタイトルでの辺見庸と高橋哲哉の対談を一冊の本にしたものである。辺見庸は、国家と個人の関係についてその身体を通して考え続けている最も信頼できる作家であり、高橋哲哉は、歴史を記憶するという人間の倫理を出来事の衝撃性のリアリティとつなげて考えているアクティブな哲学者である。今後の日本社会の行方を大きく左右しかねない法案の成立に対して、緊張感に欠けたジャーナリズム、マスコミの中で、この2人の対談を企画した東京新聞の勇気には心打たれる。さて、1999年の第百四十五通常国会にて成立した「周辺事態法(ガイドライン法案)」「盗聴法」「国旗・国歌法」「改正住民基本台帳法」の法案について、2人は厳しく深く語り合っていく。対談では、現実を見据えることなく、記憶を忘却の彼方に追いやり、心地よい観念にひたっている社会の風潮が厳しく批判され、出来事に直面し、異質と出会うことで、身体性を回復し、全体主義に穴を穿つ道が探られる。2人の議論はきわめて具体的なので、読者にとっても説得力がある。本書の中で最も共感したのは、元従軍慰安婦の女性の証言について、高橋が次のように語っているくだりである。「元慰安婦の人たちの話というのは、言葉のレベルでは、それは違う、そんなはずはないなどと、いろいろ言われます。ただそんなの当たり前なんですよ。僕らだって一週間前の自分の経験を記憶だけで言えって言われたら全部不正確になりますよ。それが五十年前ですからね。ただ厳然と動かないのは、むしろ身体的記憶なんですね。まさにそれがリアリティをあかしだてている。そういうものが、言葉のレベルで考えている人たちがすっかり忘れてしまった時期に戻ってくるということがあると思うんです。」身体に宿るリアリティが証言者の語りと自由主義史観の論者の言葉遊びとを大きく分かつものであるように思われるのである。