『断絶の世紀 証言の時代』
徐京植×高橋哲哉(岩波書店、2000)
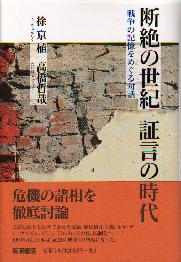 先週に引き続いて、高橋哲哉の対談。本書でのパートナーは、徐京植である。1951年に京都で生まれた在日韓国人の徐京植は、兄の徐勝、徐俊植を留学中の韓国で入獄させられるという経験をしている。彼は、祖国、愛国心、ナショナリズムについて、本気で考えなくてはならないポジションから、戦争と国家、記憶と責任といった問題を探究し続けている。
先週に引き続いて、高橋哲哉の対談。本書でのパートナーは、徐京植である。1951年に京都で生まれた在日韓国人の徐京植は、兄の徐勝、徐俊植を留学中の韓国で入獄させられるという経験をしている。彼は、祖国、愛国心、ナショナリズムについて、本気で考えなくてはならないポジションから、戦争と国家、記憶と責任といった問題を探究し続けている。
徐は、ナチスドイツによるユダヤ人強制収容所のダッハウを訪ねたとき、「バラック跡の土台だけが整然と残る」その地に「すさまじい暴力の気配」を感じ、「膝から力が抜けてしまうという経験を味わ」ったという。ホロコースト(大量虐殺)の悲劇は、強制収容所における非人道的な行為だけではなく、奇跡的に生き残った人々を襲う「自分たちの経験が他の人びとになかなか伝わらないという苦悩」という二重の形で訪れるという。高橋はこのことをアーレントの言葉を引用しながら、「「正常な世界」の「正常性」そのものがサバイバーの言葉を受け止めることを困難にしている」と述べ、日本においても「戦後の高度成長の時代を生きてきた「普通の日本人」の「普通さ」が実は潜在的な否定論を含んでいる」と指摘している。
人間にとって時間の経過とともに忘れることは「自然」なことである。しかし、自分の生活を踏みにじられた人々は、そのときの痛みを忘れることはない。そうであるならば、加害者とそれに連なる人々が、「自然」に忘れることは、被害者にとって暴力である。もちろん、そこには赦しというものがあるだろう。しかしながら、赦しの前提には、謝罪が当然あるべきだろうし、謝罪には責任主体を明らかにすることが伴わなくてはならないだろう。「普通」であることや「自然」であることに抗(あらが)っていかなくては、歴史を継承し、そこから学ぶことはできないのである。高橋と徐の対談は、私たちの「普通」「自然」に対して、ゴツゴツとぶつかってくる。
敗戦ののち、私たちの国家は、自分たちの意志で、自分たちの責任を問うことがないまま、今に至っている。東京裁判において裁かれることはあったにせよ、自らの力で戦争の責任者を明らかにすることは一度もしていない。そして、A級戦犯が首相になり、1999年には日の丸・君が代の法制化も行った。徐はこの法制化の意義について「日本は結局変わらなかったし、今後も変わるつもりはないと内外に向けて宣言するに等しい行為だと私はとらえています。第二次世界大戦という二〇世紀最大の政治暴力の経験のあと、結局変わらず、変わるつもりはないということを昂然と宣言する、ほとんど唯一の国として日本が浮かび上がってくるでしょう」と述べている。
1999年、日本は歴史の忘却に向けて大きな一歩を踏み出した。しかし、まだ諦めてしまうには早すぎる。1990年代には、元従軍慰安婦の人々が名乗り出て、私たちに語ってくれたり、加害体験を語り記す元日本軍兵士の人々も現れた。これらの語りと身体は、私たちの心に焼き付いている。小さな事実に目をひらき、他者にひらかれながら、自分自身のものの見方を捉え直し、「普通」「自然」に抗っていく人々とつながりつつ、個を鍛えていく道が残されている。

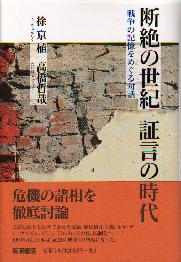 先週に引き続いて、高橋哲哉の対談。本書でのパートナーは、徐京植である。1951年に京都で生まれた在日韓国人の徐京植は、兄の徐勝、徐俊植を留学中の韓国で入獄させられるという経験をしている。彼は、祖国、愛国心、ナショナリズムについて、本気で考えなくてはならないポジションから、戦争と国家、記憶と責任といった問題を探究し続けている。
先週に引き続いて、高橋哲哉の対談。本書でのパートナーは、徐京植である。1951年に京都で生まれた在日韓国人の徐京植は、兄の徐勝、徐俊植を留学中の韓国で入獄させられるという経験をしている。彼は、祖国、愛国心、ナショナリズムについて、本気で考えなくてはならないポジションから、戦争と国家、記憶と責任といった問題を探究し続けている。