『教師は敗戦をどうむかえたのか−苦悩と模索の日々・2年間の教育日誌−』
永井健児(教育史料出版会、1998)
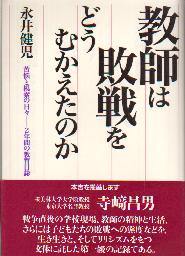 最近、東京経済大学の教育実習講義にゲストとして来て下さった高校の先生が「戦争を体験していない自分が戦争を教えるということ、この葛藤に苦しんだ」というお話をされた。その先生は戦争体験者の声を聴き、その話を語り部として教室に持ち込むという方法を掴まれたのだが、体験していない戦争を教え、語ることへの畏怖こそ、戦争を学ぶ上での根底になるものではないだろうか。
最近、東京経済大学の教育実習講義にゲストとして来て下さった高校の先生が「戦争を体験していない自分が戦争を教えるということ、この葛藤に苦しんだ」というお話をされた。その先生は戦争体験者の声を聴き、その話を語り部として教室に持ち込むという方法を掴まれたのだが、体験していない戦争を教え、語ることへの畏怖こそ、戦争を学ぶ上での根底になるものではないだろうか。
さて、この本は、敗戦間近の昭和20年4月に群馬県高崎市の東国民学校(現、小学校)に17歳の助教(代用教員)として赴任した永井健児氏が、日々の思い、子どもたちとの交流、戦時期の職員室の様子、敗戦にとまどう教師たちの姿をリアルタイムで綴った貴重な記録である。著者は、ただでさえ混沌の中に投げ込まれる教職初任期を、弱冠17歳にて、しかも戦時中、敗戦、戦後という激動の時代の中で経験している。一日一日の密度が濃く、戦時中の日本という洞窟の中にいた著者が、日々の経験と子どもの姿への手探りのなかで、広い認識を求めて彷徨う姿が、読者の胸を打つ。
玉音放送の翌日の8月16日、「虚脱状態とはこういった状況をいうのであろう。本や机、荷物などの整理をして、ただなんとなくすごす。…子どもたちはどうしているだろうか。あれほど、いや、昨日まで、日本の究極の勝利を子どもたちに信じさせておいて、あれはどうしたらよいのであろうか」と自問する著者が、敗戦後、はじめて子どもたちの前に向き合うシーンは、緊迫感にあふれていた。

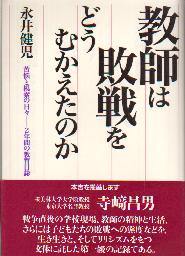 最近、東京経済大学の教育実習講義にゲストとして来て下さった高校の先生が「戦争を体験していない自分が戦争を教えるということ、この葛藤に苦しんだ」というお話をされた。その先生は戦争体験者の声を聴き、その話を語り部として教室に持ち込むという方法を掴まれたのだが、体験していない戦争を教え、語ることへの畏怖こそ、戦争を学ぶ上での根底になるものではないだろうか。
最近、東京経済大学の教育実習講義にゲストとして来て下さった高校の先生が「戦争を体験していない自分が戦争を教えるということ、この葛藤に苦しんだ」というお話をされた。その先生は戦争体験者の声を聴き、その話を語り部として教室に持ち込むという方法を掴まれたのだが、体験していない戦争を教え、語ることへの畏怖こそ、戦争を学ぶ上での根底になるものではないだろうか。