『新編八犬伝綺想』
小谷野敦(ちくま学芸文庫、2000)
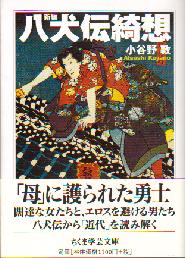 個人的に今年の大ヒット作品である。夏の帰省の列車のなかで、この本を読みながら、脳がケタケタと笑っていた。著者は、滝沢馬琴の『南総里見八犬伝』を構造主義の視点から丹念に読み、この物語が今までいわれてきたような勧善懲悪の物語ではなく、きわめて近代的な作品であるということを証明していく。八犬士の異様なまでの貞節の固さは、決して封建道徳によるものではなく、エロスへの恐れであると著者は論じる。すなわち女性を自然と同一視し、流動するもの、得体の知れないものを毛嫌いし、すべてを制御可能なものへと方向づける意志、これこそが近代であり、著者は『八犬伝』を日本に近代的な心性が登場したことを告げ知らせる作品として読み解くのである。
個人的に今年の大ヒット作品である。夏の帰省の列車のなかで、この本を読みながら、脳がケタケタと笑っていた。著者は、滝沢馬琴の『南総里見八犬伝』を構造主義の視点から丹念に読み、この物語が今までいわれてきたような勧善懲悪の物語ではなく、きわめて近代的な作品であるということを証明していく。八犬士の異様なまでの貞節の固さは、決して封建道徳によるものではなく、エロスへの恐れであると著者は論じる。すなわち女性を自然と同一視し、流動するもの、得体の知れないものを毛嫌いし、すべてを制御可能なものへと方向づける意志、これこそが近代であり、著者は『八犬伝』を日本に近代的な心性が登場したことを告げ知らせる作品として読み解くのである。
八犬士たちは、エロスを忌避し、あたかも母伏姫の子宮に回帰するかのように、安房の国に結集する。南の楽園=ユートピア神話、そして道理のない戦争、著者の読み解く『八犬伝』には、近代日本が歩む道が凝縮されている。さらに「全ての子をひとしなみに扱う平等主義・民主主義、そして進歩主義は、無機的な少年たちとこれを統べる母的なものとの密接な関係をもつ。母・伏姫は子供らに無限の力を与え、大敵との決戦に送り出す。母性と近代が日本において類稀な結合を示したのは、その両者が子供らに<人間の限界>を教えることができない、という一点においてぴたりと一致していたからである。」という文章は、今の子どもたち、あるいは大きな子どもたち(大人)の危機の所在を、明確に示している。古今東西の文献を渉猟し、読み物としても愉しいこの作品が、著者の修士論文であるというのも驚きである。1990年の初版は、時代にあまりにも先駆け過ぎたのであろう。今、ちょうど時代がこの著作に追いついているようである。

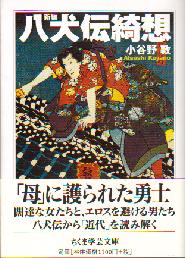 個人的に今年の大ヒット作品である。夏の帰省の列車のなかで、この本を読みながら、脳がケタケタと笑っていた。著者は、滝沢馬琴の『南総里見八犬伝』を構造主義の視点から丹念に読み、この物語が今までいわれてきたような勧善懲悪の物語ではなく、きわめて近代的な作品であるということを証明していく。八犬士の異様なまでの貞節の固さは、決して封建道徳によるものではなく、エロスへの恐れであると著者は論じる。すなわち女性を自然と同一視し、流動するもの、得体の知れないものを毛嫌いし、すべてを制御可能なものへと方向づける意志、これこそが近代であり、著者は『八犬伝』を日本に近代的な心性が登場したことを告げ知らせる作品として読み解くのである。
個人的に今年の大ヒット作品である。夏の帰省の列車のなかで、この本を読みながら、脳がケタケタと笑っていた。著者は、滝沢馬琴の『南総里見八犬伝』を構造主義の視点から丹念に読み、この物語が今までいわれてきたような勧善懲悪の物語ではなく、きわめて近代的な作品であるということを証明していく。八犬士の異様なまでの貞節の固さは、決して封建道徳によるものではなく、エロスへの恐れであると著者は論じる。すなわち女性を自然と同一視し、流動するもの、得体の知れないものを毛嫌いし、すべてを制御可能なものへと方向づける意志、これこそが近代であり、著者は『八犬伝』を日本に近代的な心性が登場したことを告げ知らせる作品として読み解くのである。