『20世紀は人間を幸福にしたか』
柳田邦男(講談社、1998)
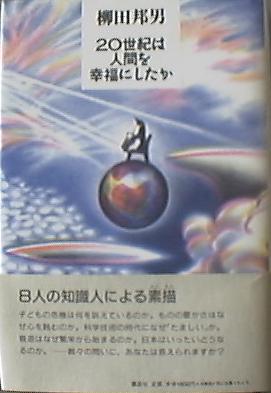 著者の柳田邦男は、NHK記者を経て、ノンフィクション作家になったが、愛息の死をきっかけに、脳死問題に取り組むことになる。自死を図り、脳死状態になった愛息をみとった11日の日々を見つめた『犠牲(サクリファイス) わが息子・脳死の11日』は、身内や親しい者の死(2人称の死)の重さを考えさせる名著であった。今回紹介した『20世紀は人間を幸福にしたか』では、著者は、その個人的な経験から抽出された「一人ひとりの人間の幸・不幸」というわたしたちにとってのっぴきならない観点から、子どもの危機、あふれる医療のなかの生きる感覚の欠如、豊かさのなかの空虚さなどのテーマに、真摯に向き合っている。
著者の柳田邦男は、NHK記者を経て、ノンフィクション作家になったが、愛息の死をきっかけに、脳死問題に取り組むことになる。自死を図り、脳死状態になった愛息をみとった11日の日々を見つめた『犠牲(サクリファイス) わが息子・脳死の11日』は、身内や親しい者の死(2人称の死)の重さを考えさせる名著であった。今回紹介した『20世紀は人間を幸福にしたか』では、著者は、その個人的な経験から抽出された「一人ひとりの人間の幸・不幸」というわたしたちにとってのっぴきならない観点から、子どもの危機、あふれる医療のなかの生きる感覚の欠如、豊かさのなかの空虚さなどのテーマに、真摯に向き合っている。
この本は、柳田邦男と8人の知識人たちとの対話によって構成されているが、そのなかでも、第二章の星野一正(生命倫理、解剖学)との対話が、わたしには一番印象に残った。この章では、人間の感情と科学的事実の問題が扱われている。柳田は次のように語っている。
「科学のレベルでは、脳が死ねばいずれ時間の問題で心臓も止まる。その人は意識も感覚も戻らないから屍体だということになる。しかし、そういう科学主義に人間の感情の部分がなぜ従わなきゃいけないのか。科学的事実はこうなんだから、現代人はこういう感情を持てというのは本末転倒です。科学は判断のひとつの材料であって、それに人間が支配されるものではない。科学の進歩による死のプロセスの変化を認めつつ、同時に古来の人間の自然な感情や家族の関係性を大事にするという柔軟な考え方を保障する社会システムこそ、これからは求めていくべきでしょう。」
これまで近代の科学は、大雑把にいえば<専門家がすべて知っている。下々の者は黙って従えばいい。>という原理によってなりたってきた。しかし、今や、政治においても、教育においても、医療においても、この原理が行き詰まっている。専門家のあり方が大きく問われる、そのような地点にわたしたちは立っているように思う。

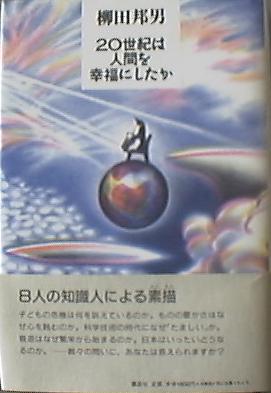 著者の柳田邦男は、NHK記者を経て、ノンフィクション作家になったが、愛息の死をきっかけに、脳死問題に取り組むことになる。自死を図り、脳死状態になった愛息をみとった11日の日々を見つめた『犠牲(サクリファイス) わが息子・脳死の11日』は、身内や親しい者の死(2人称の死)の重さを考えさせる名著であった。今回紹介した『20世紀は人間を幸福にしたか』では、著者は、その個人的な経験から抽出された「一人ひとりの人間の幸・不幸」というわたしたちにとってのっぴきならない観点から、子どもの危機、あふれる医療のなかの生きる感覚の欠如、豊かさのなかの空虚さなどのテーマに、真摯に向き合っている。
著者の柳田邦男は、NHK記者を経て、ノンフィクション作家になったが、愛息の死をきっかけに、脳死問題に取り組むことになる。自死を図り、脳死状態になった愛息をみとった11日の日々を見つめた『犠牲(サクリファイス) わが息子・脳死の11日』は、身内や親しい者の死(2人称の死)の重さを考えさせる名著であった。今回紹介した『20世紀は人間を幸福にしたか』では、著者は、その個人的な経験から抽出された「一人ひとりの人間の幸・不幸」というわたしたちにとってのっぴきならない観点から、子どもの危機、あふれる医療のなかの生きる感覚の欠如、豊かさのなかの空虚さなどのテーマに、真摯に向き合っている。