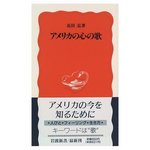・最近のテレビには気になるところがずいぶんある。たとえば、事件が起きたときにくりかえされる、きわめて感情的な報道、バラエティ番組の多さ、というよりは何でもバラエティ形式にしてしまう安直で画一的な作り方、特定の話題、人物への極端に偏った注目等々、あげたらきりがない。
・テレビは一見、新しいモノゴトをいち早く伝えるメディアのように思われるけれども、そこにはきまって、古いおきまりの味つけがされている。常識はずれをやっているように見えても、またきわめて常識的な枠取りがされている。だから、わかりにくさは排除されるし、多様性は無視される。その意味で、テレビは保守的なメディアだが、このような傾向が、ますます顕著になっている気がする。テレビなんてしょせん、そんなしょうもないメディアだ!と言ってしまえばそれまでだが、一方でその影響力はものすごく大きい。
・伊藤守の『記憶・暴力・システム』は、そんなテレビの力を、それをささえる社会やテクノロジーのシステム、介入する政治的・経済的権力、そこで使われる「言説」の特徴や作り出される「テレビ的リアリティ」の分析をテーマにしている。テレビについて批判理論を展開させようとする意欲作だと言える。この本が最初に問題提起しているのは、おおよそ次のようなことだ。
・だれかが何か発言しようと思う。あるいは発言せざるを得ないと感じたとする。それはおそらく、大多数が共有する価値や見解とは相容れないか、あるいははずれたものだ。そうすると、どういうことが起こるか。メディア、とりわけテレビはまず、それを無視しようとする。無視できないものであれば、大多数が共有するはずの「常識」を盾にして、あるいは矛にして批判し、押しつぶしにかかる。あるいは論旨のすりかえといったこともあるだろう。その意味で、テレビに自由で気ままが許されるのは、あくまで「常識」の範囲内のことにかぎられる。
・大多数が共有する価値や見解を「常識」として押し付ける強力な圧力を形成するメディア、日々の経験を自明なものに編制し、しかもその自明性を、変化をともないながら組み替える強力なパワーをもったメディアに焦点をおきながら、メディア文化の生産と消費をふくむコミュニケーション構造全体の問題と、それを消費するオーディエンスの行為を考えることが本書に収録した文章の狙いだった。(p.vii)
・政治的な対立点が曖昧になり、ことの善悪も真偽もわかりにくい世界になっている。そんな中でテレビは、一方でなかば無意識のうちにおこる感情や欲望に訴えかけ、他方でまたきわめてわかりやすい常識や慣行を持ち出してくる。みずから火をつけ、事を荒立てておきながら、またあたかも裁判官のような態度をしめして、それを沈静化させようとする。テレビは曖昧な世界をますます増幅させるが、そうであればこそなおさら、それをわかりやすくすることにも懸命になる。まさに「マッチ・ポンプ」の世界である。
・もちろん、視聴者である私たちは、そのような意図にまったく無自覚だというわけではない。むしろ、そんなテレビをけなし、冷ややかに嗤うことを視聴態度の一つにさえしている。けれども、できるのは、その程度のことでしかない。テレビに映ったものへの関心度に比べて、映らないものへのそれが、ほとんどゼロに近いとすれば、どんなに批判的な態度をとったとしても、テレビに囲い込まれていることに違いはないのである。
・天皇の戦争責任を追及して開かれた「女性国際戦犯法廷」をNHKがドキュメントして放送した。2001年の話だが、この番組は、「法廷」の内容を改竄したと主催者に訴えられた一方で、今年になって、番組を制作したNHKのディレクターによって、自民党の政治家から、内容変更についての強い圧力があったというリークもされている。この問題を大きく取りあげた朝日新聞とNHKとの間、さらにはそこに安部、中川の自民党議員が加わった議論があって、しばらく音沙汰なかったが、7月25日の朝日新聞で、リーク記事以降の経過がまとめられた。
・記事によれば、自民党議員、とくに中川昭一ははっきりと、変更した番組の放送中止を求めているし、NHKの予算をとおすべきではないと言っている。偏向しているから放送をしてはいけないというのは、一見もっともらしいが、偏向であるかないかの規準がどこにあるのかははっきりしないし、それ以上に、多様な考えや主張を偏向という名で閉め出したのでは、結局、常識という名の体制的な考えで一色に染まってしまうことになる。権力の側にたつ者が判断した「偏向」のレッテル張りは明らかに、逆サイドへの偏向である。NHKはもちろん、反論したが、夜の7時のニュースでは、トップではなくスポーツに移る前だった。
・『記憶・暴力・システム』には、「法廷」とそのドキュメントとの間にあるずれをテーマにした章がある。2003年に発表されたものだが、そこで問われているのは、テレビ的リアリティが歪曲する「記憶」の問題である。
・この改竄問題から、私たちはなにを読みとるべきなのだろうか。それは、「天皇の戦争責任」、そして日本軍「慰安婦」といった事柄を、私たちが想起すべき過去の記憶、公共の記憶としてはふさわしくないものとして構造的に排除するコミュニケーション構造の暴力性である。(p.95)
・天皇を戦犯にしたくない、してはいけないとする考え方が、公共の記憶を、天皇の戦争責任を問わない方向で作り上げてきた。あるいは外国人に強制した従軍慰安婦などはなかったことにとしたいという気持ちが、その事実を公共の記憶から消し去ってきた。「女性国際戦犯法廷」はそこを断罪し、NHKのなかにも、それを放送する必要性を自覚する人がいたわけだが、またそれは、公共の記憶を否定する告発であったために、政治権力の介入を招くことにもなった。
・私たちは、こういった問題にどうしようもなく鈍感になっている。あるいは、自覚し、共感していても、それを話題にすることにわずらわしさを感じるようになっている。それはテレビが提供する常識的でわかりやすいリアリティに安住しているほうが圧倒的に楽だからだ。「テレビ的リアリティ」は「あまりに日常の一部となっているために真剣に意識されて行われているわけではないテレビを見るという行為と、公平と客観性のスローガンの下に本質的な対立点や論争点を曖昧化するテレビジョン特有のテクスト構成、という二つの相補的な関係性から成立する。」(p.98)
・著者は、それが分厚い皮膜のようになってテレビとその視聴者を覆っているという。テレビ的リアリティこそが唯一の現実ということになったら、それこそオーウェルが描いた逆ユートピアそのものだが、皮肉なことに、テレビがもたらすリアリティは、そこに安住していればそれなりに自由で幸福な生活を実感させてくれたりもする。皮膜の分厚さをいまさらながらに思い知らされる気がするが、それが見えないものではなく、目に見える形で露骨になっている。 (2005.07.25)